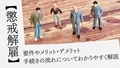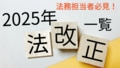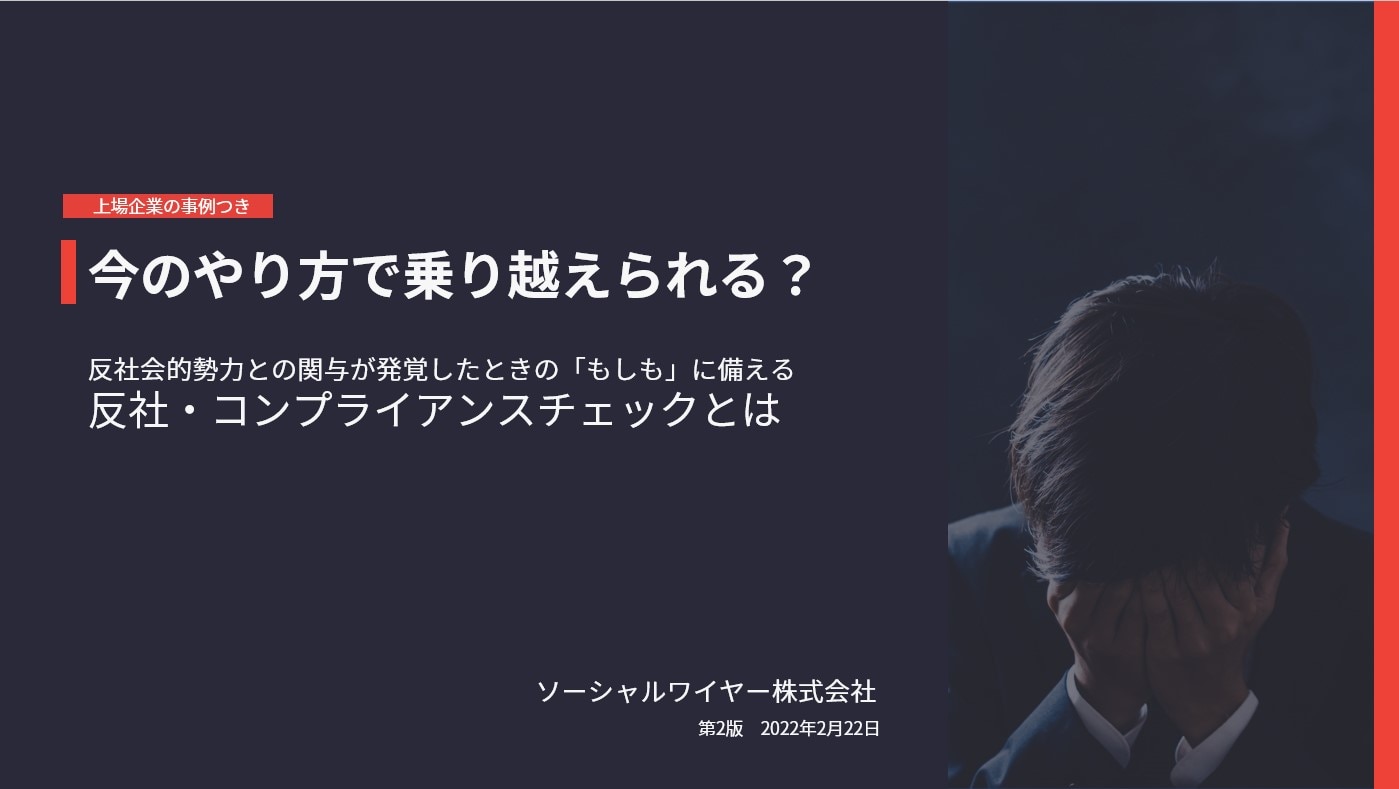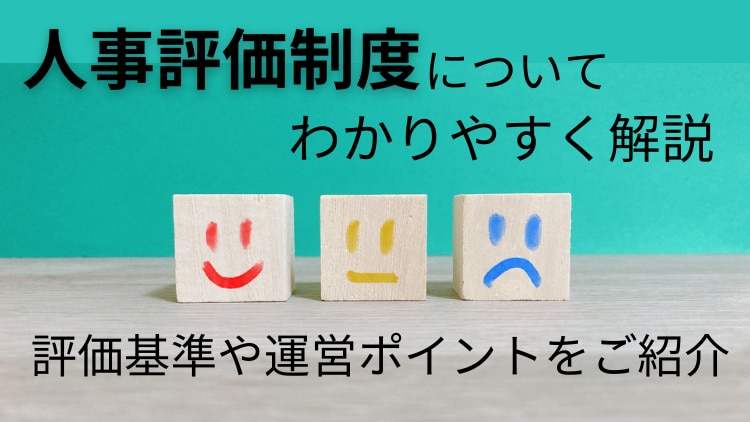
人事評価制度についてわかりやすく解説!評価基準や運営ポイントをご紹介
人事評価制度は、企業と従業員の成長を支える重要な仕組みです。
この記事では、人事評価制度の基本的な仕組みから、評価基準や具体的な運営ポイントまでをわかりやすく解説します。
また、業績評価や能力評価、さらには公平性を保つための絶対評価の重要性など、制度を効果的に活用するための知識を幅広くご紹介します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【初心者必見】反社チェックのやり方・業務フローまとめ
目次[非表示]
- 1.人事評価とは
- 2.人事評価の目的
- 2.1.企業の方針や目標などの明示
- 2.2.従業員の育成
- 2.3.適材適所への人材配置
- 2.4.公正な処遇の決定
- 3.人事評価制度における3つの評価基準
- 4.最新の6つの人事評価制度
- 4.1.コンピテンシー評価
- 4.2.目標管理制度(MBO:Management By Objectives)
- 4.3.360度評価
- 4.4.ピアボーナス
- 4.5.バリュー評価
- 4.6.OKR(Objectives and Key Results)
- 5.人事評価制度の運営ポイント
- 5.1.評価基準の見える化
- 5.2.具体的な評価項目の設定
- 5.3.フィードバック面談を実施
- 5.4.評価エラーの防止
- 5.5.基本的に絶対評価で運営することを原則とする
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの基本を学ぶ】
人事評価とは

人事評価制度は、企業と従業員の双方にとって重要な役割を果たします。
この評価の仕組みによって、企業は従業員の能力や業績を適切に把握し、従業員のスキル向上やキャリア形成を支援することができます。
一方で、従業員は公正な評価を受けることでモチベーションが向上し、さらなる成果への意欲を高められます。
効果的な人事評価制度を構築することで、企業全体の成長と活力を促進できます。
人事評価の概要
人事評価とは、従業員の業務成果や能力、職場での態度などを総合的に評価する仕組みを指します。
この制度は、企業が従業員のパフォーマンスを把握し、適切なフィードバックを提供するための重要な役割を果たします。
評価は、企業の目標や方針に基づいて行われ、従業員個々の成長を促進することを目的としています。
また、人事評価は単なる査定にとどまらず、従業員のキャリア形成やモチベーション向上にも貢献するプロセスです。
人事考課との違い
「人事評価」と「人事考課」は、似たような言葉ですが異なる側面があります。
人事考課は主に従業員の現状を把握し、能力や勤務態度を評価することに重点を置いています。
一方で、人事評価は中長期的な視点を持ち、企業の戦略目標や従業員の潜在的な能力を考慮して行われます。
具体的には、人事評価は個々の成績やスキルだけでなく、将来的な成長可能性や適性も重視します。
この違いによって、人事評価はより戦略的かつ総合的な判断を下すための制度となっています。
関連記事:人事制度とは?3本柱とその役割、制度構築のフローを解説
人事評価の目的

人事評価制度には、企業の成長を促進し、従業員の能力を最大限に引き出すという重要な役割があります。
その具体的な目的を以下に詳しく解説します。
企業の方針や目標などの明示
人事評価は、企業が掲げるビジョンや目標を従業員に明確に示す重要なツールです。
これにより、個々の従業員が自身の業務が全体の目標にどのように関連しているのかを理解が深まります。
また、評価制度を通じて目標を共有することで、組織全体の一体感が生まれ、効率的な業務推進が可能となります。
従業員の育成
人事評価のもう一つの重要な目的は、従業員の成長を支援することです。
評価を通じて、各従業員の強みや課題が明確になります。
この情報を基に、スキルアップを促す研修やキャリアパスの設計が行えます。
さらに、フィードバックを適切に提供することで、従業員は自身の能力を客観的に見つめ直し、成長への意欲を高めることができます。
関連記事:タレントマネジメントとは?基礎知識や導入方法、メリット、注意点をわかりやすく解説
適材適所への人材配置
適切な人材を適切な役割に配置することは、組織の成功に欠かせません。
人事評価を通じて、従業員の特性や能力が把握できるため、適材適所の人材配置が可能になります。
これにより、業務の効率化と従業員満足度の向上が期待されます。
公正な処遇の決定
人事評価は、公平で透明性のある処遇を実現する基盤でもあります。
明確な評価基準を設けることで、従業員は公平に評価されるという安心感を持つことができます。
これにより、組織内の信頼関係が強化され、従業員のモチベーション向上や離職率の低下にも寄与します。
関連記事:人材育成とは?注目される理由や育成の目的、方法をわかりやすく解説
人事評価制度における3つの評価基準
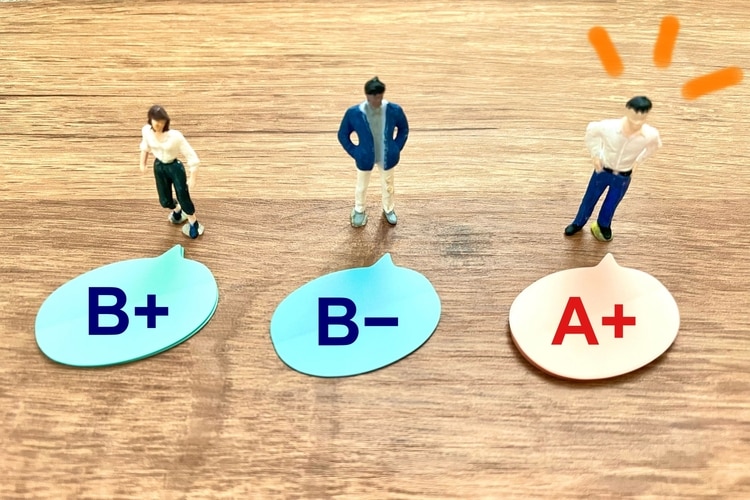
従業員を公正かつ効果的に評価するために、企業は明確な評価基準を設ける必要があります。
一般的に、人事評価制度では「業績評価」「能力評価」「情意評価」という3つの基準が使用されます。
それぞれの評価基準について詳しく説明します。
業績評価
業績評価は、従業員が設定された業務目標をどれだけ達成したかを評価する基準です。
この評価は、従業員の働きが企業全体の成果にどの程度寄与しているのかを具体的に測定するための重要な指標となります。
企業が持続的に成長するためには、従業員一人ひとりが業績を積み上げる必要があります。
そのため、業績評価は目標達成度、課題解決能力、日々の業務での成果などを詳細に分析する仕組みです。
- 業績目標達成度:企業の掲げる短期および長期の目標に対し、従業員がどれだけ貢献したかを評価します。達成度を数値化することで、評価の透明性を高めます。
- 課題目標達成度:業務上の課題に取り組む姿勢と成果を評価します。特に困難な課題を解決する能力は業績評価の重要なポイントです。
- 日常業務成果:日々の業務での生産性や具体的な貢献度を評価します。これにより従業員の普段の働きが持つ価値を測ります。
これらの評価項目を総合的に判断することで、従業員の実績を公平に評価し、さらなる成長を促します。
関連記事:人材マネジメントとは?その内容や必要性、ポイントを解説
能力評価
能力評価は、従業員が業務を効率的かつ効果的に遂行するために必要なスキルや知識を測る基準です。
従業員の能力は、企業の競争力を左右する重要な要素であり、適切な評価によって従業員の能力を最大限発揮させることに期待できます。
この評価基準では、以下のような具体的な能力が分析されます。
- 企画力:新しいアイデアや計画を立案する能力。創造的な発想は企業の革新を支える基盤です。
- 実行力:計画を効率的かつ確実に進行させる能力。結果を出す力を評価します。
- 知識:業務に必要な専門的な知識を評価し、従業員の業務遂行能力の深さを測ります。
- 育成力:他者を指導し、チーム全体のスキルアップを促す能力。リーダーシップの一環として重要視されます。
- 改善力:現状を見直し、より良い方法を提案する能力。業務プロセスの効率化に寄与します。
このように、能力評価は従業員の個々の特性を細かく分析し、それに基づいた適切な支援を可能にします。
情意評価
情意評価は、従業員の職場での態度や人間関係における行動を評価する基準です。
良好な職場環境を保つためには、従業員の責任感や協調性が重要であり、それらを正確に測ることが求められます。
情意評価は従業員同士の信頼関係やコミュニケーション能力を向上させる土台となります。
- 責任性:責任ある行動を取る能力を評価し、業務遂行の信頼性を測ります。
- 積極性:自発的に行動し、問題解決に積極的に取り組む姿勢を評価します。この評価項目は、従業員が革新を促進する能力を示します。
- 協調性:チームでの円滑なコミュニケーションや協力体制を築く能力を評価します。これにより、職場の一体感とチームワークの品質が向上します。
情意評価は、職場環境を向上させ、従業員間の信頼関係を構築するための重要な役割を果たします。これにより、組織全体の活力を高める効果が期待できます。
関連記事:採用のミスマッチを防ぐリファレンスチェックとは?メリット・デメリットについて解説
最新の6つの人事評価制度

人事評価制度とは、企業が従業員を公正かつ包括的に評価するための重要な仕組みです。
近年、従業員の能力や業績を適切に評価するために様々な新しい手法が導入されています。
ここでは、最新の6つの人事評価制度について詳しく解説します。
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価は、特定の役割で必要とされる行動やスキルに焦点を当てた評価方法です。
この制度では、従業員が持つ行動特性や能力が評価の主な基準となります。
例えば、リーダーシップや問題解決能力、コミュニケーション能力など、業務遂行に必要な具体的な能力を測ります。
コンピテンシー評価は、従業員が特定の職務で成功するための条件を明確にするため、適材適所への配置を促進します。
目標管理制度(MBO:Management By Objectives)
目標管理制度は、従業員自身が目標を設定し、それを達成することで評価される仕組みです。
この制度では、上司と従業員が共同で具体的な目標を設定し、進捗を定期的に確認します。
目標達成のプロセスを重視することで、従業員のやる気を引き出し、業績向上につなげます。
また、目標が明確に示されることで、評価基準の透明性と公正性が高まります。
関連記事:採用担当者必見!中途採用の成功事例と成功させるポイントを徹底解説
360度評価
360度評価は、従業員を複数の視点から総合的に評価する方法です。
上司、同僚、部下、さらには顧客や取引先からのフィードバックを取り入れることで、多角的な評価が実現できます。
この制度は、従業員の強みと改善点をより正確に把握し、個人の成長を支援するために役立ちます。
また、他者の視点を取り入れることで、評価に偏りが生じにくいという利点があります。
ピアボーナス
ピアボーナスは、従業員同士が互いの貢献を認め合い、ボーナスを贈る評価方法です。
この制度は、従業員間のコミュニケーションやチームワークを促進し、職場の連帯感を強化する目的で導入されています。
ピアボーナスを通じて、従業員は自分の仕事がどのように他者に影響を与えているのかを実感し、モチベーション向上につながります。
関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説
バリュー評価
バリュー評価は、企業が掲げる価値観に沿った行動や成果を評価する制度です。
この評価方法では、企業文化や理念に基づいた従業員の行動が重視されます。
例えば、「チームワークを重んじる」「顧客満足を最優先にする」といった企業理念に基づいて従業員がどのように貢献しているのかを評価します。
この制度は、企業と従業員の価値観の統一を図る役割を果たします。
OKR(Objectives and Key Results)
OKRは、目標とその達成を測る指標を設定する評価方法です。
この制度では、大きな目標を設定し、それを達成するための具体的な成果指標を定めます。
定期的な進捗確認を行うことで、目標への取り組みが可視化されます。
OKRは、組織全体の方向性を統一し、従業員一人ひとりが自身の目標達成に集中できる環境を提供します。
関連記事:戦略人事とは?メリットや必要な機能、成功させるためのポイントを解説
人事評価制度の運営ポイント

人事評価制度を効果的に運営するためには、明確な基準と透明性が不可欠です。
企業が従業員を公平に評価し、成長を支援するためには、運営ポイントを徹底する必要があります。
ここでは、その重要なポイントについて詳しく解説します。
評価基準の見える化
評価基準を明確にし、従業員に示すことは、人事評価の公平性を確保するための第一歩です。
基準が曖昧だと、従業員は評価の結果に疑念を抱き、モチベーションを損なう可能性があります。
見える化された基準を導入することで、従業員は自分が何を求められているのかを理解しやすくなり、業務目標に集中しやすくなります。
また、評価基準の見える化は管理者にとっても有益であり、評価の際の判断材料がより具体的になります。
具体的な評価項目の設定
評価基準に基づき、具体的かつ客観的な評価項目を設定することが必要です。
例えば、「業績目標達成度」や「責任感」といった具体的な項目を挙げることで、評価の透明性が高まり、従業員が納得できる仕組みを構築できます。
また、具体的な評価項目を設定することで、従業員の業績や態度を細かく分析することが可能となり、正確なフィードバックを提供できます。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
フィードバック面談を実施
評価結果を従業員に伝えるだけでなく、フィードバック面談を通じて具体的なアドバイスや改善点を共有することが重要です。
この面談の目的は、単なる評価ではなく、従業員の成長を支援することにあります。
建設的なフィードバックを提供することで、従業員は自身の強みや改善点を理解し、業務への取り組みをより効果的にすることができます。
評価エラーの防止
評価の公平性を損なう要因である評価エラーを防止することは、制度を適切に運営するために欠かせません。
例えば、管理者の主観や先入観が評価に影響を与える場合、従業員が不満を抱える可能性があります。
そのため、管理者への教育や評価プロセスの標準化を通じて、評価エラーのリスクを最小限に抑えることが重要です。
基本的に絶対評価で運営することを原則とする
人事評価では、絶対評価を基本とすることが推奨されます。
絶対評価は、他者との比較ではなく、従業員個々の成果や基準に基づいて行われる評価方法です。
この運営方法は、従業員に公平感を与えるだけでなく、個々の成長に焦点を当てることを可能にします。
関連記事:企業が取り組むべきハラスメント対策 その重要性とメリットを解説
まとめ
人事評価制度は、企業と従業員双方の成長を促進する重要な仕組みです。
評価基準や目的を明確にし、公平性を確保することで、従業員のモチベーション向上や適材適所への配置が可能になります。
また、評価結果を基にしたフィードバックやスキルアップ支援により、企業全体の活力も高まります。
関連記事:人材管理の方法は?手順やメリット、データベースの作成方法を解説
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説