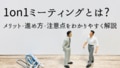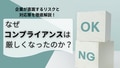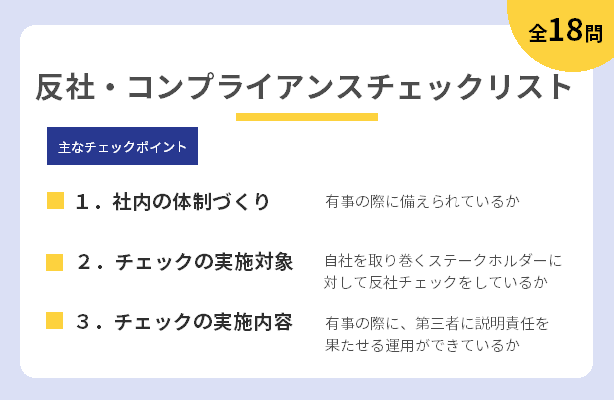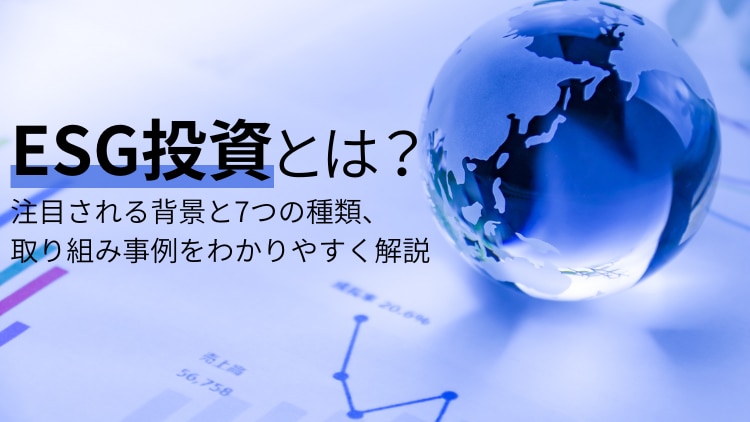
ESG投資とは?注目される背景と7つの種類、取り組み事例をわかりやすく解説
環境・社会・ガバナンスに配慮した「ESG投資」が、持続可能な経営の鍵として注目を集めています。
SDGsの浸透や投資家の価値観の変化により、企業のESG対応が評価軸に。
この記事では、ESG投資の基本から7つの手法、企業の実践事例までをわかりやすく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら
目次[非表示]
- 1.ESG投資とは
- 1.1.ESG投資が注目される背景
- 1.1.1.SDGsへの関心の高まり
- 1.1.2.投資家の意識変化
- 1.1.3.日本の年金を運用する「GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)」も推進
- 2.ESG投資の7つの種類
- 2.1.ポジティブスクリーニング
- 2.2.ネガティブスクリーニング
- 2.3.国際規範スクリーニング
- 2.4.ESGインテグレーション
- 2.5.サステナビリティ・テーマでの投資
- 2.6.インパクト投資
- 2.7.エンゲージメント/議決権行使
- 3.ESG投資を意識した経営を行うメリット
- 3.1.投資家からの評価向上
- 3.2.経営の長期的な安定
- 3.3.キャッシュフローの増強による企業の成長
- 4.企業のESGに関する取り組み事例
- 4.1.環境に配慮した自社製品の製造
- 4.2.グループ企業でガバナンスを強化
- 4.3.廃棄物の極小化
- 4.4.環境に配慮されたオフィス家具・設備の導入
- 4.5.オフィスの省エネ対策を強化
- 4.6.環境に配慮したオフィスへの移転
- 5.ESG投資に取り組む際の注意点
- 5.1.長期的な視点での取り組みと評価をする
- 5.2.ESGへの取り組みのアピールも重要
- 5.3.統一的な評価基準はない
- 6.まとめ
ESG投資とは
 ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3要素を重視して行う投資手法です。
ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3要素を重視して行う投資手法です。
従来の財務指標だけでなく、企業の持続可能性や社会的責任を評価軸に加えることで、長期的な成長とリスク管理を両立させるアプローチとして注目されています。
気候変動や人権問題、企業統治の透明性など、非財務情報が企業価値に直結する時代において、ESG投資は新たなスタンダードとなりつつあります。
ESG投資が注目される背景
ESG投資が急速に広がっている背景には、社会全体の価値観の変化と政策的な後押しがあります。
環境問題や人権課題が深刻化する中で、企業の責任ある行動が求められるようになり、投資家もその姿勢を重視するようになりました。
また、国際的な枠組みや政府の方針もESG投資の普及を後押ししています。
以下では、具体的な背景要因を3つに分けて解説します。
SDGsへの関心の高まり
2015年に国連が採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」は、企業や投資家にとって重要な指針となっています。
環境保護、貧困の撲滅、ジェンダー平等など、17の目標に向けた取り組みが求められる中、企業のESG対応はSDGs達成への貢献として評価されるようになりました。
投資家は、SDGsに沿った経営を行う企業を選ぶことで、社会的責任を果たしながらリターンを得ることが可能になります。
関連記事:パーパス経営とは?導入ステップ・メリット・注意点をわかりやすく解説
投資家の意識変化
近年、投資家の間で「倫理的な投資」や「インパクト投資」への関心が高まっています。
特にミレニアル世代やZ世代の若い投資家は、企業の社会的責任や環境への配慮を重視する傾向が強く、単なる利益追求ではなく、価値観に合った投資を選ぶ傾向があります。
こうした意識の変化は、資本の流れを変え、企業に対してESG対応を促す強力な圧力となっています。
日本の年金を運用する「GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)」も推進
日本においても、ESG投資は公的機関によって積極的に推進されています。
代表的なのが、世界最大級の年金基金であるGPIFです。
GPIFは2017年からESG指数に連動した運用を開始し、企業のESG情報を評価に組み込む方針を打ち出しました。
この動きは、国内企業に対してESG対応の重要性を強く示すものであり、民間投資家や金融機関にも大きな影響を与えています。
公的資金がESG投資を後押しすることで、社会全体の持続可能性への意識が高まっています。
関連記事:反社会的勢力と関わる16のリスクとは?リスク回避のための反社チェックについても解説
ESG投資の7つの種類
 ESG投資には複数のアプローチがあり、投資家の目的や価値観に応じて手法が選ばれます。
ESG投資には複数のアプローチがあり、投資家の目的や価値観に応じて手法が選ばれます。
ここでは代表的な7つの種類を紹介し、それぞれの特徴と活用のポイントを解説します。
ポジティブスクリーニング
ポジティブスクリーニングは、ESGの取り組みが優れている企業を選定して投資する手法です。
環境負荷の低減、ダイバーシティ推進、ガバナンスの透明性など、評価基準に基づいて上位企業を選びます。
持続可能性を重視する投資家にとって、企業の先進的な取り組みを応援する手段となります。
ネガティブスクリーニング
ネガティブスクリーニングは、倫理的・社会的に問題があるとされる業種や企業を除外する方法です。
たとえば、武器製造、タバコ、ギャンブル、化石燃料などが対象となることが多く、投資家の価値観に合わない企業を排除することで、リスク回避と社会的責任の両立を図ります。
国際規範スクリーニング
国際規範スクリーニングは、国連グローバル・コンパクトやILO(国際労働機関)などの国際的な基準に違反している企業を除外する手法です。
人権侵害、労働搾取、環境破壊などに関与する企業を排除することで、国際社会のルールに沿った投資を実現します。
グローバルな視点での責任投資に適しています。
関連記事:予防法務とは?重要性と具体的な業務内容、注意点を解説
ESGインテグレーション
ESGインテグレーションは、従来の財務分析にESG要素を組み込む手法です。
企業の収益性や成長性に加え、環境リスクや社会的評価、ガバナンス体制を総合的に分析し、投資判断に反映させます。
リスク管理と長期的なリターンの両立を目指す、最も広く使われているアプローチの一つです。
サステナビリティ・テーマでの投資
この手法では、再生可能エネルギー、水資源管理、教育、ヘルスケアなど、持続可能な社会の実現に貢献するテーマに沿った企業やプロジェクトに投資します。
社会課題の解決に直結する分野への資金提供を通じて、投資家自身も社会的インパクトを実感できるのが特徴です。
インパクト投資
インパクト投資は、財務的リターンだけでなく、明確な社会的・環境的成果を生み出すことを目的とした投資です。
発展途上国の教育支援、地域医療の拡充、環境保全プロジェクトなど、成果が定量的に測定されるケースが多く、投資の「意味」を重視する層に支持されています。
エンゲージメント/議決権行使
エンゲージメントとは、投資先企業に対して対話を通じてESG改善を促す活動です。
議決権行使も含め、株主としての影響力を活用し、企業の行動変容を促します。
短期的な売買ではなく、中長期的な関係構築を通じて企業価値の向上を目指す、アクティブな投資スタイルです。
関連記事:コンプライアンスと心理的安全性の関係とは?見るべきサインや向上させる方法を解説
ESG投資を意識した経営を行うメリット
 ESG投資が広がる中、企業にとってもESGを経営に取り入れることは重要な戦略となっています。
ESG投資が広がる中、企業にとってもESGを経営に取り入れることは重要な戦略となっています。
環境・社会・ガバナンスへの配慮は、単なる社会的責任ではなく、企業価値の向上や持続可能な成長につながる要素です。
ここでは、ESGを意識した経営がもたらす3つの主要なメリットを紹介します。
投資家からの評価向上
ESGに積極的な企業は、投資家からの信頼を得やすくなります。
特に機関投資家や年金基金などは、ESG対応を重視する傾向が強く、ESGスコアの高い企業に資金が集まりやすくなっています。
透明性のある情報開示や持続可能な取り組みは、企業のブランド価値を高め、資本市場での競争力を強化します。
関連記事:企業イメージをアップさせるコンプライアンス遵守を解説
経営の長期的な安定
環境リスクや社会的課題への対応は、企業のリスク管理にも直結します。
ESGを経営に組み込むことで、法規制の変化や社会的批判への耐性が高まり、レピュテーションリスクの回避にもつながります。
また、従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下など、組織の健全性を保つ効果も期待できます。
キャッシュフローの増強による企業の成長
ESG対応によって、エネルギー効率の改善や資源の最適活用が進み、コスト削減につながるケースも多くあります。
さらに、社会的評価の高い企業は顧客や取引先からの支持を得やすく、売上の安定化や新規事業の展開にも好影響を与えます。
結果として、キャッシュフローが強化され、持続的な成長基盤が築かれます。
関連記事:人材育成とは?注目される理由や育成の目的、方法をわかりやすく解説
企業のESGに関する取り組み事例
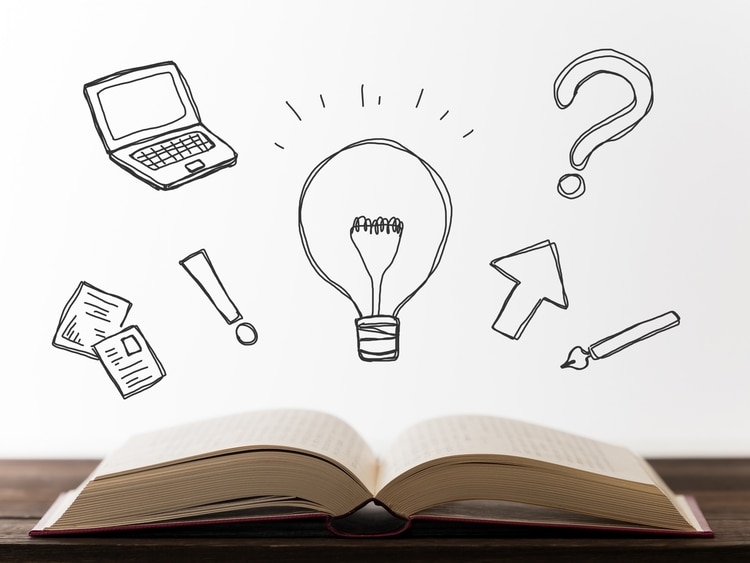 ESG投資の拡大に伴い、企業も環境・社会・ガバナンスへの対応を経営戦略に組み込むようになっています。
ESG投資の拡大に伴い、企業も環境・社会・ガバナンスへの対応を経営戦略に組み込むようになっています。
ここでは、実際に企業が取り組んでいるESG施策の事例を紹介し、持続可能な経営のヒントを探ります。
環境に配慮した自社製品の製造
多くの企業が、製品開発の段階から環境負荷の低減を意識しています。
再生可能素材の活用や、製造工程でのCO₂排出削減、省エネ設計などが代表例です。
たとえば、家電メーカーでは省電力性能を高めたモデルを開発し、消費者の環境意識に応える製品ラインを展開しています。
グループ企業でガバナンスを強化
企業グループ全体でガバナンス体制を見直す動きも進んでいます。
コンプライアンス教育の統一、内部通報制度の整備、取締役会の多様性確保などがその一環です。
グループ間での情報共有やリスク管理を強化することで、透明性と信頼性の高い経営基盤を築いています。
関連記事:企業におけるガバナンスとは?強化する方法やメリットをわかりやすく解説
廃棄物の極小化
製造業を中心に、廃棄物の削減に向けた取り組みが加速しています。
リサイクル率の向上、廃材の再利用、ゼロエミッション工場の設計などが注目されています。
食品業界では、賞味期限管理の徹底やフードロス削減のための流通改善が進められています。
環境に配慮されたオフィス家具・設備の導入
オフィス環境においても、環境負荷を軽減する工夫が見られます。
再生素材を使用した家具や、エネルギー効率の高い照明・空調設備の導入がその一例です。
サステナブル認証を取得した製品を選定することで、企業の環境意識を社内外に示すことができます。
オフィスの省エネ対策を強化
日常業務におけるエネルギー使用量の削減も重要なテーマです。
LED照明への切り替え、空調の自動制御、ペーパーレス化の推進などが効果的です。
従業員の意識改革と合わせて、全社的な省エネ文化の醸成が求められています。
環境に配慮したオフィスへの移転
企業の中には、環境性能の高いビルへの移転を通じてESG対応を強化するケースもあります。
ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)やLEED認証取得施設への移転は、エネルギー効率の向上だけでなく、企業イメージの向上にもつながります。
移転を機に、働き方改革やウェルビーイングの向上も図る企業が増えています。
関連記事:労務コンプライアンスとは?違反事例とチェックポイントを解説
ESG投資に取り組む際の注意点
 ESG投資は企業価値の向上や社会的信頼の獲得につながる一方で、取り組みにあたっては慎重な姿勢と戦略的な視点が求められます。
ESG投資は企業価値の向上や社会的信頼の獲得につながる一方で、取り組みにあたっては慎重な姿勢と戦略的な視点が求められます。
単なる形式的な対応ではなく、実効性と継続性を伴う施策が重要です。
ここでは、ESG投資に取り組む際に押さえておきたい3つの注意点を紹介します。
長期的な視点での取り組みと評価をする
ESG施策は短期的な成果が見えにくく、評価にも時間がかかる傾向があります。
環境対策やガバナンス改善は、数年単位で効果が現れることが多く、投資家やステークホルダーに対しても長期的な視点での説明が必要です。
一過性の対応ではなく、継続的な改善と情報開示を通じて信頼を築くことが求められます。
ESGへの取り組みのアピールも重要
優れたESG施策を実施していても、社外に十分に伝わっていなければ評価につながりません。
サステナビリティレポートの発行、第三者認証の取得、IR資料での明示など、積極的な情報発信が不可欠です。
投資家や顧客に対して、企業の姿勢や成果をわかりやすく伝えることで、ブランド価値や資本調達力の向上にもつながります。
統一的な評価基準はない
ESGの評価は、機関や指標によって基準が異なり、必ずしも一貫性があるとは限りません。
同じ企業でも、評価機関によってスコアが大きく異なることがあります。
そのため、自社にとって適切な評価軸を見極め、複数の指標を参考にしながら戦略的に対応することが重要です。
外部評価に依存しすぎず、自社の価値観と整合性のあるESG方針を持つことが、持続的な成長につながります。
関連記事:風評被害によるレピュテーションリスクとは?もたらす影響と対策を解説
まとめ
ESG投資は、企業の持続可能性と社会的責任を評価する新たな投資基準として、世界的に注目を集めています。
企業にとっては、単なる投資対象としての魅力を高めるだけでなく、経営の質を向上させる絶好の機会でもあります。
長期的な視点でESGに取り組み、社会とともに成長する企業こそが、次世代のスタンダードとなるでしょう。
関連記事:福利厚生とは?種類や導入するメリット・デメリットをわかりやすく解説
関連記事:採用管理システム(ATS)とは?基本機能や導入するメリット、選定のポイントを解説