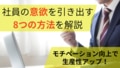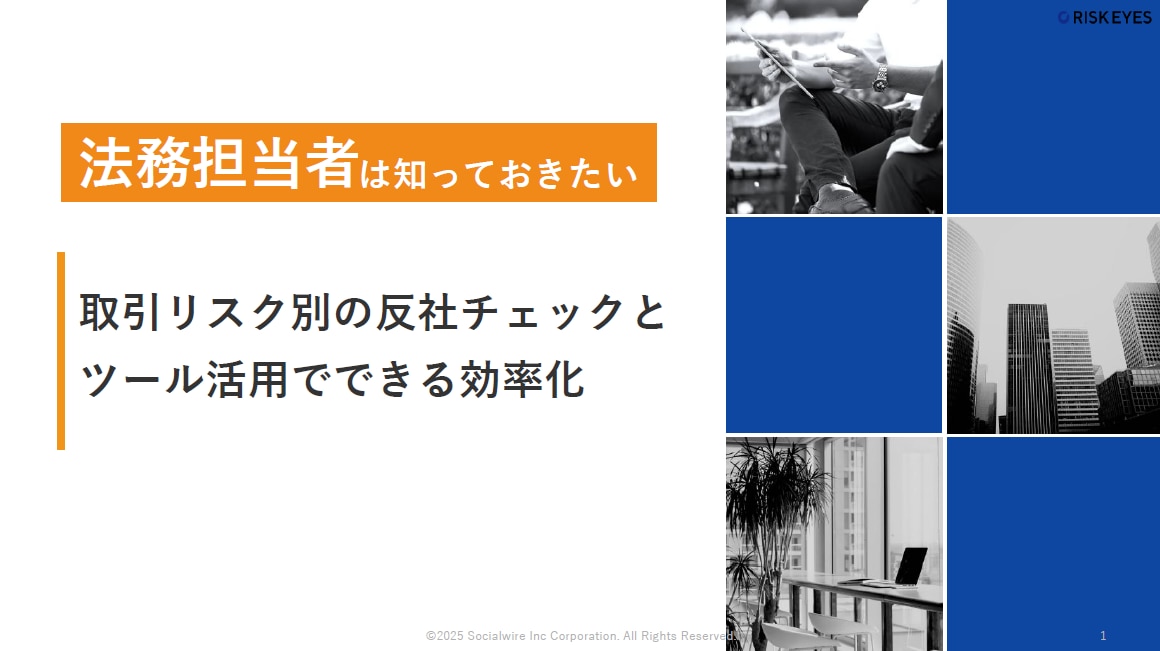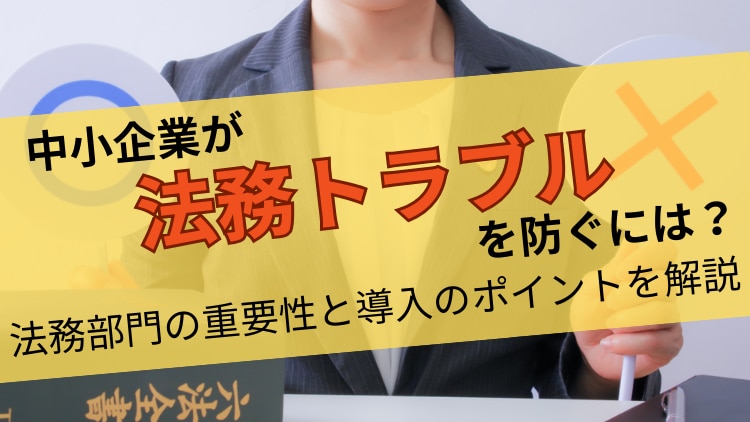
中小企業が法務トラブルを防ぐには?法務部門の重要性と導入のポイントを解説
法務トラブルは企業規模に関係なく発生するリスクがあり、特に中小企業にとっては一度の訴訟や契約トラブルが経営に致命的な打撃を与えかねません。
近年では、法改正や社会的コンプライアンス意識の高まりにより、法務の重要性がますます増しています。
この記事では、中小企業が法務リスクを最小限に抑えるための法務部門の役割と導入時のポイントについて解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【実務担当者】取引リスク別反社チェック効率化の方法
目次[非表示]
- 1.中小企業における法務部門の役割
- 2.中小企業の法務の現状
- 2.1.法務の重要性が増している背景
- 3.中小企業が法務部門を設置しないことによる主なリスク
- 3.1.担当業務に割ける時間が減る
- 3.2.法的トラブルが増え、対応も遅延する
- 3.3.法律に違反するリスク
- 3.4.知的財産権の侵害問題が発生する
- 3.5.「攻めの法務」による企業価値を向上させる機会を損失する
- 4.中小企業で発生しやすい法務問題
- 4.1.契約トラブル
- 4.2.債権回収・保全
- 4.3.労務問題
- 4.4.コンプライアンス問題
- 4.5.事業主の相続
- 5.中小企業で法務部門を設置する場合のポイント
- 5.1.必ず弁護士と連携する
- 5.2.弁護士を早めに探す
- 5.3.コストをかけても社内研修を実施する
- 5.4.社外研修を活用する
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの効率化を学ぶ】
中小企業における法務部門の役割

中小企業にとって法務部門の設置は、経営の安定や成長を支える重要な取り組みです。
契約トラブルや労務問題、コンプライアンス違反など、日々の業務に潜む法的リスクに対して、法務部門は「予防」「戦略」「臨床」という3つの視点から対応する役割を担います。
予防法務
予防法務は、法的トラブルを未然に防ぐための機能です。
契約書の内容チェック、社内規程の整備、社員へのコンプライアンス研修などを通じて、リスクの芽を早期に摘み取ります。
とくに契約書まわりの確認は、取引先との信頼構築にもつながるため、外部に任せきりにせず、社内でも基本体制を構築しておくことが重要です。
関連記事:予防法務とは?重要性と具体的な業務内容、注意点を解説
戦略法務
戦略法務は、企業の成長を加速させる「攻めの法務」とも言えます。
新規事業の立ち上げ、業務提携、IPO準備など、経営戦略の節目において、法的な観点からの助言や支援を行います。
事業リスクをコントロールしながらスピード感ある意思決定を支える存在として、経営層との連携が不可欠です。
臨床法務
臨床法務は、トラブルが発生した際に迅速かつ的確な対応を行う役割を担います。
訴訟や行政対応、クレーム処理など、企業の信用と損害の最小化を図るための専門的な支援が求められます。
顧問弁護士との連携や、社内法務担当の実務経験が鍵を握る分野です。
関連記事:企業法務の役割と重要性とは?主な仕事や関連する法律について解説
中小企業の法務の現状

現在、日本において法務部門を設置している中小企業は1割程度にとどまっています。
多くの企業では、法務業務を総務や経営者が兼任しているのが実情です。
背景には、専門人材の確保が困難であることや、法務の必要性が日常業務の中で見えにくいことが挙げられます。
しかし、契約トラブルや労働問題、コンプライアンス違反は企業規模を問わず発生するリスクがあり、体制整備を後回しにすることが重大な損失に繋がる可能性があります。
法務の重要性が増している背景
近年、法務の重要性は急速に高まっています。
個人情報保護法や電子契約に関する法改正、働き方改革による労務管理の厳格化など、企業が対応すべき法律の範囲は拡大しています。
加えて、SNSや口コミによる情報拡散の影響により、企業活動が世間の目にさらされる機会も増えています。
そのため、炎上や風評被害といった法的リスクへの対応力が問われる時代となっています。
今後は、中小企業であっても法務部門の設置や社外専門家との連携が、経営の安定化と信用維持に不可欠な要素となっていくでしょう。
関連記事:IPO準備&急成長ベンチャーに必要な「契約管理」 法務体制強化でリスク管理
中小企業が法務部門を設置しないことによる主なリスク

中小企業が法務部門を持たない場合、日常業務の中で見えにくい法的リスクが顕在化しやすくなります。
特に経営層や総務担当者が法務対応を兼任している場合、専門性や対応スピードに限界があり、結果として企業活動に深刻な影響を与える可能性があります。
担当業務に割ける時間が減る
法務の知識がない状態で契約審査やトラブル対応に時間を取られると、本来担うべき業務に支障が出ます。
とくに営業や財務などの主要業務との兼任では、判断の遅れやミスが発生しやすく、生産性の低下につながります。
法的トラブルが増え、対応も遅延する
契約書の不備、労務上の対応遅れ、クレーム処理の不適切さなどにより、法的トラブルが顕在化するケースは少なくありません。
対応が後手に回ることで、損害額の拡大や企業信用の毀損に直結する恐れがあります。
関連記事:コンプライアンスと法務の違いは?業務内容や部門を分けるメリット・デメリットを解説
法律に違反するリスク
法改正の把握が遅れると、知らず知らずのうちに法律違反をしてしまう可能性があります。
たとえば、労働時間の管理や個人情報保護、景品表示法などの分野では、規制の強化と運用の厳格化が進んでおり、無自覚な違反が行政指導の対象となる場合もあります。
知的財産権の侵害問題が発生する
ロゴやサービス名など、マーケティングや製品開発に関連する知的財産への理解が浅い場合、意図せず他社の権利を侵害してしまうリスクがあります。
また、自社の商標や著作物を守るための手続きが不十分なまま、模倣や盗用に対抗できずに権利を失うケースもあります。
「攻めの法務」による企業価値を向上させる機会を損失する
法務部門は守りの役割だけでなく、成長戦略にも貢献します。
例えば、事業提携の契約設計、新規事業の法的スキームづくり、IPO準備などにおいて、法的な支援があればリスクを抑えつつスピーディに実行することが可能です。
法務機能がないと、これらの機会を逃し、競争優位性の構築が遅れる原因となります。
関連記事:知財戦略(知的財産戦略)とは?得られる効果と進め方、注意点についてわかりやすく解説
中小企業で発生しやすい法務問題

中小企業における法務の整備はまだ十分ではなく、多くの場合、実務担当者が法的判断を兼任しているのが実態です。
しかし、日常業務の中で発生する法務リスクは複雑化・増加しており、適切な対応が遅れれば、経営上の深刻な損害につながる可能性があります。
以下では、特に中小企業で頻発しやすい法務問題について解説します。
契約トラブル
契約書の内容が曖昧である場合や、書面の作成を怠り口頭で済ませてしまうことで、後々契約内容を巡る認識の違いや責任の所在に関する争いが生じるケースがあります。
納期や支払条件、解除条項などを明確にしないまま取引を開始すると、トラブルになった際の対応が困難になります。
債権回収・保全
売掛金の未回収や取引先の倒産などにより、金銭的損失が生じるリスクがあります。
担保の設定、保証契約の締結、回収不能時の法的対応など、予防・事後対応の両面から備えておく必要があります。
とくに中小企業では、一件の回収不能が資金繰りに深刻な影響を与える可能性が高いです。
関連記事:与信管理に必要なマニュアルとは?作成方法と活用法も解説
労務問題
従業員とのトラブルは多岐にわたります。
雇用契約書の不備、残業代の未払い、解雇手続きの不適切、ハラスメント対応の遅れなど、労働関連法規に対する理解不足が問題を複雑化させます。
労務問題は企業の評判にも直結するため、就業規則や労働条件通知書の整備は不可欠です。
コンプライアンス問題
内部不正、利益相反、役員の不適切な発言、SNSによる炎上など、企業倫理を問われる問題が多発しています。
法令遵守のみならず、倫理規範や内部通報制度の整備を通じて、問題発生時のダメージコントロールと組織の健全性維持が求められます。
事業主の相続
オーナー経営型の中小企業においては、事業主が急逝した場合の株式・資産の承継や経営権の移譲が大きな課題となります。
事前に遺言や株式譲渡契約を整備していなければ、相続争いに発展し、事業継続が困難になるケースもあります。
法務・税務の両側面からの計画的な準備が重要です。
関連記事:コンプライアンス違反を起こす人と組織 事例と対策を紹介
中小企業で法務部門を設置する場合のポイント

法務部門の設置は、中小企業にとって経営上のリスクを管理し、企業価値を高める重要な施策です。
企業規模が小さくても、契約トラブルや労務問題、知的財産の管理など、法務に関する課題は多岐にわたり、放置すれば経営に深刻な影響を与える可能性があります。
限られた人員や予算の中でも、機能的な法務体制を構築するには、以下のポイントを意識した準備が不可欠です。
必ず弁護士と連携する
たとえ社内に法務担当者を配置した場合でも、すべての法的課題に対応するには限界があります。
契約の審査、取引先とのトラブル解決、法改正への対応など、専門性が求められる場面では、顧問弁護士との連携が不可欠です。
会社の状況を弁護士に定期的に共有し、迅速かつ的確な助言を受けられる体制を整えることで、社内業務のスムーズな遂行につながります。
弁護士を早めに探す
トラブルが起きてから弁護士を探すのでは、初動が遅れ対応にも支障が出ます。
業界に詳しく、相談しやすい弁護士を早めに見つけておきましょう。
商工会議所や同業他社からの紹介、企業法務に強い法律事務所のセミナー参加などを通じて、候補となる専門家と接点を持つことが有効です。
関連記事:【法務担当者必見】2025年の主な法改正を一覧で解説
コストをかけても社内研修を実施する
法務部門の設置だけではなく、全社員の法務意識とリテラシーを向上させる取り組みも必要です。
契約書の取り扱い、個人情報の管理、ハラスメント対応など、日常業務の中で法務と接点を持つ場面は数多くあります。
社内研修を定期的に実施し、事例を交えて現場感のある学習機会を設けることで、組織全体のリスク管理力を高めることができます。
社外研修を活用する
中小企業では社内だけで十分な法務教育を行うことが難しいケースもあります。
そのような場合は、自治体や業界団体、商工会議所などが開催するセミナーや研修を積極的に活用しましょう。
法改正の最新情報や実務に役立つ具体的事例を学ぶことで、実践的な判断力が養われ、社内対応力の向上につながります。
社員のスキルアップだけでなく、社外の専門家や同業他社と交流する機会にもなるため、今後の連携強化にも役立ちます。
関連記事:質を向上させるコンプライアンス研修の資料作成方法を解説
まとめ
法務部門の設置は、中小企業にとって経営の安定と成長の両面に貢献する重要な取り組みです。
予防・戦略・臨床の各領域を体系的にカバーすることで、法的リスクを減らしながら企業価値を高めることが可能となります。
とくに近年の法改正やコンプライアンス意識の高まりにより、法務体制の整備が企業経営に直結する時代となってきました。
社内外の体制を整え、実務に根ざした法務機能を着実に構築していくことが、持続可能な組織運営の鍵となります。
関連記事:企業の義務である障害者雇用 2024年改正「障害者雇用促進法」について詳しく解説
関連記事:契約書レビューとは?具体的な流れや確認すべきポイントをわかりやすく解説