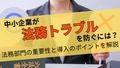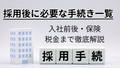オフィスセキュリティの基本と実践!重要性・リスク・対策を徹底解説
企業活動の中心となるオフィスは、情報・人材・資産が集まる重要な空間です。
近年では、サイバー攻撃だけでなく、物理的な侵入や内部不正など、セキュリティリスクが多様化しています。
この記事では、オフィスセキュリティの基本から具体的な対策までを網羅的に解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
👉コンプライアンスとは?わかりやすく・簡単に意味や使い方を解説
👉企業におけるガバナンスとは?強化する方法やメリットをわかりやすく解説
▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら
目次[非表示]
- 1.オフィスセキュリティとは
- 2.オフィスセキュリティが重要な3つの理由
- 2.1.情報漏洩を防ぐため
- 2.2.従業員や資源を守るため
- 2.3.社会的責任を果たすため
- 3.オフィスセキュリティ対策不足がもたらす4つのリスク
- 3.1.人的リスク
- 3.2.物的リスク
- 3.3.情報リスク
- 3.4.処罰の対象になるリスク
- 4.オフィスセキュリティで重要な「ゾーニング」によるレベル分け
- 4.1.レベル1:公共性の高い場所
- 4.2.レベル2:共用スペース
- 4.3.レベル3:業務スペース
- 4.4.レベル4:役員ゾーン
- 4.5.レベル5:最高位のセキュリティが必要とされる場所
- 5.オフィスセキュリティ対策の具体例
- 5.1.防犯カメラ
- 5.2.入退室管理システム
- 5.3.テンキー方式
- 5.4.ICカード認証
- 5.5.スマホ認証
- 5.6.指紋や顔での認証
- 5.7.金庫などの収納セキュリティ
- 5.8.シュレッダー
- 5.9.パーティションや仕切り
- 5.10.サウンドマスキング
- 5.11.セキュリティ仕様のクリアホルダー
- 6.まとめ
オフィスセキュリティとは

オフィスセキュリティとは、企業のオフィス空間における情報・人・物の安全を確保するための取り組みです。
ITセキュリティと物理的セキュリティの両面から、リスクを未然に防ぎ、企業活動の継続性を守ることが目的です。
具体的には、入退室管理、防犯カメラ、情報保管のルール整備、従業員教育などが含まれます。
セキュリティ対策は、企業の規模や業種に関わらず、信頼性と社会的責任を果たすために欠かせない要素です。
関連記事:レピュテーションリスクを回避するための「レピュテーションマネジメント」とは?実施方法とメリットも解説
オフィスセキュリティが重要な3つの理由

企業活動の中心であるオフィスには、機密情報・人材・資産が集約されています。
これらを守るために、オフィスセキュリティは欠かせない要素です。
ここでは、オフィスセキュリティが重要とされる3つの理由を解説します。
情報漏洩を防ぐため
企業が保有する顧客情報、契約書、設計図、財務データなどは、外部に漏れることで甚大な損害をもたらします。
情報漏洩は、企業の信用を失墜させるだけでなく、取引停止や損害賠償、法的責任にも発展する可能性があります。
特に、紙媒体の書類やUSBメモリなど、物理的な情報の管理は見落とされがちです。
オフィスセキュリティを強化することで、こうした情報資産の漏洩リスクを未然に防ぐことができます。
関連記事:情報漏洩を防ぐコンプライアンス対策 関連法律と罰則についても解説
従業員や資源を守るため
オフィスは従業員が日々働く場所であり、安全な環境が確保されていなければ、業務効率やモチベーションにも悪影響を及ぼします。
不審者の侵入や内部不正によるトラブルは、従業員の安全を脅かすだけでなく、企業資産の盗難・破損にもつながります。
防犯カメラや入退室管理システムなどの物理的セキュリティ対策は、従業員の安心感を高め、健全な職場環境の維持に貢献します。
社会的責任を果たすため
企業は、顧客や取引先から預かった情報を適切に管理する責任があります。
セキュリティ対策を怠ることは、社会的信用の喪失につながり、企業ブランドにも深刻なダメージを与えます。
また、個人情報保護法やマイナンバー法など、法令遵守の観点からも、セキュリティ体制の整備は不可欠です。
オフィスセキュリティは、企業が社会的責任を果たすための基盤であり、持続可能な経営の柱となります。
関連記事:企業イメージをアップさせるコンプライアンス遵守を解説
オフィスセキュリティ対策不足がもたらす4つのリスク

企業活動の拠点であるオフィスには、従業員・情報・設備など多くの重要資産が集約されています。
しかし、セキュリティ対策が不十分な場合、さまざまなリスクが顕在化し、企業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、オフィスセキュリティ対策不足がもたらす4つの主要なリスクについて解説します。
人的リスク
セキュリティが甘いオフィスでは、不審者の侵入や内部不正によるトラブルが発生しやすくなります。
例えば、来訪者の管理が曖昧な場合、外部の人物が自由に社内を出入りできてしまい、従業員の安全が脅かされることもあります。
また、従業員同士のトラブルやハラスメントが発生した際に、監視体制が整っていないと、適切な対応が遅れ、職場環境の悪化につながります。
人的リスクは、企業の信頼性や従業員の定着率にも影響を与えるため、早急な対策が求められます。
関連記事:コンプライアンス違反を起こす人と組織 事例と対策を紹介
物的リスク
オフィスには、パソコンやサーバー、書類、什器など多くの物的資産が存在します。
セキュリティ対策が不十分な場合、盗難や破損、火災などの物的リスクが高まります。
特に、夜間や休日の無人時間帯における防犯体制が弱いと、外部からの侵入による被害が発生しやすくなります。
資産の損失は、直接的な金銭的ダメージだけでなく、業務の停滞や復旧コストの増加にもつながります。
情報リスク
情報漏洩は、企業にとって最も深刻なリスクの一つです。
顧客情報、契約書、設計図、財務データなどが外部に流出した場合、企業の信用は著しく損なわれ、取引停止や損害賠償、法的責任を問われる可能性があります。
特に、紙媒体の書類やUSBメモリなど、物理的な情報管理が甘いと、意図せぬ漏洩が発生しやすくなります。
情報リスクを防ぐためには、アクセス制限や監視体制の強化が不可欠です。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
処罰の対象になるリスク
セキュリティ対策の不備は、法令違反として処罰の対象になることがあります。
たとえば、個人情報保護法やマイナンバー法に違反した場合、行政指導や罰則が科される可能性があります。
また、情報漏洩が発生した際には、企業名が公表され、社会的信用の失墜につながることもあります。
法令遵守は、企業の社会的責任の一環であり、セキュリティ対策の怠慢は経営リスクそのものです。
関連記事:コンプライアンスとは何を守ることなのか?企業に必要な取り組みも解説
オフィスセキュリティで重要な「ゾーニング」によるレベル分け

オフィスセキュリティを効率的かつ効果的に運用するためには、「ゾーニング」による空間のレベル分けが不可欠です。
ゾーニングとは、オフィス内の各エリアをセキュリティレベルに応じて分類し、それぞれに適切な管理体制を敷く手法です。
これにより、情報漏洩や不正アクセスのリスクを最小限に抑えつつ、業務効率を損なわないバランスの取れたセキュリティ運用が可能になります。
以下では、一般的なゾーニングの5つのレベルについて解説します。
レベル1:公共性の高い場所
このゾーンは、来訪者や外部関係者が自由に出入りできるエリアです。
具体的には、ビルのエントランス、受付前のロビー、カフェスペースなどが該当します。
ここでは、監視カメラや警備員の配置など最低限の監視体制を整えることで、不審者の早期発見やトラブルの抑止が可能です。
また、企業イメージを左右する場所でもあるため、清潔感や案内表示の整備も重要です。
レベル2:共用スペース
レベル2は、社内外の人が一定の制限のもとで利用するエリアです。
会議室、応接室、休憩室、トイレなどが含まれます。
このゾーンでは、入退室管理や予約システムの導入により、利用者の把握と不正利用の防止が求められます。
特に、会議室では機密情報が扱われることもあるため、録音・録画の制限や遮音性の確保など、物理的な対策も検討すべきです。
関連記事:コンプライアンスとガバナンスとは?意味の違いと企業が行うべき取り組みを解説
レベル3:業務スペース
従業員が日常的に業務を行うエリアがこのゾーンです。
執務室、部署ごとのエリア、共有PCスペースなどが該当します。
ここでは、社員以外の立ち入りを制限し、IDカードによる入退室管理や監視カメラの設置が基本となります。
また、情報端末の利用ルールや画面の覗き見防止フィルターなど、情報セキュリティとの連携も重要です。
業務効率を保ちながら、適切なセキュリティレベルを維持することが求められます。
レベル4:役員ゾーン
役員室、経営会議室、秘書室など、企業の意思決定に関わる重要なエリアがこのゾーンです。
ここでは、限られた社員のみがアクセス可能であり、セキュリティレベルはさらに高く設定されます。
顔認証や静脈認証などの生体認証技術の導入、専用ネットワークの構築、外部通信の制限などが検討されるべきです。
情報の機密性が高いため、物理的・技術的な両面からの対策が不可欠です。
レベル5:最高位のセキュリティが必要とされる場所
このゾーンは、企業の中でも最も厳重な管理が求められるエリアです。
サーバールーム、金庫室、機密文書保管庫などが該当します。
ここでは、二重認証や24時間監視、入退室履歴の記録、アクセス権限の厳格な管理が必須です。
災害時のバックアップ体制や、外部からのサイバー攻撃への防御策も含め、総合的なセキュリティ設計が求められます。
関連記事:コンプライアンス違反の事例を紹介 ハラスメントとの関係も解説
オフィスセキュリティ対策の具体例

企業の情報資産や人的資源を守るためには、オフィスにおけるセキュリティ対策が欠かせません。
セキュリティと一口に言っても、物理的な防犯から情報漏洩防止、プライバシー保護まで多岐にわたります。
ここでは、オフィスで導入可能な具体的なセキュリティ対策を11項目に分けて紹介します。
防犯カメラ
最も基本的なセキュリティ対策の一つが防犯カメラの設置です。
エントランスや通路、共用スペースなどに設置することで、不審者の侵入や内部不正の抑止効果が期待できます。
録画データはトラブル発生時の証拠としても活用でき、従業員の安心感にもつながります。
最近ではAIによる顔認識や異常検知機能を備えた高性能カメラも登場しています。
入退室管理システム
誰がいつどこに入退室したかを記録・管理するシステムは、セキュリティの中核を担います。
社員ごとにアクセス権限を設定することで、機密エリアへの不正侵入を防止できます。
ログデータは監査やトラブル対応にも活用でき、セキュリティレベルの向上に貢献します。
関連記事:企業に欠かせないコンプライアンスオフィサーとは?主な業務・必要なスキルについて解説
テンキー方式
テンキーによる暗証番号入力は、比較的導入しやすい入退室管理手法です。
特定の番号を知っている人だけが入室できるため、簡易的なセキュリティゾーンの構築に適しています。
ただし、番号の漏洩や使い回しによるリスクもあるため、定期的な番号変更や併用対策が望まれます。
ICカード認証
社員証などにICチップを搭載し、カードをかざすことで認証する方式です。
個人ごとのアクセス制限が可能で、紛失時には即座に無効化できる点がメリットです。
複数の扉やエリアに対応できるため、ゾーニングとの相性も良く、企業規模を問わず導入されています。
スマホ認証
スマートフォンを使った認証は、利便性とセキュリティを両立できる最新の手法です。
専用アプリやBluetooth、QRコードなどを活用し、物理的な鍵やカードを不要にします。
遠隔操作や一時的なアクセス権付与も可能で、柔軟な運用が魅力です。
関連記事:企業が取り組むべきハラスメント対策 その重要性とメリットを解説
指紋や顔での認証
生体認証は、本人確認の精度が高く、なりすましや盗難リスクを大幅に低減できます。
指紋認証や顔認証は、役員室やサーバールームなど、高セキュリティが求められるエリアに適しています。
導入コストはやや高めですが、セキュリティ強化には非常に有効です。
金庫などの収納セキュリティ
現金や重要書類、契約書などを保管するには、耐火・耐盗性能を備えた金庫の設置が不可欠です。
鍵式・テンキー式・指紋認証式など、用途に応じたタイプを選ぶことで、物理的な情報漏洩リスクを防止できます。
設置場所や固定方法にも配慮が必要です。
シュレッダー
不要になった書類をそのまま廃棄するのは非常に危険です。
顧客情報や社内資料が外部に漏れるリスクを防ぐために、シュレッダーによる破棄処理は必須です。
クロスカットやマイクロカットなど、細断レベルに応じた機種選定も重要です。
関連記事:企業のリスクマネジメントとは?リスクの種類や基本プロセス・手法をわかりやすく解説
パーティションや仕切り
オフィス内の視線や動線をコントロールすることで、情報の覗き見や盗み見を防止できます。
特に、来客対応エリアと業務エリアを明確に分けることで、無意識の情報漏洩を防ぐ効果があります。
防音性や遮光性を備えたパーティションを選ぶことで、プライバシー保護にもつながります。
サウンドマスキング
会話内容が周囲に漏れることを防ぐために、サウンドマスキング技術を活用する企業も増えています。
ホワイトノイズや環境音を流すことで、音の拡散を抑え、機密性の高い会話を保護します。
特に、会議室や役員室などでの導入が効果的です。
セキュリティ仕様のクリアホルダー
一見地味ですが、情報漏洩防止に役立つのがセキュリティ仕様のクリアホルダーです。
中身が見えにくい加工が施されており、持ち運び時の覗き見を防止できます。
社外への持ち出し資料や会議資料などに活用することで、細かなセキュリティ対策が可能になります。
関連記事:バックオフィス業務とは?具体的な業務内容と課題、効率化する方法を解説
まとめ
オフィスセキュリティは、企業の信頼性・継続性・社会的責任を守るために欠かせない要素です。
ゾーニングによるレベル分けと、具体的な対策の導入によって、リスクを最小限に抑えることが可能です。
今一度、自社のセキュリティ体制を見直し、必要な対策を講じることが、持続可能な企業経営への第一歩となります。
関連記事:IPO準備企業における内部統制への対応方法とは 体制構築のステップも解説
関連記事:企業活動におけるコンプライアンスとは?違反を防ぐ対策についても解説