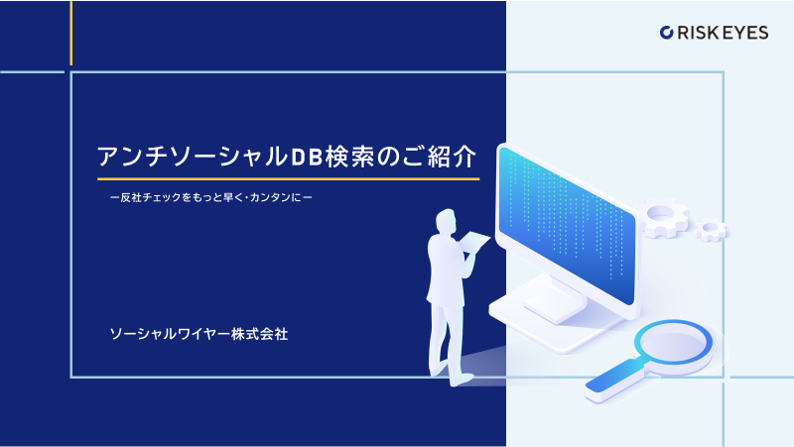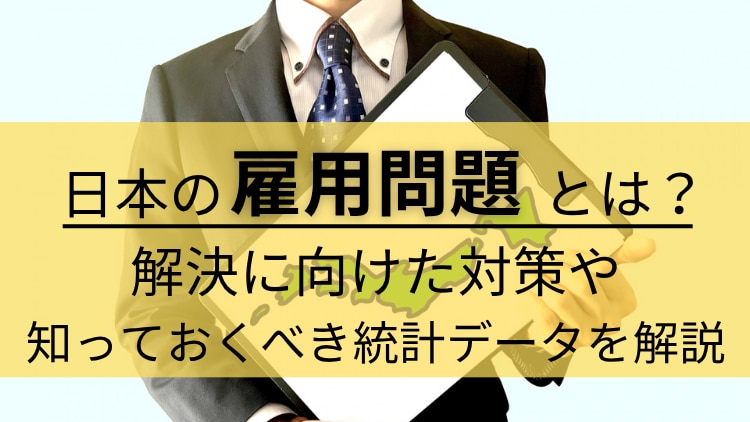
日本の雇用問題とは?解決に向けた対策や知っておくべき統計データを解説
日本の雇用を取り巻く環境は今、大きな転換期にあります。
人口構造の変化に加え、働き方改革やグローバル化の進展によって、従来の雇用制度やマネジメント手法が通用しにくくなりつつあります。
こうした背景を踏まえ、この記事では、メンバーシップ型雇用や終身雇用といった日本特有の雇用慣行を整理したうえで、人材不足や賃金格差などの課題とその解決策を、最新の統計データとともに解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
注意すべき相手をすぐに発見できる反社リストを検索
目次[非表示]
- 1.そもそも日本の雇用の特徴とは?
- 1.1.メンバーシップ型雇用契約
- 1.2.終身雇用制
- 1.3.年功序列
- 1.4.企業別労働組合
- 2.日本の雇用問題
- 2.1.人材不足
- 2.2.不本意非正規雇用
- 2.3.賃金格差の拡大
- 2.4.外国人労働者の受け入れ
- 2.5.雇用形態の多様化による管理の煩雑化
- 3.雇用問題の解決につながる対策
- 3.1.法令順守・適切な法改正対応
- 3.2.多様性の理解と柔軟な対応
- 3.3.非正規社員の待遇改善
- 3.4.多様な人材の雇用
- 3.5.外部リソースの活用
- 3.6.業務自動化ツールの導入
- 4.雇用に関する統計データ
- 4.1.労働力人口
- 4.2.就業者数
- 4.3.雇用者数
- 4.4.正規雇用・非正規雇用者数
- 4.5.不本意非正規雇用者数
- 4.6.産業別就業者
- 4.7.女性の労働力率
- 5.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【独自で収集した反社リストについてもっと知る】
そもそも日本の雇用の特徴とは?

日本の雇用慣行は、戦後の高度経済成長期に確立された独自の制度に支えられてきました。
欧米の「ジョブ型雇用」とは異なり、日本では「メンバーシップ型雇用」が主流であり、終身雇用や年功序列といった制度と密接に結びついています。
以下では、その主要な特徴を解説します。
メンバーシップ型雇用契約
日本企業では、特定の職務に人を割り当てるのではなく、まず人を採用し、その後に業務を割り振る「メンバーシップ型雇用」が一般的です。
職務内容や勤務地、労働時間が柔軟に設定されるため、企業内での異動や配置転換が頻繁に行われます。
この仕組みにより、企業は長期的な人材育成を前提とした経営が可能になります。
終身雇用制
終身雇用とは、定年までの長期雇用を前提とした慣行です。
法的な制度ではないものの、企業と従業員の間に「長く勤めることが前提」という暗黙の了解が存在します。
これにより、従業員は安定した雇用を得られ、企業側も忠誠心の高い人材を確保できます。
ただし、経済の変化により、近年ではこの制度の持続可能性が問われています。
関連記事:戦略人事とは?メリットや必要な機能、成功させるためのポイントを解説
年功序列
年功序列は、勤続年数や年齢に応じて昇進や昇給が決まる制度です。
若手社員にとっては将来的な見通しが立てやすく、企業への定着率向上に寄与します。
一方で、成果主義との乖離や、優秀な若手のモチベーション低下といった課題も指摘されています。
企業別労働組合
日本では、企業単位で労働組合が組織される「企業別組合」が主流です。
欧米のような産業別・職能別組合とは異なり、企業内の従業員が一体となって労使交渉を行うため、比較的協調的な関係が築かれやすいという特徴があります。
ただし、産業全体の課題に対する交渉力には限界があります。
関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説
日本の雇用問題

日本の雇用環境は、少子高齢化やグローバル化、働き方の多様化といった社会構造の変化により、一層複雑化しています。
ここでは、特に注目すべき5つの課題を取り上げ、それぞれの背景と影響を解説します。
人材不足
日本では労働力人口の減少が深刻化しており、特に、医療・福祉、建設業、運輸業、宿泊・飲食サービス業での人手不足が顕著です。
厚生労働省のデータによると、2023年の有効求人倍率は1.31倍と高水準を維持しており、企業は人材確保に苦慮しています。
高齢者や女性の労働参加が進んでいるものの、供給と需要のギャップは依然として大きいのが現状です。
2035年には現在の1.85倍の労働力不足が予想されており、抜本的な対策が急務となっています。
不本意非正規雇用
非正規雇用者の中で、正社員として働きたいにも関わらず非正規雇用で働いている「不本意非正規雇用者」の問題が深刻化しています。
2024年の統計では、非正規雇用労働者全体の8.7%が不本意非正規雇用者となっています。
この層の待遇改善と正規転換支援は、労働市場の健全化に不可欠です。
関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説
賃金格差の拡大
正規・非正規間、男女間、地域間での賃金格差が拡大しています。
非正規労働者の平均賃金は正規の6割程度にとどまり、生活の安定や将来設計に影響を及ぼしています。
また、同一労働同一賃金の原則が浸透しきっていない現状も、格差是正の妨げとなっています。
外国人労働者の受け入れ
人手不足を補うため、外国人労働者の受け入れが進んでいます。
技能実習制度や特定技能制度の拡充により、外国人雇用は増加傾向にありますが、言語や文化の壁、労働条件の不備といった課題も浮上しています。
多文化共生の視点と制度整備が求められます。
雇用形態の多様化による管理の煩雑化
副業・フリーランス・テレワークなど、働き方の選択肢が広がる一方で、企業側は労務管理や評価制度の見直しを迫られています。
従来の一律的な制度では対応が難しく、柔軟かつ個別最適な人材マネジメント体制の構築が急務です。
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説
雇用問題の解決につながる対策

日本の雇用環境は、少子高齢化や働き方の多様化により複雑化しています。
企業が持続的に成長するためには、これらの課題に対して戦略的かつ柔軟に対応することが不可欠です。
以下では、雇用問題の解決に向けた6つの具体的な対策を紹介します。
法令順守・適切な法改正対応
まず基本となるのが、労働関連法令の順守と法改正への迅速な対応です。
たとえば、2020年に施行された「同一労働同一賃金」や、2024年の労働基準法改正(勤務間インターバル制度の努力義務化)など、企業は制度の変化を正確に把握し、社内規程や運用体制を見直す必要があります。
法令順守はコンプライアンスの観点だけでなく、従業員からの信頼獲得にも直結します。
関連記事:法改正対応のポイントは?具体的な流れや情報収集方法を解説
多様性の理解と柔軟な対応
ダイバーシティ&インクルージョンの推進は、企業の競争力を高める鍵となります。
性別・年齢・国籍・障害の有無などに関係なく、多様な人材が活躍できる環境づくりが求められています。
たとえば、育児や介護と仕事を両立できる柔軟な勤務制度(時短勤務、リモートワークなど)の導入は、離職防止や働きがいの向上にも効果的です。
非正規社員の待遇改善
2024年時点で非正規雇用者は全体の約36%を占めており、その中には不本意非正規も約160万人存在します。
こうした背景を踏まえ、非正規社員の賃金・福利厚生・キャリア支援の充実が急務です。
正規転換制度の整備や、スキルアップ研修の提供により、モチベーション向上と定着率の改善が期待されます。
関連記事:雇用契約と業務委託契約の違いと見分け方を徹底解説!業務委託のメリットも解説
多様な人材の雇用
労働力人口が減少する中で、高齢者・女性・外国人・障害者など多様な人材の活用が不可欠です。
特に65歳以上の就業率は上昇傾向にあり、定年後の再雇用制度やシニア向けの職務設計が注目されています。
また、外国人労働者の受け入れに際しては、言語支援や生活支援体制の整備も重要です。
外部リソースの活用
人材不足や専門性の確保に対応するためには、外部リソースの戦略的活用も有効です。
人材紹介会社や業務委託、クラウドソーシングなどを活用することで、必要なスキルを持つ人材を柔軟に確保できます。
特に中小企業にとっては、コストを抑えつつ即戦力を得られる手段として注目されています。
業務自動化ツールの導入
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIなどの業務自動化ツールの導入は、定型業務の効率化と人手不足の緩和に大きく貢献します。
たとえば、勤怠管理や経費精算、採用管理などのバックオフィス業務を自動化することで、従業員がより付加価値の高い業務に集中できます。
2024年には中堅企業でも導入が進み、業務効率化とコスト削減の両立が実現しつつあります。
関連記事:バックオフィス業務とは?具体的な業務内容と課題、効率化する方法を解説
雇用に関する統計データ

日本の雇用環境を正確に把握するには、信頼性の高い統計データの分析が欠かせません。
ここでは、総務省統計局が公表した2025年5月時点の労働力調査をもとに、主要な雇用指標を解説します。
労働力人口
2025年5月の労働力人口は約7,021万人で、前年同月比で62万人の増加となりました。
これは34か月連続の増加であり、女性や高齢者の労働参加が進んでいることを示しています。
労働力人口とは、15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた数を指します。
就業者数
就業者数は6,838万人で、前年同月比72万人の増加。
こちらも34か月連続の増加となっており、特に医療・福祉、製造業、宿泊業などでの雇用が拡大しています。
就業者の増加は、景気回復や人手不足への対応が背景にあると考えられます。
関連記事:採用戦略とは?進め方やメリット、ポイントをわかりやすく解説
雇用者数
就業者のうち、雇用契約に基づいて働く雇用者数は6,174万人。
この中には正規・非正規の労働者が含まれます。
雇用者数の増加は、企業の採用意欲の高まりと、労働市場の活性化を反映しています。
正規雇用・非正規雇用者数
2025年5月時点での正規雇用者数は約3,723万人、非正規雇用者数は約2,101万人となっています。
非正規雇用者の割合は全体の約35%で、依然として高い水準にあります。
特に女性や高齢者に非正規雇用が多く、雇用の安定性や待遇格差が課題となっています。
不本意非正規雇用者数
非正規雇用者の中でも、本来は正社員を希望していた「不本意非正規雇用者」は約160万人と推計されています。
これは非正規全体の約7.5%に相当し、前年よりもやや減少傾向にありますが、依然として女性や若年層に多いのが特徴です。
正規転換支援やキャリア形成支援の強化が求められます。
関連記事:直接雇用のメリットとは?間接雇用との比較や3年ルール、企業の義務についても解説
産業別就業者
産業別に見ると、医療・福祉分野が最多で、次いで製造業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業が続きます。
特に医療・福祉分野では高齢化に伴う需要増により、就業者数が増加傾向にあります。
一方で、建設業や農林水産業では人手不足が深刻化しており、業界ごとの雇用対策が必要です。
女性の労働力率
2025年5月時点の女性の労働力率は約45%で、前年より微増しています。
育児や介護との両立支援策の拡充や、柔軟な働き方の普及が背景にあり、今後もさらなる上昇が期待されます。
ただし、依然として非正規雇用の割合が高く、キャリア形成や賃金格差の是正が課題です。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
まとめ
日本の雇用は、伝統的な制度と新たな課題が交錯する過渡期にあります。
人材不足や非正規雇用の課題に対しては、制度改革と企業の柔軟な対応が求められます。
また、統計データをもとに現状を正確に把握し、戦略的な人材マネジメントを行うことが、持続可能な雇用環境の実現につながるでしょう。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説
関連記事:人材管理の方法は?手順やメリット、データベースの作成方法を解説