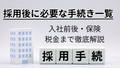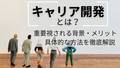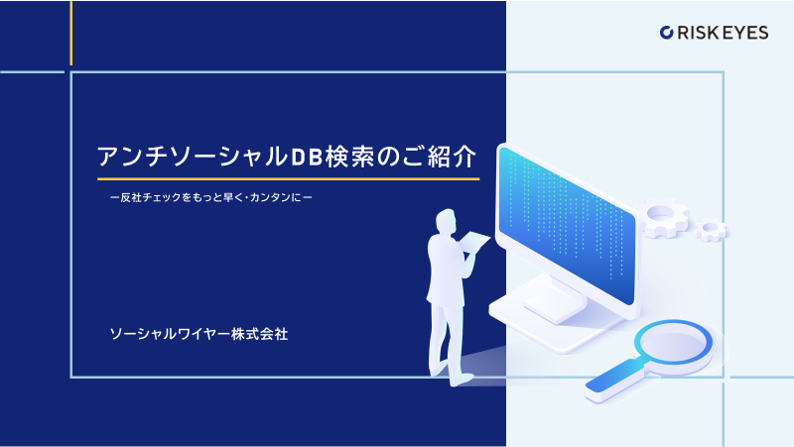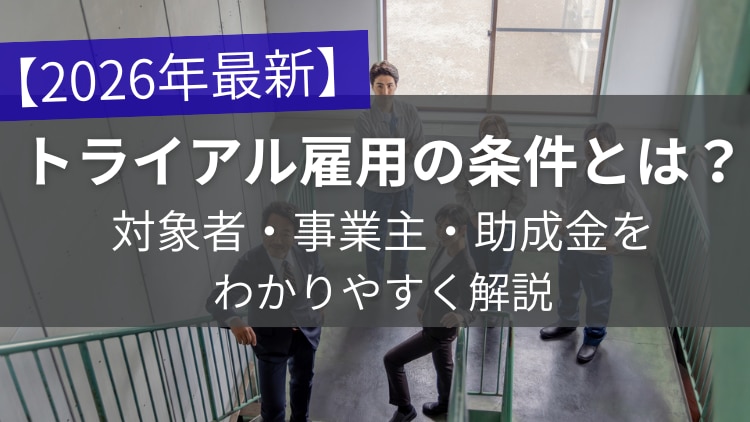
【2026年最新版】トライアル雇用の条件とは?対象者・事業主・助成金をわかりやすく解説
2026年現在、企業の採用活動において「トライアル雇用制度」の活用がますます注目されています。
求職者とのミスマッチを防ぎつつ、助成金の活用で採用コストも抑えられるこの制度は、特に中小企業にとって有効な選択肢です。
この記事では、対象者・事業主の条件から各コースの助成金額まで、最新情報をわかりやすく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
注意すべき相手をすぐに発見できる反社リストを検索
目次[非表示]
- 1.そもそもトライアル雇用とは?
- 1.1.試用期間との違い
- 2.トライアル雇用「一般トライアルコース」の条件
- 2.1.対象者の条件
- 2.2.事業主の条件
- 2.2.1.対象者の雇用を約束していない
- 2.2.2.3親等以内の親族を雇用していない
- 2.2.3.過去3年間に対象者を雇用したことがない
- 2.2.4.過去3年間で常用雇用に移行した人数
- 2.2.5.雇用保険の適用事業主
- 2.2.6.企業の都合で対象者を離職させた経歴がない
- 2.3.助成金の受給額
- 3.障害者向けのトライアル雇用「障害者トライアルコース」
- 4.障害者短時間トライアル雇用
- 5.若年・女性建設労働者トライアルコース
- 5.1.対象者の条件
- 5.2.事業主の条件
- 5.2.1.中小建設事業主
- 5.2.2.トライアル雇用助成金の支給決定を受けている
- 5.2.3.雇用保険の適用事業主
- 5.3.助成金の受給額
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【独自で収集した反社リストについてもっと知る】
そもそもトライアル雇用とは?

トライアル雇用とは、職業経験が乏しい、または長期離職中の求職者を対象に、企業が一定期間「お試し雇用」する制度です。
原則3か月間の有期雇用契約を結び、企業と求職者の双方が適性や能力を見極めたうえで、本採用(無期雇用)に移行するかどうかを判断します。
ハローワーク等の紹介を通じて実施され、採用ミスマッチの防止や人材確保を目的としています。
また、条件を満たすことで企業は助成金を受給できるため、採用コストの削減にもつながります。
試用期間との違い
一見似ている「試用期間」との違いは、雇用の前提と制度の有無です。
試用期間は本採用を前提とした雇用契約の一部であり、労働基準法に基づいて運用されます。
一方、トライアル雇用は本採用の義務がなく、制度として国が定めた条件に基づき、助成金の対象となります。
また、試用期間は企業が自由に期間を設定できますが、トライアル雇用は原則3か月と定められています。
関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説
トライアル雇用「一般トライアルコース」の条件

一般トライアルコースは、職業経験や技能が不足している求職者を対象に、企業が一定期間「お試し雇用」することで、適性を見極めながら本採用につなげる制度です。
ハローワーク等の紹介を通じて雇用されることが前提で、条件を満たすことで企業は助成金を受給できます。
対象者の条件
以下のいずれかに該当する求職者が対象となります。
- 過去2年以内に2回以上の離職・転職歴がある
- 離職期間が1年以上ある(パート・アルバイト含め一切の就労なし)
- 妊娠・出産・育児による離職後、1年以上安定した職に就いていない
- 60歳未満で安定した職に就いておらず、ハローワークで個別支援を受けている
- 特別な配慮が必要な者(生活保護受給者、母子・父子家庭の親、ホームレス等)
また、紹介日(ハローワーク等からの紹介日)において、安定した職業に就いていないことが条件です。
関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説
事業主の条件
トライアル雇用助成金を受給するには、事業主側にも複数の条件があります。
それぞれ解説します。
対象者の雇用を約束していない
雇用前に無期雇用契約を前提とした約束がないことが必要です。
あくまで「試行雇用」であることが前提です。
3親等以内の親族を雇用していない
対象者が事業主の親族(3親等以内)である場合は助成金の対象外となります。
公平性を保つための条件です。
過去3年間に対象者を雇用したことがない
同一人物を過去に雇用していた場合は対象外です。
新規雇用であることが求められます。
過去3年間で常用雇用に移行した人数
事業主が過去3年間にトライアル雇用を実施し、対象者を常用雇用(無期雇用)へ移行させた実績がある場合、その人数は助成金申請時の審査に影響します。
具体的には、以下の基準が設けられています。
- 過去3年間でトライアル雇用から常用雇用へ移行した人数が「0人」の場合→新規申請として扱われ、助成金の対象となる可能性が高いです。
- 過去3年間で移行人数が「1〜2人」の場合→制度の趣旨に沿った運用と判断され、申請は原則問題なく受理されます。
- 過去3年間で「3人以上」移行している場合→助成金の継続的な活用実績があるとみなされますが、申請内容によっては「制度の乱用」と見なされる可能性もあるため、移行後の定着率や雇用の安定性が審査対象となります。
この条件は、制度の趣旨である「安定的な雇用への移行」を促進するために設けられており、単なる助成金目的の雇用を防ぐためのものです。
過去の実績が多い場合は、移行後の雇用継続状況や職場環境の改善状況なども併せて評価されるため、申請前に自社の雇用履歴を整理しておくことが重要です。
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説
雇用保険の適用事業主
雇用保険に加入している事業所であることが必須です。
対象者も雇用保険の被保険者資格を取得する必要があります。
企業の都合で対象者を離職させた経歴がない
過去に企業都合で対象者を離職させた場合、助成金の対象外となる可能性があります。
安定した雇用環境が求められます。
助成金の受給額
一般トライアルコースでは、以下の助成金が支給されます。
- 月額4万円(対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合は月額5万円)
- 支給対象期間は最長3か月
- 支給は1回まとめて行われる(一括支給)
なお、対象者の就労日数が少ない場合は、以下のように減額されることがあります。
実働率 | 月額(通常) | 月額(母子・父子家庭) |
|---|---|---|
75%以上 | 40,000円 | 50,000円 |
50%以上75%未満 | 30,000円 | 37,500円 |
25%以上50%未満 | 20,000円 | 25,000円 |
1%以上25%未満 | 10,000円 | 12,500円 |
0% | 0円 | 0円 |
また、トライアル雇用期間中に無期雇用へ移行した場合や、対象者が途中で離職した場合も、実働日数に応じて支給額が調整されます。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説
障害者向けのトライアル雇用「障害者トライアルコース」

障害者雇用促進法により、一定規模以上の企業には障害者の雇用が義務付けられています。
しかし、実際の採用においては「業務への適応が不安」「職場環境との相性が分からない」といった課題も多く、企業・求職者双方にとってハードルとなっています。
そこで活用されているのが「障害者トライアルコース」です。
これは、障害者を一定期間試行的に雇用し、適性や能力を見極めたうえで本採用につなげる制度です。
対象者の条件
障害者トライアルコースの対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
- 障害者雇用促進法に定める障害者であること
- 継続雇用を希望しており、制度の内容を理解したうえでトライアル雇用を希望していること
- 以下のいずれかに該当すること
ア)紹介日において、未経験の職種への就職を希望している
イ)紹介日前2年以内に離職・転職を2回以上繰り返している
ウ)紹介日前時点で離職期間が6か月を超えている
エ)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者(上記ア〜ウに該当しなくても対象)
このように、就職困難な状況にある障害者に対して、雇用の機会を提供することが制度の目的です。
関連記事:企業の義務である障害者雇用 2024年改正「障害者雇用促進法」について詳しく解説
事業主の条件
事業主側にも以下の条件が求められます。
- ハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介による雇用であること
- 雇用保険の適用事業主であること
- トライアル雇用期間中に雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
- 派遣雇用ではないこと(派遣求人は対象外)
- トライアル雇用開始後2週間以内に「実施計画書」を提出すること
また、トライアル雇用期間中の勤務実態や契約内容を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書など)の提出も必要です。
助成金の受給額
障害者トライアルコースでは、対象者の属性に応じて助成金が支給されます。
まず、精神障害者を雇用する場合には、最大で6か月間の助成が認められています。
具体的には、最初の3か月間は月額最大8万円、その後の3か月間は月額最大4万円が支給されます。
これにより、企業は最大で合計36万円の助成を受けることが可能です。
一方、精神障害者以外の対象者(身体障害者や知的障害者など)を雇用する場合は、月額最大4万円が支給され、支給期間は最長3か月間となります。
つまり、最大で12万円の助成を受けることができます。
なお、支給額は対象者の出勤率に応じて変動します。
出勤率が高いほど満額に近い助成が支給され、出勤率が低い場合は段階的に減額される仕組みです。
また、トライアル雇用期間中に無期雇用へ移行した場合や、対象者が途中で離職した場合も、実働日数に応じて助成額が調整されます。
関連記事:雇用契約と業務委託契約の違いと見分け方を徹底解説!業務委託のメリットも解説
障害者短時間トライアル雇用

障害者短時間トライアル雇用は、精神障害者や発達障害者など、長時間勤務が難しい方を対象に、週10時間以上20時間未満の短時間勤務からスタートする試行雇用制度です。
企業と求職者が実際の業務を通じて適性や職場環境の相性を確認しながら、最終的には週20時間以上の継続雇用を目指すことを目的としています。
対象者の条件
この制度の対象となるのは、以下の条件を満たす精神障害者または発達障害者です。
- 継続雇用を希望していること
- 障害者短時間トライアル雇用制度の内容を理解し、制度を利用しての雇用を希望していること
また、対象者はハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介によって雇用される必要があります。
自社採用や直接応募では制度の対象外となるため注意が必要です。
関連記事:直接雇用のメリットとは?間接雇用との比較や3年ルール、企業の義務についても解説
事業主の条件
事業主が助成金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業主であること
- ハローワーク等の紹介によって対象者を雇い入れること
- 雇用契約開始後2週間以内に「実施計画書」を提出すること
- 雇用契約時の週所定労働時間が10時間以上20時間未満であること
- トライアル雇用期間中に、週20時間以上の勤務へ移行することを目指していること
この制度は、障害者の職場適応や体調に配慮しながら、段階的に就労時間を増やすことを支援する仕組みです。
助成金の受給額
障害者短時間トライアル雇用では、対象者1人につき月額最大4万円の助成金が支給されます。
支給期間は最長12か月間で、企業は最大48万円の助成を受けることが可能です。
ただし、実際の支給額は対象者の出勤率に応じて変動します。
出勤率が高い場合は満額に近い助成が支給されますが、出勤率が低い場合は段階的に減額される仕組みです。
また、途中で無期雇用に移行した場合や離職した場合も、実働日数に応じて助成額が調整されます。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
若年・女性建設労働者トライアルコース

建設業界では、若年層や女性の人材確保が長年の課題となっています。
特に現場作業に従事する人材の高齢化が進む中、若手や女性の新規参入を促進するための支援策として「若年・女性建設労働者トライアルコース」が設けられています。
この制度は、一定期間の試行雇用を通じて適性を見極めながら、常用雇用への移行を目指すもので、条件を満たす中小建設事業主には助成金が支給されます。
対象者の条件
このコースの対象となるのは、以下の条件をすべて満たす労働者です。
- トライアル雇用開始時点で35歳未満の若年者、または女性であること
- 主として建設工事現場での現場作業(例:左官、大工、鉄筋工、配管工など)または施工管理業務(例:現場監督)に従事すること(※設計、測量、経理、営業などの職種は対象外)
- 実労働時間の半分以上を現場作業または施工管理に充てていること
- 一般トライアルコースまたは障害者トライアルコースの対象者であること
この制度は、単なる若年者・女性の雇用支援ではなく、建設現場での実務経験を積ませることを目的としています。
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?必須項目や2024年法改正に伴う変更点について解説
事業主の条件
若年・女性建設労働者トライアルコースの助成金を受給するには、事業主側にも以下の条件が求められます。
それぞれ詳しく解説します。
中小建設事業主
事業主は以下のすべての条件を満たす「中小建設事業主」である必要があります。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 建設業として雇用保険料率の適用を受けていること
- 資本金が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下であること
- 雇用管理責任者を選任していること
この条件により、制度は中小企業の人材確保を重点的に支援する仕組みとなっています。
トライアル雇用助成金の支給決定を受けている
本コースの助成金を受けるには、まず「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」の支給決定を受けていることが前提です。
つまり、若年・女性建設労働者トライアルコースは、既存のトライアル制度に上乗せされる形で運用されます。
雇用保険の適用事業主
雇用保険に加入していることは必須条件です。
対象者も雇用保険の被保険者資格を取得する必要があります。
助成金の受給額
助成金は、対象者1人につき月額最大4万円が支給されます。
支給期間は最長3か月間で、企業は最大12万円の助成を受けることが可能です。
ただし、実際の支給額は対象者の出勤日数に応じて変動します。
トライアル雇用期間中に常用雇用へ移行した場合や、途中で離職した場合は、実働日数に応じて助成額が調整されます。
また、制度の趣旨に反する虚偽申請や労働関係法令違反があった場合は、助成金が不支給となる可能性があります。
関連記事:日本の雇用問題とは?解決に向けた対策や知っておくべき統計データを解説
まとめ
2026年現在、トライアル雇用制度は多様化し、一般求職者だけでなく障害者や建設業界の若年・女性労働者にも対応しています。
制度を活用することで、企業は採用ミスマッチを防ぎ、助成金を受けながら人材確保が可能です。
導入を検討する際は、ハローワークを通じた紹介や実施計画書の提出など、手続きの流れを事前に確認しておきましょう。
制度の詳細は厚生労働省の公式ページや各地域の労働局で確認できます。
関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説
関連記事:戦略人事とは?メリットや必要な機能、成功させるためのポイントを解説