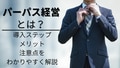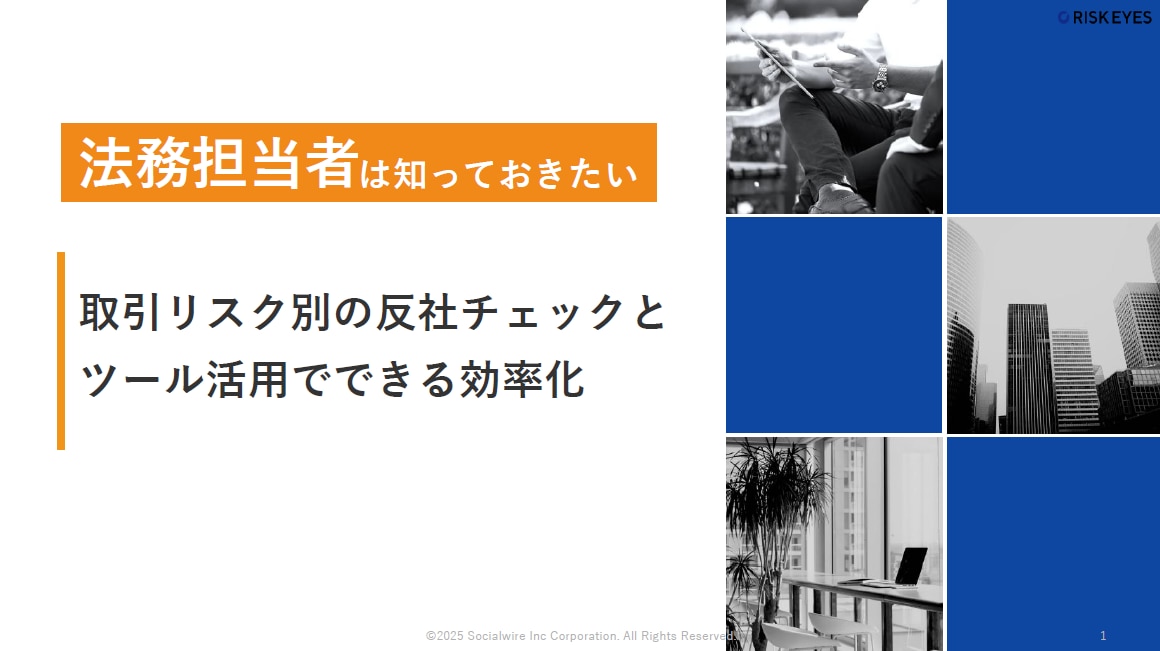人事評価エラーとは?11種類の具体例と原因・防止策を徹底解説
人事評価は、従業員のモチベーションや組織の成長に直結する重要なプロセスです。
しかし、評価者の主観や認知バイアスが入り込むことで「人事評価エラー」が発生し、公平性や信頼性が損なわれることがあります。
この記事では、人事評価エラーの種類と原因、そしてそれを防ぐための具体策を徹底解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【実務担当者】取引リスク別反社チェック効率化の方法
目次[非表示]
- 1.人事評価エラーとは?
- 1.1.人事評価エラーが発生する原因
- 2.11種類の人事評価エラー
- 2.1.ハロー効果
- 2.2.中心化傾向
- 2.3.寛大化傾向
- 2.4.逆算化傾向
- 2.5.論理誤差
- 2.6.対比誤差
- 2.7.期末誤差
- 2.8.極端化傾向
- 2.9.厳格化傾向
- 2.10.親近効果
- 2.11.アンカリング
- 3.人事評価エラーが引き起こす問題
- 3.1.部署内の関係性の悪化
- 3.2.離職率の増加
- 3.3.訴訟問題に発展
- 4.人事評価エラーを防ぐ対策
- 4.1.具体的事実に基づいた評価
- 4.2.評価基準の明確化
- 4.3.1つの事実は1つの要素として評価
- 4.4.公私混同に注意
- 4.5.評価者同士での基準のすり合わせ
- 4.6.複数評価者による評価
- 4.7.評価者研修の実施
- 4.8.フィードバック面談の実施
- 5.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの効率化を学ぶ】
人事評価エラーとは?
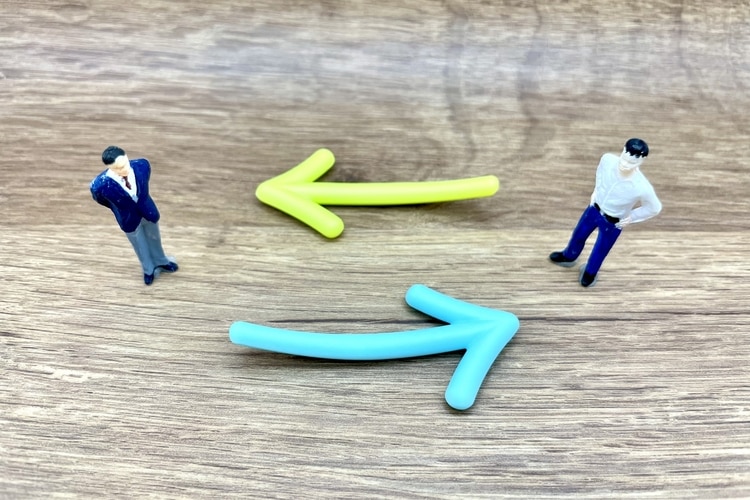
人事評価エラーとは、評価者の主観や認知バイアスによって、従業員の実際の能力や成果とは異なる評価が下されてしまう現象です。
評価制度は本来、公平かつ客観的であるべきですが、評価者の思い込みや感情が入り込むことで、評価の信頼性が損なわれ、従業員のモチベーション低下や組織内の不満につながる恐れがあります。
人事評価エラーが発生する原因
主な原因は、評価者の経験不足や評価基準の曖昧さ、そして人間特有の認知バイアスです。
例えば、印象に残った一場面だけで全体を判断したり、他者との比較で評価が歪むことがあります。
また、評価時の感情や人間関係も影響を与えるため、評価者には高い客観性と倫理意識が求められます。
適切な研修や制度設計が、こうしたエラーの防止に不可欠です。
関連記事:人事評価制度を導入するメリットとは?課題や制度を見直すべきタイミングを解説
11種類の人事評価エラー

人事評価は、従業員の成長支援や組織の健全な運営に欠かせない重要なプロセスです。
しかし、評価者の認知バイアスや主観が入り込むことで、評価の公平性が損なわれる「人事評価エラー」が発生します。
ここでは、代表的な11種類の評価エラーについて、それぞれの特徴と注意点を解説します。
ハロー効果
ハロー効果とは、ある一つの優れた特徴が他の評価項目にも好影響を与えてしまう現象です。
例えば、「明るく元気な社員だから仕事もできるはず」といった印象が、実際の業務成果とは関係なく高評価につながることがあります。
逆に、ネガティブな印象が全体評価を下げる「逆ハロー効果」も存在します。
中心化傾向
中心化傾向は、評価者が極端な評価を避け、すべての項目を平均的なスコアに寄せてしまう傾向です。
これにより、優秀な人材の成果が埋もれてしまい、組織の人材育成や適正な報酬分配が妨げられる可能性があります。
関連記事:人事評価によくある課題と解決策とは?IT活用で効率化する方法も解説
寛大化傾向
寛大化傾向とは、評価者が厳しい評価を避け、全体的に高めのスコアをつけてしまう傾向です。
特に人間関係を重視する文化や、評価者が部下との関係悪化を恐れる場合に起こりやすく、組織の課題が見えづらくなるリスクがあります。
逆算化傾向
逆算化傾向は、最終的な評価スコアを先に決め、それに合わせて各項目の評価を調整することです。
例えば、「この社員はB評価にしたい」と決めたうえで、各項目の点数を調整するようなケースです。
これにより、評価の客観性が失われ、評価制度への信頼が低下します。
論理誤差
論理誤差は、評価項目間に因果関係があると誤認し、ある項目の評価が他項目に影響することです。
たとえば、「プレゼンが上手=リーダーシップも高い」といった論理的な飛躍が評価に反映されると、本来の能力を正しく測ることができません。
関連記事:モチベーション向上で生産性アップ!社員の意欲を引き出す8つの方法を解説
対比誤差
対比誤差は、他の従業員との比較によって評価が歪む現象です。
優秀な社員の後に普通の社員を評価すると、相対的に過小評価されることがあります。
評価はあくまで個人の基準に基づいて行うべきであり、他者との比較は避けるべきです。
期末誤差
期末誤差とは、評価期間の終盤の印象が強く残り、初期のパフォーマンスが軽視される傾向です。
特に成果主義の組織では、直近の成果が評価に強く影響することがあり、継続的な努力や改善が正当に評価されないことがあります。
極端化傾向
極端化傾向は、評価者が極端なスコア(非常に高いまたは低い)をつける傾向です。
個人の価値観や感情が強く反映される場合に起こりやすく、評価の一貫性が損なわれる原因となります。
特定の評価者に偏った傾向が見られる場合は、評価者研修などの対策が必要です。
関連記事:パフォーマンス評価とは?目的とメリット、導入方法を解説
厳格化傾向
厳格化傾向は、評価者が意図的に厳しい評価を下す傾向です。
昇進や報酬に慎重な組織文化や、評価者自身が高い基準を持っている場合に起こりやすく、従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。
親近効果
親近効果は、評価者と被評価者の関係性(同じ部署、出身校、趣味など)が評価に影響することです。
無意識のえこひいきが生じることで、他の社員との公平性が損なわれ、組織内の不満や不信感を招くことがあります。
アンカリング
アンカリングは、最初に提示された情報(例:前回の評価)が基準となり、その後の評価がそれに引きずられる現象です。
たとえば、前回「C評価」だった社員に対して、今回も同様の評価をつけてしまうなど、過去の印象が現在の評価に影響を与えることがあります。
関連記事:人事と労務の役割と違いとは?業務内容や年間スケジュール、効率化の方法を解説
人事評価エラーが引き起こす問題
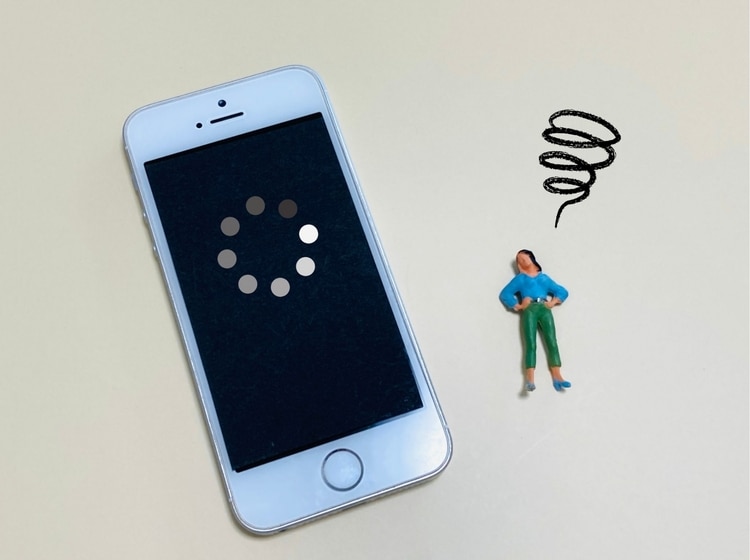
人事評価におけるエラーは、単なる評価ミスにとどまらず、組織全体に深刻な影響を及ぼします。
評価の公平性が損なわれることで、従業員の信頼やモチベーションが低下し、組織の健全な運営が脅かされる可能性があります。
ここでは、代表的な3つの問題について解説します。
部署内の関係性の悪化
不公平な評価は、従業員間の信頼関係を崩し、協力体制やチームワークに悪影響を与えます。
特定の社員が過大評価される一方で、努力が正当に認められない社員がいると、職場内に不満や対立が生まれやすくなります。
結果として、コミュニケーションの停滞や業務効率の低下を招くことになります。
関連記事:コンプライアンスと心理的安全性の関係とは?見るべきサインや向上させる方法を解説
離職率の増加
評価に納得感が持てない従業員は、自身の成長機会や報酬に不安を感じ、転職を選ぶ傾向が強まります。
特に、評価が昇進や給与に直結している場合、不当な評価はキャリアの停滞と捉えられ、優秀な人材の流出につながります。
これは企業にとって大きな損失であり、採用・育成コストの増加にも直結します。
訴訟問題に発展
人事評価が差別的、または不合理であると判断された場合、従業員からの訴訟リスクが生じます。
特に、昇進・降格・解雇などの意思決定に評価が関与している場合、不当な評価がハラスメントや不利益処遇とみなされる可能性があります。
企業は、評価の透明性と記録の整備を徹底することで、法的リスクを回避する必要があります。
関連記事:人材育成とは?注目される理由や育成の目的、方法をわかりやすく解説
人事評価エラーを防ぐ対策

人事評価は、従業員の成長支援や組織の健全な運営に欠かせない重要な制度です。
しかし、評価者の主観や認知バイアスが入り込むことで「人事評価エラー」が発生し、評価の公平性が損なわれることがあります。
こうしたエラーを防ぐためには、制度設計だけでなく、評価者の意識改革と運用面での工夫が不可欠です。
以下では、実務に活かせる8つの具体策を紹介します。
具体的事実に基づいた評価
評価は印象や感情ではなく、客観的な事実に基づいて行うことが基本です。
たとえば、「〇〇プロジェクトで納期を3日短縮した」「月間売上目標を120%達成した」など、数値や行動に裏付けられた成果を評価の根拠とすることで、主観的な判断を排除できます。
記録を残す習慣や、業務日報・成果報告の活用が有効です。
評価基準の明確化
評価項目ごとに具体的な基準を設定し、評価者間で共通認識を持つことが重要です。
たとえば「コミュニケーション力」なら、「会議での発言頻度」「他部署との連携実績」など、評価対象を明文化することで、ばらつきを防ぎます。
評価シートやマニュアルの整備により、基準の一貫性を保つことができます。
関連記事:人材マネジメントとは?その内容や必要性、ポイントを解説
1つの事実は1つの要素として評価
一つの出来事を複数の評価項目に反映させると、評価が過剰に偏るリスクがあります。
たとえば「プレゼンが上手だった」という事実を、「表現力」「リーダーシップ」「論理性」など複数項目に反映させると、ハロー効果が生じやすくなります。
1つの事実は1つの評価要素に限定し、評価の重複を避けることが公平性につながります。
公私混同に注意
評価者の個人的な感情や人間関係が評価に影響することは避けなければなりません。
たとえば「気が合う」「よく話しかけてくれる」といった印象が評価に反映されると、他の社員との公平性が損なわれます。
評価時には、業務上の成果や行動にのみ着目し、私的な感情を排除する意識が求められます。
評価者同士での基準のすり合わせ
複数の評価者がいる場合、評価基準のすり合わせを定期的に行うことで、評価のばらつきを防ぐことができます。
評価会議や事前レビューを通じて、「この行動はどの項目に該当するか」「どの程度の評価が妥当か」といった認識を共有することで、組織全体の評価精度が向上します。
関連記事:人事制度とは?3本柱とその役割、制度構築のフローを解説
複数評価者による評価
360度評価や共同評価など、複数の視点から評価を行うことで、個人の主観による偏りを軽減できます。
直属の上司だけでなく、同僚や他部署の関係者からのフィードバックを取り入れることで、より多面的で客観的な評価が可能になります。
特に管理職やリーダー層の評価には有効です。
評価者研修の実施
評価者に対して、人事評価の目的や評価エラーの種類、適切な評価方法を学ぶ研修を定期的に実施することが効果的です。
研修では、ケーススタディやロールプレイを通じて、実際の評価場面を想定したトレーニングを行うことで、評価者の意識とスキルを高めることができます。
フィードバック面談の実施
評価結果を被評価者に丁寧に説明し、納得感を高めることも重要です。
フィードバック面談では、評価の根拠となる事実や行動を具体的に伝えることで、評価への信頼性が向上します。
また、被評価者の自己認識とのギャップを埋めることで、次期の成長目標設定にもつながります。
関連記事:戦略人事とは?メリットや必要な機能、成功させるためのポイントを解説
まとめ
人事評価は、組織の健全な成長と従業員のキャリア形成に欠かせないプロセスです。
しかし、評価者の認知バイアスや主観が入り込むことで、評価の公平性が損なわれるリスクがあります。
今回紹介した11種類の人事評価エラーとその防止策を理解し、実務に活かすことで、より透明性の高い評価制度を構築することが可能です。
評価制度の見直しは、組織の信頼性向上と人材定着の鍵となります。
関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説
関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説