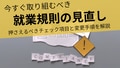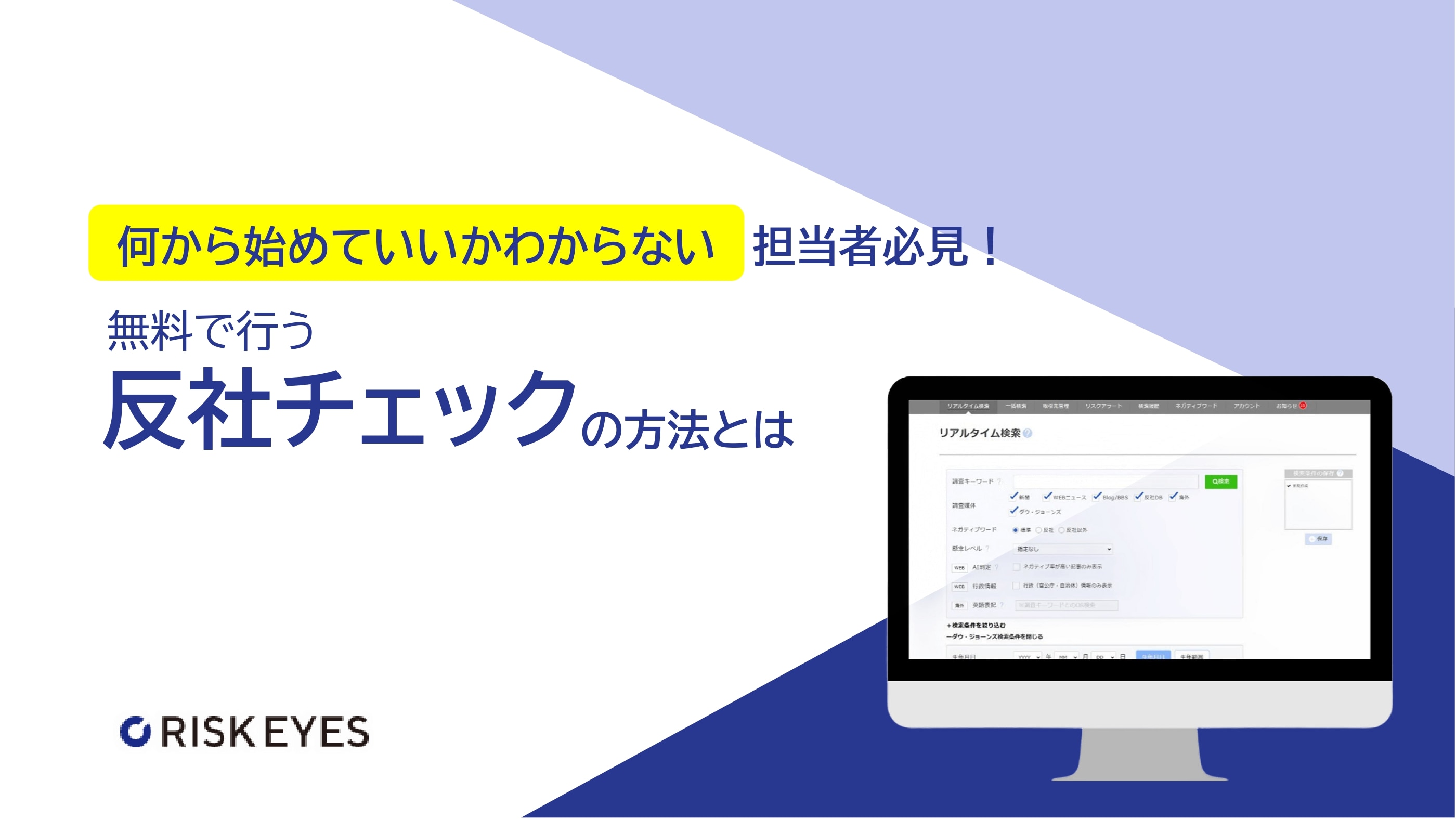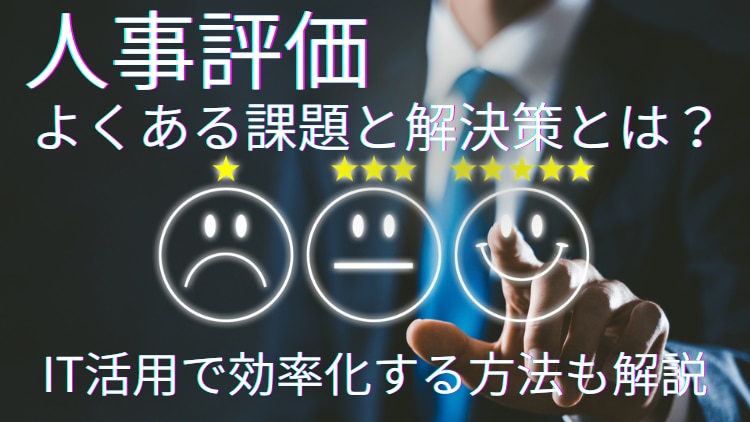
人事評価によくある課題と解決策とは?IT活用で効率化する方法も解説
人事評価制度は、企業の成長や従業員の定着・育成に深く関わる重要な仕組みです。
しかし現場では、評価の曖昧さや工数の多さ、公平性の欠如などさまざまな課題が浮上しています。
この記事では、人事評価によくみられる課題を整理し、その具体的な解決策を紹介します。
また、IT活用による業務の効率化や評価の質向上についても詳しく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【初心者必見】反社チェックのやり方・業務フローまとめ
目次[非表示]
- 1.そもそも人事評価とは
- 1.1.人事評価の3つの目的
- 1.2.約半数が人事評価に不満を抱えている
- 2.人事評価の課題とそれぞれの解決策
- 2.1.評価に工数がかかる
- 2.2.評価基準が曖昧
- 2.3.企業の現状や社会情勢にそぐわない
- 2.4.企業と従業員に温度差がある
- 2.5.評価担当者によって結果が異なる
- 2.6.設計の段階に問題がある
- 2.7.評価が離職防止に結びついていない
- 2.8.リモートワークに対応できていない
- 2.9.評価に見合った待遇がない
- 3.人事評価制度に問題がある場合どうなる
- 3.1.生産性が低下する
- 3.2.人材が定着しない
- 3.3.企業イメージが悪化する
- 4.ITを活用した人事評価の最適化
- 4.1.評価制度のデジタル化による業務負担の軽減
- 4.2.公平性の確保
- 4.3.評価と人材育成を連携し、組織の成長を促す
- 5.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの基本を学ぶ】
そもそも人事評価とは

人事評価とは、従業員の業務成果や能力、勤務態度などを一定の基準で評価し、昇進・昇給・配置などの人事判断に活用する制度です。
単なる査定ではなく、企業の成長と従業員の育成を両立させる重要な仕組みといえます。
人事評価の3つの目的
人事評価には主に3つの目的があります。
1つ目は「適切な人材配置と待遇の決定」。
従業員の能力や成果に応じた配置や報酬を実現することで、組織の生産性向上につながります。
2つ目は「効率的な人材育成」。
評価を通じて課題を明確にし、育成方針を立てることが可能です。
3つ目は「経営ビジョンの浸透」。
評価基準に企業理念を反映させることで、従業員の行動を組織の方向性と一致させる効果があります。
関連記事:人事評価制度を導入するメリットとは?課題や制度を見直すべきタイミングを解説
約半数が人事評価に不満を抱えている
しかし、理想的な制度とは裏腹に、実際には多くの従業員が人事評価に不満を抱えています。
日経の記事によると、約半数が「評価が適正でない」「納得できない」と感じているとのことです。
その背景には、評価基準の不透明さやフィードバック不足、評価者の主観が入りやすい構造などが挙げられます。
制度の目的を明確にし、運用の透明性を高めることが、納得感のある評価制度の第一歩です。
人事評価の課題とそれぞれの解決策

人事評価制度は、従業員の成長支援や組織力の強化に欠かせない仕組みです。
しかし、制度の運用においては多くの課題が存在し、従業員の納得感や企業の生産性に影響を及ぼすことも少なくありません。
ここでは、よく見られる課題とその解決策を具体的に紹介します。
評価に工数がかかる
人事評価は、シートの作成や記入、面談の実施、結果の集計など多くの工程を含むため、評価担当者に大きな負担がかかります。
これにより、制度そのものが「手間のかかる業務」として形骸化するリスクもあります。
この課題を解決するには、クラウド型評価ツールの導入が効果的です。
評価項目のテンプレート化、自動集計機能、リマインダーなどを活用することで、業務の効率化と属人性の排除を実現できます。
評価基準が曖昧
何を基準に評価されているのかが明確でないと、従業員は納得感を得られず、不信感を抱くことになります。
「努力しても何が評価されるか分からない」という状況は、モチベーション低下の温床です。
解決策としては、職種や役割に応じた具体的な評価項目を設け、評価基準を事前に共有することが重要です。
OKR(Objectives and Key Results)やコンピテンシー評価などを活用することで、目標と行動を整合させることも可能です。
関連記事:パフォーマンス評価とは?目的とメリット、導入方法を解説
企業の現状や社会情勢にそぐわない
評価制度が過去の前提で構築されたままだと、リモートワークやジョブ型雇用といった新しい働き方に対応できません。
これでは、優秀な人材の適正評価が困難になります。
定期的な制度の見直しが欠かせません。
成果だけでなく、プロセス・協働姿勢・新しい業務スタイルへの対応力など、現代的な要素を評価に組み込むことがポイントです。
企業と従業員に温度差がある
制度に対する認識が企業と従業員で大きく異なると、制度は十分に機能しません。
「何のために評価されるのか」「どう役立つのか」が伝わっていないケースが多く見られます。
この温度差は、制度導入前後の説明会やワークショップ、フィードバック面談を通じて埋めることが可能です。
さらに、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)との連動を図ることで、企業文化への共感を醸成できます。
関連記事:【法務担当者必見】2025年の主な法改正を一覧で解説
評価担当者によって結果が異なる
評価者によって判断が大きく異なれば、公平性が損なわれ、制度そのものへの信頼が低下します。
特に部門間で評価にばらつきが出ると、不満が社内に広がりやすくなります。
360度評価の導入や評価者向け研修を通じて、基準の統一と主観の排除を図ることが重要です。
また、AIによる定量的分析を補完的に活用することで、さらなる客観性の向上が期待できます。
設計の段階に問題がある
制度が複雑すぎたり、実態にそぐわない内容で構築されていたりすると、運用がうまくいかず、現場に定着しません。
設計段階から従業員にとって負担が大きく「使いにくい制度」になってしまうケースもあります。
解決には、制度設計の段階で現場の意見を取り入れ、「シンプル・明確・柔軟」を基本に構築することが求められます。
試験導入と改善サイクルを通じて、現場にフィットする制度へと育てていく姿勢が大切です。
評価が離職防止に結びついていない
評価が昇給やキャリア形成に反映されない場合、従業員は成果を出しても報われないと感じ、離職リスクが高まります。
せっかくの評価が、従業員の不満につながる逆効果になることもあります。
この課題は、評価結果を具体的な処遇に反映することで解決できます。
昇格・昇給・表彰制度との連動、育成計画への接続、納得感のあるフィードバックの実施が重要です。
関連記事:社内規程の種類と作り方、作成のポイントをわかりやすく解説
リモートワークに対応できていない
リモート環境では、勤怠や貢献度を評価しづらく、従業員の努力が見えづらくなります。
その結果、オフィス勤務者とリモート勤務者で評価に差が出ることもあります。
ここでは、成果管理型の評価制度(MBOやOKRなど)の導入が有効です。
目標設定と進捗報告を可視化し、定期的な1on1や週次報告を通じてプロセスも評価対象に含めることで、勤務形態に左右されない制度が実現します。
評価に見合った待遇がない
高評価を得ても報酬や昇進に反映されなければ、従業員は不満を抱え、「頑張る意味がない」と感じてしまいます。
これでは評価制度の目的そのものが揺らぎます。
この課題の解決には、評価と報酬の連動性を明示し、制度として社内にしっかり根付かせる必要があります。
報酬体系との接続や、処遇の透明化を進めることで、モチベーション維持につながります。
関連記事:労務トラブルとは?発生時の対応手順や注意点、未然に防ぐ対策を解説
人事評価制度に問題がある場合どうなる

企業の持続的な成長を支えるうえで、人事評価制度は欠かせない基盤のひとつです。
適切な評価は、従業員のモチベーション向上や人材の育成、組織力の強化に直結します。
しかし、制度設計や運用に問題があると、期待される機能が十分に発揮されず、かえって組織全体に深刻な影響を及ぼす可能性もあります。
従業員の不満が高まり、パフォーマンスや定着率の低下、企業イメージの悪化など、複数のリスクが連鎖的に発生します。
ここでは、人事評価制度に不備がある場合に生じる代表的な3つのリスクについて、具体的に解説していきます。
関連記事:解雇するための条件とは?主な解雇理由や解雇後の注意点についてわかりやすく解説
生産性が低下する
評価基準が曖昧だったり、評価者によって判断がばらつくと、従業員は「何を目指せばよいのか」が分からなくなります。
努力が正当に評価されない環境では、モチベーションが低下し、業務への集中力も失われがちです。
結果として、チーム全体のパフォーマンスが落ち、生産性の低下につながります。
人材が定着しない
不公平な評価制度は、従業員の不満を生みます。
特に、成果が処遇に反映されない場合、「この会社では頑張っても報われない」と感じ、優秀な人材ほど離職を選ぶ傾向があります。
定着率の低下は、採用・育成コストの増加を招き、企業の持続的な成長を阻害します。
企業イメージが悪化する
人事評価制度の不備は、社内だけでなく社外にも影響を及ぼします。
離職率の高さや従業員の不満がSNSや口コミで広がれば、「働きにくい会社」としての印象が定着し、採用活動にも支障をきたします。
企業ブランドの低下は、顧客や取引先からの信頼にも影響を与えるため、早急な改善が求められます。
関連記事:企業イメージをアップさせるコンプライアンス遵守を解説
ITを活用した人事評価の最適化

近年、企業の人材マネジメントにおいてITの活用が急速に進んでいます。
特に人事評価制度の分野では、デジタル化による業務効率化と評価の質向上が注目されています。
従来の紙ベースやExcelによる評価運用は、煩雑な作業や集計ミスのリスクを伴い、担当者の負担も大きいものでした。
そこで、評価制度のデジタル化が求められています。
評価制度のデジタル化による業務負担の軽減
クラウド型の人事評価システムを導入することで、評価シートの配布・回収・集計が自動化され、業務負担が大幅に軽減されます。
たとえば、ある介護施設では1,000枚以上の紙を扱っていた評価業務がゼロになり、集計作業も40時間からほぼゼロに短縮された事例があります。
これにより、評価者は本来の面談やフィードバックに集中できるようになり、組織全体の生産性向上にもつながります。
関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説
公平性の確保
ITを活用することで、評価基準の統一や評価プロセスの透明化が可能になります。
AIによる定量・定性データの分析により、評価者の主観や偏りを排除し、客観的な評価が実現します。
これにより、従業員の納得感が高まり、エンゲージメントの向上にも寄与します。
また、評価結果の見える化により、評価の信頼性が高まり、組織内の信頼関係の構築にも効果を発揮します。
評価と人材育成を連携し、組織の成長を促す
評価制度は単なる査定ではなく、人材育成と連動させることで真価を発揮します。
ITシステムを活用すれば、評価結果をもとに個々の強みや課題を分析し、育成計画や配置戦略に反映することが可能です。
これにより、従業員の成長支援と組織のパフォーマンス向上を両立でき、持続的な成長を実現する基盤となります。
関連記事:人材マネジメントとは?その内容や必要性、ポイントを解説
まとめ
人事評価制度は、企業と従業員の信頼関係を築く重要な仕組みです。
課題を放置すれば、離職や生産性低下を招きかねません。
制度の見直しとITの活用により、評価の納得感と運用効率を両立させることが可能です。
今こそ、自社の評価制度を再点検し、未来志向の人事戦略へと進化させましょう。
関連記事:戦略人事とは?メリットや必要な機能、成功させるためのポイントを解説
関連記事:人材育成とは?注目される理由や育成の目的、方法をわかりやすく解説