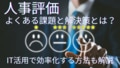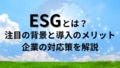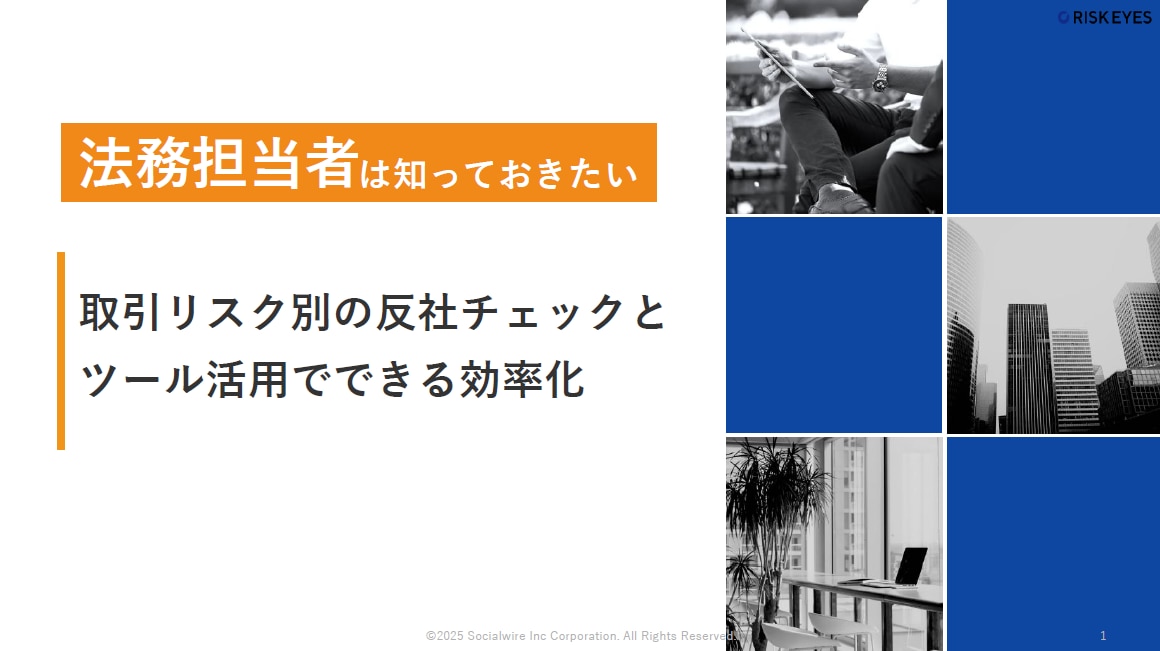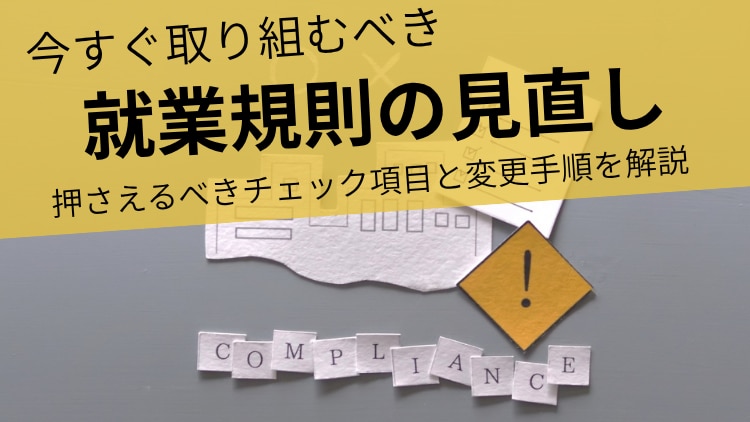
今すぐ取り組むべき就業規則の見直し―押さえるべきチェック項目と変更手順を解説
法改正や働き方の変化が進む中、企業が就業規則を放置することは大きなリスクを伴います。
労働環境の実態と規則の不一致は、法令違反だけでなく従業員の不満や人材流出にもつながりかねません。
今こそ、自社の規則を定期的に点検し、現代の制度やニーズに合致させる必要があります。
この記事では、見直しの必要性やタイミング、具体的なチェック項目、変更の流れまでを実務に役立つ形でわかりやすく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【実務担当者】取引リスク別反社チェック効率化の方法
目次[非表示]
- 1.就業規則の見直しが必要な理由
- 1.1.法改正への対応のため
- 1.2.労働環境を時代に合ったものに適正化するため
- 1.3.労働者の権利保護のため
- 1.4.助成金の申請に必要な場合がある
- 2.就業規則の見直しをすべきタイミング
- 2.1.就業規則と実態にギャップがあるとき
- 2.2.就業規則が社会情勢の変化に対応できていないとき
- 2.3.働き方に関する法改正があったとき
- 2.4.労働基準監督署から是正勧告を受けたとき
- 3.就業規則の見直しを怠った場合の3つのリスク
- 3.1.法令違反
- 3.2.従業員のモチベーションの低下や人材流出
- 3.3.不要なコストの発生
- 4.就業規則を見直す際のチェック項目
- 4.1.労働時間の制度に関する項目
- 4.2.テレワークに関する項目
- 4.3.賃金制度に関する項目
- 4.4.正社員以外の従業員に関する項目
- 4.5.育児・介護休業に関する項目
- 4.6.ハラスメント予防に関する項目
- 5.就業規則を変更する手順
- 5.1.変更内容の検討
- 5.2.労働組合にヒアリング
- 5.3.変更届の作成
- 5.4.労働基準監督署へ届け出
- 5.5.社内周知
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの効率化を学ぶ】
就業規則の見直しが必要な理由

企業が健全かつ効率的に運営されるためには、現場の運用に即した就業規則の整備が欠かせません。
特に近年では法改正や働き方の多様化が進み、規則の形骸化やリスク増大を防ぐために定期的な見直しが求められています。
以下のような理由から、企業は計画的なアップデートを検討すべきです。
法改正への対応のため
労働関連法は年々改正が重ねられており、未対応の就業規則は法令違反と見なされる可能性があります。
例えば、育児・介護休業法の改正や、ハラスメント防止に関する指針の強化など、現代の労務管理に求められるルールは多岐にわたります。
改正内容に即した規定の整備は、リスク回避だけでなく行政からの評価向上にもつながります。
労働環境を時代に合ったものに適正化するため
テレワークや副業制度、フレックス勤務など、従来とは異なる働き方が一般化しています。
こうした制度が就業規則上に明記されていないと、企業と従業員の認識にズレが生じ、後々トラブルの火種になる可能性があります。
就業規則の内容を現代の労働環境に適合させることで、従業員満足度の向上や優秀人材の定着にも効果が期待されます。
関連記事:法改正対応のポイントは?具体的な流れや情報収集方法を解説
労働者の権利保護のため
労使間のトラブルは、規則が曖昧なことに起因するケースが少なくありません。
たとえば、セクシャルハラスメント防止策や育児休業取得の詳細、賃金支給ルールなど、権利の所在を明確にする項目は就業規則に定義することが望まれます。
これにより、従業員の不安解消と信頼関係の構築が図れます。
助成金の申請に必要な場合がある
厚生労働省や自治体が提供する助成金制度の多くは、適正な労務管理が前提条件です。
たとえば「人材確保等支援助成金」では、就業規則に育児・介護休業制度が明記されていることが申請要件のひとつとなります。
機会損失を防ぐためにも、就業規則は常に整備された状態を保つ必要があります。
関連記事:リテンション施策とは?効果的な例や施策を立てる手順・ポイントを解説
就業規則の見直しをすべきタイミング
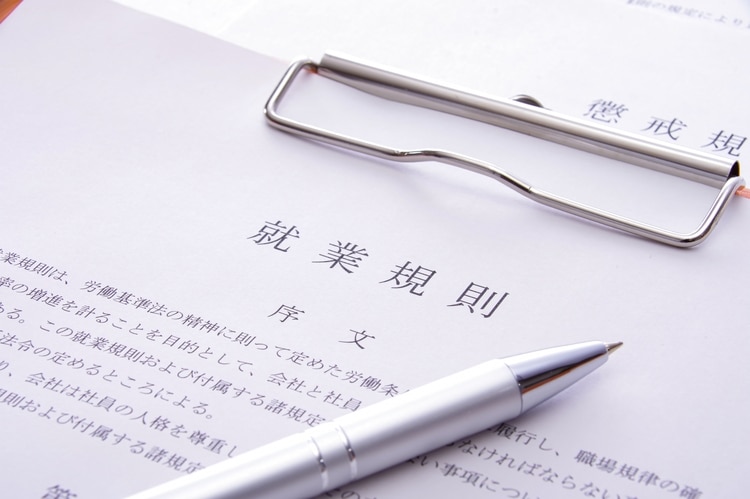
就業規則は、一度作成すれば終わりというものではなく、企業活動や社会の変化に応じて定期的に見直す必要があります。
ルールの形骸化を防ぎ、従業員との適切な労使関係を維持するためにも、最低でも年に一度の点検を推奨します。
以下のタイミングでは、特に重点的な確認と改訂が求められます。
就業規則と実態にギャップがあるとき
就業規則が記載している制度と、実際に現場で運用されている働き方や待遇に食い違いがある場合は、トラブルが生じやすくなります。
たとえば、フレックスタイム制を導入しているにもかかわらず、就業規則に記載がないなどは典型例です。
このようなギャップは法令違反に該当する可能性もあるため、早急な是正が必要です。
就業規則が社会情勢の変化に対応できていないとき
感染症対策、物価高騰への対応、副業・兼業の容認など、社会的背景に基づく働き方の変化は就業規則にも反映させるべき事項です。
たとえば、テレワークに関する規定が曖昧なままだと、費用負担や勤務管理に関するトラブルが起きる可能性もあります。
企業としての柔軟性を持つためにも、時代のニーズに合ったアップデートが不可欠です。
関連記事:副業は禁止できる?違法性から実例まで企業の判断基準を解説
働き方に関する法改正があったとき
育児・介護休業制度の改正、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金など、働き方に直結する法改正は頻繁に行われています。
これらに対応していない就業規則では、行政からの指導対象となる可能性があるだけでなく、従業員にとっても不利益が生じかねません。
施行日や改正内容を把握し、迅速な対応が求められます。
労働基準監督署から是正勧告を受けたとき
監督署からの是正勧告は、企業の労務管理に重大な問題があることを示すものです。
この勧告を受けた場合は、就業規則の該当箇所を速やかに見直し、改善策を講じることが求められます。
対応が遅れた場合、企業の信頼性に傷がつき、採用活動や従業員定着にも悪影響を及ぼしかねません。
関連記事:【法務担当者必見】2025年の主な法改正を一覧で解説
就業規則の見直しを怠った場合の3つのリスク

就業規則の改定は、企業が安定して運営されるための重要な業務です。
見直しを怠ることで、思わぬトラブルや損失が生じるリスクが高まります。
特に以下の3点は、企業の信頼性や経営に直接影響を与える重大なリスクです。
法令違反
労働関連法は定期的に改正されるため、就業規則が現行法に合致していないと法令違反と判断される可能性があります。
たとえば育児・介護休業法、ハラスメント防止指針などへの対応が不十分な場合、労働基準監督署からの是正指導や罰則の対象となり、行政上の信用が損なわれます。
関連記事:コンプライアンス違反を起こす人と組織 事例と対策を紹介
従業員のモチベーションの低下や人材流出
不明瞭で不合理な規則が続くと、従業員に不安や不信感が生まれます。
働き方や福利厚生に関するルールが実態と乖離していれば、職場環境への不満が高まり、離職や定着率の低下につながります。
信頼される職場づくりのためにも、就業規則の整備は欠かせません。
不要なコストの発生
曖昧な規則は、トラブル時の対応に時間や費用を要する原因となります。
訴訟費用や労務コンサルへの依頼、従業員対応の工数増加など、余計なコストが発生するケースは少なくありません。
リスク予防の観点からも、就業規則の見直しはコスト削減施策とも言えます。
関連記事:半グレと増加する闇バイト 新卒や若者にも必要な反社チェック
就業規則を見直す際のチェック項目

就業規則の見直しでは、企業の実態や最新の法改正を踏まえた項目の精査が不可欠です。
以下では、特に重要なチェックポイントとして意識すべき内容を解説します。
労働時間の制度に関する項目
フレックス制度、変形労働時間制、みなし労働時間制など、労働時間に関するルールは企業によって多様です。
特に「36協定」関連の残業規定や休憩時間の取り扱い、始業終業時刻の定義などは法令遵守の観点からも明文化しておく必要があります。
制度導入後に規則への反映が漏れているケースも散見されるため、運用との整合性を必ず確認しましょう。
関連記事:日本の労働法とは?種類と特徴、使用者の義務や注意すべきポイントを解説
テレワークに関する項目
コロナ禍以降、テレワーク制度は常設化している企業も多く見られます。
就業規則では在宅勤務時の勤務管理方法、通信費や機材の費用負担、情報セキュリティ対策、業務報告のルールなどを明記することが重要です。
曖昧なルールでは不正確な労働時間管理や、企業資産の毀損・情報漏洩リスクを引き起こす可能性があります。
賃金制度に関する項目
基本給、諸手当、賞与、昇給の有無とその基準、割増賃金の計算方法など、賃金に関する条項は従業員の生活に直結するため、特に慎重な記述が求められます。
同一労働同一賃金の流れを受けて、職務内容と報酬体系の整合性も見直しの対象です。
また、遅刻・早退・欠勤時の控除ルールも誤解を招かないよう明確化しましょう。
正社員以外の従業員に関する項目
パートタイマー、契約社員、アルバイトなど非正規雇用者に対する就業規則上の扱いは、雇用形態ごとに区分して記載するのが望ましいです。
就業時間、休暇、福利厚生、評価制度など、正社員との差異について透明性をもって示すことは、トラブルの未然防止にもつながります。
関連記事:直接雇用のメリットとは?間接雇用との比較や3年ルール、企業の義務についても解説
育児・介護休業に関する項目
育児・介護休業法の改正により、従業員が制度を柔軟に活用できる環境整備が求められています。
取得条件、申請方法、復帰後の就業形態、再配置の方針などを明記し、育児・介護との両立を支援する姿勢を明示することが、企業のイメージ向上にも貢献します。
ハラスメント予防に関する項目
近年の法改正により、パワハラ・セクハラ防止措置の義務化が進んでいます。
就業規則にはハラスメントの定義、相談窓口、調査・対応の手順、懲戒に関する方針を盛り込むことで、組織としての防止体制を構築できます。
曖昧な対応では企業責任を問われる可能性もあるため、定期的な見直しが必須です。
関連記事:企業が取り組むべきハラスメント対策 その重要性とメリットを解説
就業規則を変更する手順

企業が労働環境の整備や法令対応を目的に就業規則を変更する際には、単なる文言の修正にとどまらず、法的な手続きと社内への適切な説明が求められます。
変更の流れを理解し、抜け漏れなく進めることで、従業員との信頼関係を損なうことなく、円滑な運用が可能となります。
以下は、主な変更手順の流れです。
変更内容の検討
まずは、現行の就業規則と実態、法改正内容を比較し、改定すべき項目を明確にします。
特に労働時間制度、賃金規定、育児休業制度など、法令との整合性が重要な項目については優先的に見直しましょう。
また、社内ヒアリングや近年の労務トラブルを参考に、従業員視点での課題抽出も有効です。
関連記事:労務トラブルとは?発生時の対応手順や注意点、未然に防ぐ対策を解説
労働組合にヒアリング
就業規則の変更には、労働者代表との意見聴取が必須です。
労働組合がある場合は組合への説明、無い場合は過半数代表者からの意見を得ることになります。
ここでは変更案の趣旨や背景を丁寧に伝えることで、従業員の理解を得られやすくなります。
意見に対して文書で記録を残すことも忘れずに。
変更届の作成
意見聴取を踏まえた最終案が固まったら、変更箇所を反映した就業規則本文と、意見聴取結果を記載した「意見書」を作成します。
変更点が明確にわかるよう、改定前後の条文比較や新旧対照表などの資料を添付することが望ましいです。
関連記事:労務コンプライアンスとは?違反事例とチェックポイントを解説
労働基準監督署へ届け出
作成した変更届および添付書類を、就業規則の変更日から10日以内に所轄の労働基準監督署へ提出します。
受理されれば正式に効力が発生しますが、内容によっては修正指導が入ることもあるため、書式や内容の整合性には注意が必要です。
社内周知
変更後の就業規則は、社内イントラネットへの掲載、説明会の実施、メール通知などを活用して全従業員に周知します。
ただ配布するだけでなく、内容の正確な理解を促すための工夫が重要です。
特に賃金や労働時間に関連する項目はトラブル予防の観点からも丁寧な説明が求められます。
関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説
まとめ
就業規則は、企業運営の礎であり従業員との信頼関係を築く重要なツールです。
法改正や働き方の多様化に対応するため、定期的な見直しが不可欠です。
リスクを未然に防ぎ、時代に即したルールへとアップデートすることで、企業価値の向上と働きやすい職場環境の実現につながります。
関連記事:労務管理の目的と主な業務とは?関連法律や注意すべきポイントを解説
関連記事:社内規程の種類と作り方、作成のポイントをわかりやすく解説