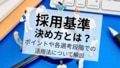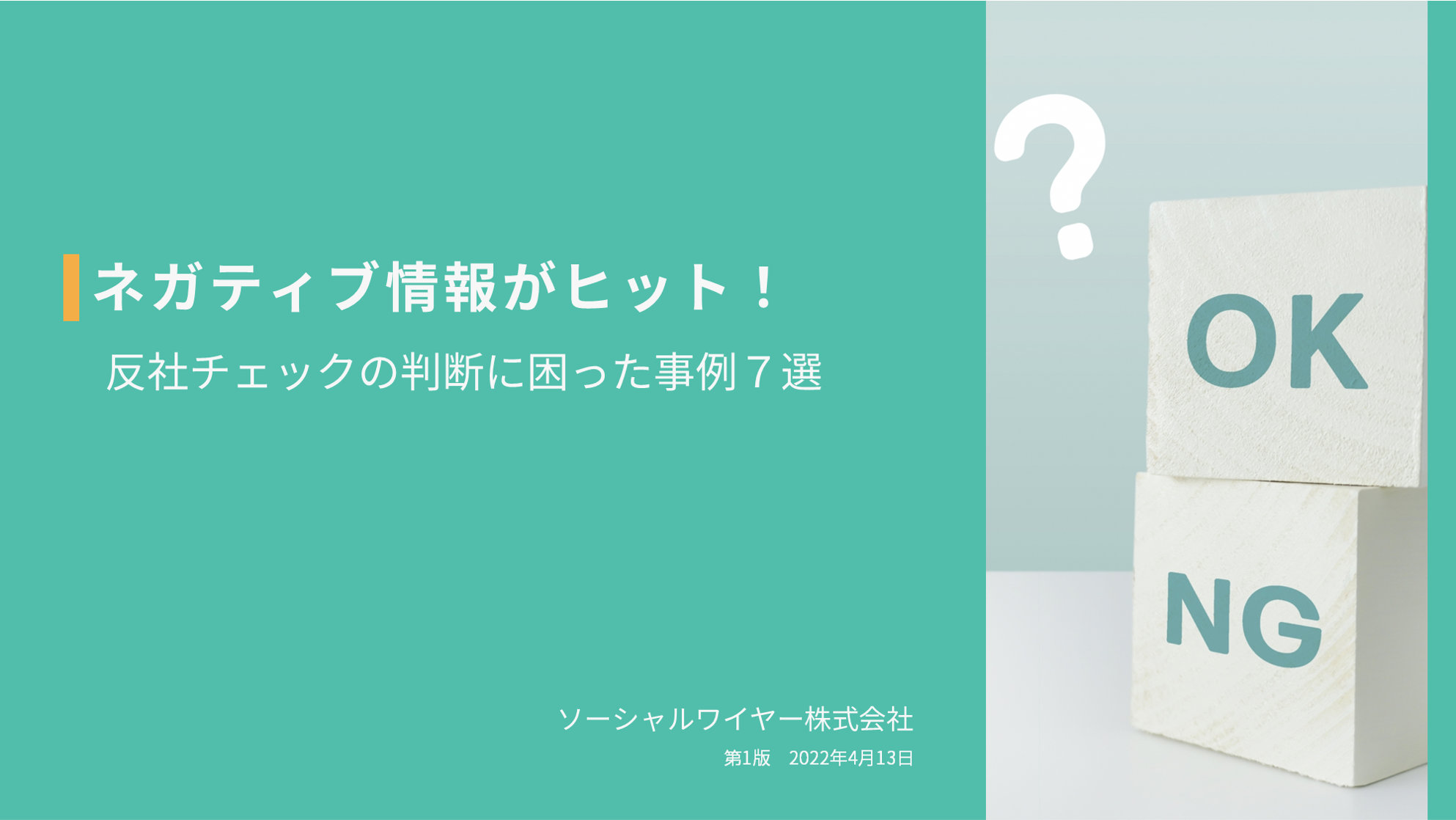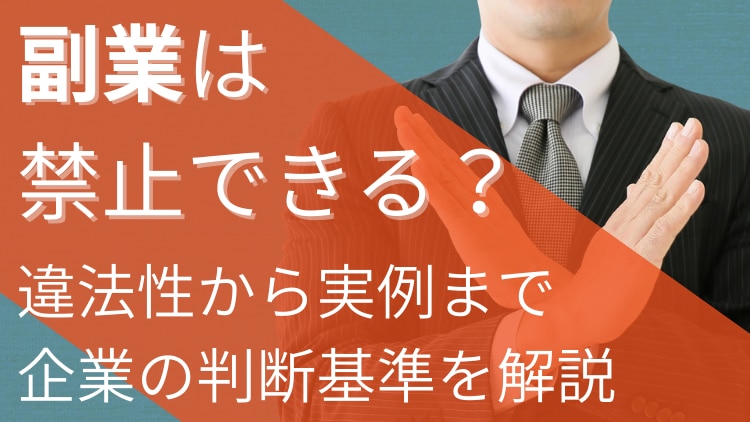
副業は禁止できる?違法性から実例まで企業の判断基準を解説
働き方改革やリモートワークの普及により、副業を希望する労働者が増加しています。
一方で、企業としては副業をどこまで認めるべきか、禁止することは法的に可能なのか、判断に迷うケースも少なくありません。
この記事では、副業の定義から違法性、企業が副業を禁止できるケース、そして実際に副業を解禁した企業の事例まで、企業が押さえるべき判断基準を解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【実務担当者】反社チェックの契約可否の判断に迷った事例
目次[非表示]
- 1.そもそも副業とは
- 1.1.兼業との違い
- 2.副業禁止は違法になるのか?
- 2.1.副業は法律で禁止されていない
- 2.2.公務員は原則として副業禁止
- 3.労働者の副業を禁止できるケース
- 3.1.会社の業務に支障が出る場合
- 3.2.会社の信用を損なうおそれがある場合
- 3.3.同業他社で働く場合
- 3.4.営業秘密の流出が懸念される場合
- 4.副業を禁止するメリット・デメリット
- 4.1.副業を禁止するメリット
- 4.1.1.生産性の維持・向上
- 4.1.2.情報漏洩リスクの低下
- 4.1.3.適切な従業員管理の実現
- 4.2.副業を禁止するデメリット
- 4.2.1.事業拡大の機会損失
- 4.2.2.知識やスキル獲得の機会損失
- 4.2.3.昔気質な企業イメージの定着
- 5.副業を解禁した企業の事例
- 5.1.クラウドソーシングサービス運営会社
- 5.2.大手製薬会社
- 5.3.インターネット関連事業を行う企業
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの事例を学ぶ】
そもそも副業とは

副業とは、本業とは別に収入を得るために行う仕事のことを指します。
たとえば、平日は会社員として働きながら、週末にライターやデザイナーとして活動するケースなどが該当します。
副業は、収入の補填やスキルアップ、キャリアの幅を広げる手段として注目されており、働き方改革の一環として政府もその推進を後押ししています。
副業の形態は多様で、アルバイトやフリーランス、ネットショップ運営、投資など、個人のライフスタイルや目的に応じて選択肢が広がっています。
特に近年は、リモートワークの普及により、時間や場所に縛られない副業が増加傾向にあります。
兼業との違い
兼業は複数の仕事を同等の比重で行う働き方を指します。
一方、副業は本業を主軸とし、空いた時間に行う補助的な仕事です。
企業の就業規則では「副業・兼業」とまとめて扱われることもありますが、実務上は目的や働き方に応じて区別されることが重要です。
関連記事:雇用期間に関する法律上のルールとは?有期雇用契約のポイントや注意点を解説
副業禁止は違法になるのか?

副業を希望する社員が増える中、企業としては「副業をどこまで認めるべきか」という判断が求められています。
結論から言えば、副業を一律に禁止することは、法的にリスクを伴う可能性があります。
詳しく解説します。
関連記事:労務管理の目的と主な業務とは?関連法律や注意すべきポイントを解説
副業は法律で禁止されていない
まず前提として、労働基準法や民法において、企業が社員の副業を一律に禁止する法的根拠は存在しません。
憲法第22条により「職業選択の自由」が保障されており、社員は原則として勤務時間外に自由な活動が可能です。
ただし、企業秩序の維持や業務への支障といった合理的な理由があれば、就業規則に基づき副業を制限できます。
公務員は原則として副業禁止
一方、公務員については国家公務員法・地方公務員法により、営利目的の副業が原則として禁止されています。
これは公務の中立性や公平性を確保するための措置であり、民間企業の社員とは異なる法的制約が課されています。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
労働者の副業を禁止できるケース

副業・兼業の推進が叫ばれる中でも、企業が一定の条件下で副業を制限・禁止できるケースは存在します。
労働者の自由と企業の秩序を両立させるためには、就業規則や労務管理の整備が不可欠です。
以下では、企業が副業を禁止できる代表的な4つのケースを解説します。
会社の業務に支障が出る場合
副業によって本業のパフォーマンスが低下する場合、企業は副業を制限できます。
たとえば、深夜勤務の副業により日中の業務に集中できない、疲労で遅刻や欠勤が増えるといったケースです。
これは労働契約上の「職務専念義務」に反する可能性があり、企業としては業務への支障を理由に副業の制限を正当化できます。
関連記事:福利厚生とは?種類や導入するメリット・デメリットをわかりやすく解説
会社の信用を損なうおそれがある場合
労働者が反社会的勢力と関わる業種や、公序良俗に反する副業に従事することで、企業の社会的信用が損なわれるリスクがあります。
たとえば、風俗業や違法性のあるビジネスへの関与が報道されれば、企業のブランドイメージにも悪影響を及ぼしかねません。
このような場合、企業は就業規則に基づき副業を禁止することが可能です。
同業他社で働く場合
労働者が同業他社で副業を行うことは、「競業避止義務」に違反する可能性があります。
たとえば、自社と競合する企業で営業や開発に従事する場合、自社の利益が直接的に損なわれるおそれがあるため、企業は副業を禁止できます。
特に営業先やノウハウの流用が疑われる場合は、厳格な対応が求められます。
営業秘密の流出が懸念される場合
副業先が同業でなくても、自社の技術や顧客情報などの営業秘密が漏洩するリスクがある場合、企業は副業を制限できます。
たとえば、開発職の社員が副業で類似製品の設計に関与する場合、意図せず情報が流出する可能性があります。
企業は秘密保持義務を根拠に、副業の内容を精査し、必要に応じて制限措置を講じるべきです。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説
副業を禁止するメリット・デメリット

働き方改革や多様なキャリア形成が進む中で、「副業解禁」を選択する企業が増えています。
一方で、依然として副業を禁止する企業も少なくありません。
ここでは、副業を禁止することによるメリットとデメリットを整理し、企業がどのような観点で判断すべきかを考察します。
副業を禁止するメリット
副業を禁止する3つのメリットを解説します。
生産性の維持・向上
副業を禁止することで、従業員が本業に集中しやすくなります。
副業による疲労や時間的制約がなければ、業務への集中力やパフォーマンスの維持が期待できます。
特に、納期や品質が重視される業務では、安定した稼働が求められるため、企業としては、副業によるリスクを回避することが合理的な判断となる場合があります。
関連記事:人事と労務の役割と違いとは?業務内容や年間スケジュール、効率化の方法を解説
情報漏洩リスクの低下
副業先が競合他社である場合、意図せずとも機密情報が漏洩するリスクが高まります。
副業を禁止することで、こうした情報セキュリティ上の懸念を最小限に抑えることができます。
特に、顧客情報や技術ノウハウを扱う業種では、情報管理の観点から副業制限が有効なリスクマネジメント手段となります。
適切な従業員管理の実現
副業を容認すると、労働時間の通算管理や健康状態の把握が複雑になります。
労働基準法では、複数の事業場で働く場合でも労働時間を通算する必要があるため、企業側の管理負担が増加します。
副業を禁止することで、労働時間や健康管理を一元的に把握しやすくなり、過重労働や労災リスクの低減にもつながります。
関連記事:情報漏洩を防ぐコンプライアンス対策 関連法律と罰則についても解説
副業を禁止するデメリット
副業を禁止することはメリットがある反面、いくつかのデメリットもあります。
3つのデメリットを解説します。
事業拡大の機会損失
副業を通じて得られる外部の知見や人脈は、企業にとって貴重な資源となり得ます。
副業を禁止することで、従業員が他業界で得た経験やネットワークを自社に還元する機会を失い、結果としてイノベーションや事業拡大のチャンスを逃す可能性があります。
関連記事:IPO準備時におけるM&Aのメリット・デメリット 実施時の注意点も解説
知識やスキル獲得の機会損失
副業は、従業員が本業では得られないスキルや経験を習得する機会でもあります。
特に、スタートアップや異業種での副業経験は、柔軟な思考や課題解決力を育む上で有効です。
副業を禁止することで、こうした成長機会を奪い、結果的に人材の成長スピードを鈍化させるリスクがあります。
昔気質な企業イメージの定着
副業を一律に禁止する企業は、柔軟性に欠ける「昔気質な企業」として見られる可能性があります。
特に若年層の求職者は、自由度の高い働き方を重視する傾向があり、副業禁止が採用競争力の低下につながることもあります。
企業ブランディングや人材確保の観点からも、副業に対するスタンスは慎重に検討すべきです。
関連記事:企業イメージをアップさせるコンプライアンス遵守を解説
副業を解禁した企業の事例

働き方改革の進展とともに、従業員の副業を認める企業が増えています。
ここでは、業種ごとに副業解禁の取り組み事例を紹介し、その背景や効果について考察します。
クラウドソーシングサービス運営会社
あるクラウドソーシングサービスを展開する企業では、2016年に副業禁止規定を撤廃し、いち早く副業を自由化しました。
従業員が自社プラットフォームを通じて副業を行うことも可能としています。
これは、ユーザー視点の理解を深めると同時に、サービス改善にもつながる取り組みです。
副業を通じて得た知見が本業に還元される好循環が生まれています。
また、同社は企業向けに「副業導入プログラム」も提供しており、自社の知見を外部にも展開するなど、副業推進のリーディングカンパニーとしての立場を確立しています。
関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説
大手製薬会社
製薬業界においても、副業を解禁する動きが見られます。
ある企業では「社外チャレンジ制度」として、従業員が社外での活動を通じて新たなスキルや視点を得ることを推奨しています。
副業制度は、勤続3年以上の正社員を対象に、申請・承認制で運用されており、現在までに延べ120名以上が副業を実践しています。
さらに、社内で複数の部署を兼務できる制度も整備されており、多様なキャリア形成を支援する体制が整っています。
この企業の副業制度は、単なる収入補完ではなく、「社会課題への挑戦」や「自己実現」を重視しており、制度設計にもその思想が色濃く反映されています。
副業を通じて得た知見を本業に還元する好循環が生まれている点が特徴です。
インターネット関連事業を行う企業
インターネット広告やメディア事業を展開する企業では、「事前申請で副業OK」という柔軟なルールを導入しています。
2015年に副業を解禁し、2019年には技術職向け社内副業制度を導入しました。
この制度は、エンジニアやクリエイターがグループ内の他部署・他社のプロジェクトに就業時間外で参画し、報酬を得られる仕組みです。
また、従業員の自律性を尊重し、社外での活動を通じて得た経験を本業に活かすことを期待しています。
また、社外副業も申請制で認められており、大学講師や起業、ライター活動など多様な働き方が実現されています。
副業を通じたスキルアップやキャリアの多軸化を積極的に支援するカルチャーが根付いている点が、この企業の大きな特徴です。
関連記事:人材管理の方法は?手順やメリット、データベースの作成方法を解説
まとめ
副業は原則として労働者の自由であり、企業が一律に禁止することは法的に難しい時代になっています。
ただし、業務への支障や企業秩序の維持といった合理的な理由がある場合には、一定の制限が認められます。
企業としては、就業規則の整備や副業申請のフロー構築、リスク管理体制の強化を通じて、柔軟かつ現実的な副業対応を進めることが求められます。
副業を「リスク」ではなく「成長機会」と捉える視点が、これからの人材戦略において重要な鍵となるでしょう。
関連記事:タレントマネジメントとは?基礎知識や導入方法、メリット、注意点をわかりやすく解説
関連記事:労働基準法における休憩時間の原則や注意点とは?違反時の罰則についても解説