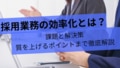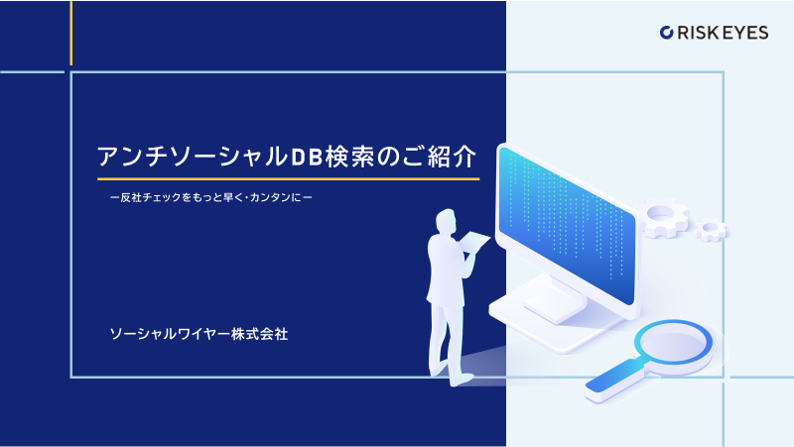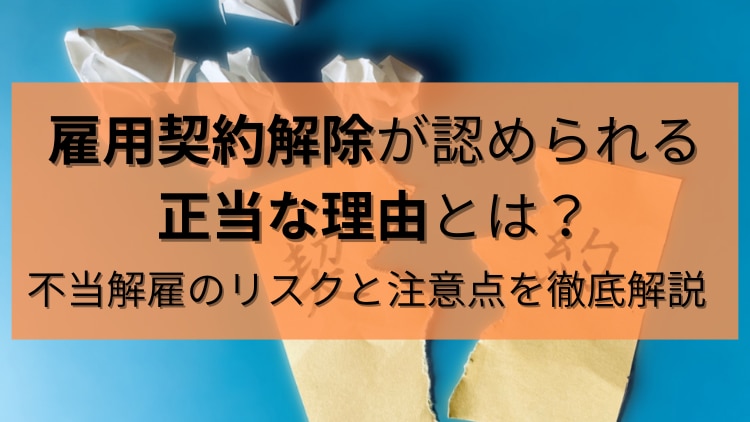
雇用契約解除が認められる正当な理由とは?不当解雇のリスクと注意点を徹底解説
企業が従業員との雇用契約を解除する際には、法的な正当性と慎重な手続きが求められます。
不当な解除は重大なリスクを伴い、企業の信頼や経営にも影響を及ぼしかねません。
この記事では、雇用契約解除の正当な理由、不当解雇のリスク、注意点、そして事前に行うべき反社チェックまで、実務に役立つポイントを網羅的に解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
注意すべき相手をすぐに発見できる反社リストを検索
目次[非表示]
- 1.雇用契約の解除とは
- 1.1.雇用契約を解除する3つのケース
- 1.1.1.企業から従業員を解雇するケース
- 1.1.2.従業員から解除を申し出るケース
- 1.1.3.企業と従業員の話し合いで解除するケース(合意解約)
- 1.2.雇止めとの違い
- 2.雇用契約解除が認められる正当な理由とは
- 3.雇用契約解除が不当と判断された場合のリスク
- 3.1.契約解除が無効になる
- 3.2.復職+バックペイの支払い
- 3.3.損害賠償の請求を受ける
- 3.4.他社員にも波及し、多額の金銭支払いが発生する
- 3.5.企業イメージが悪化する
- 4.雇用契約の解除に関して注意すべきポイント
- 4.1.有効となる理由を準備する
- 4.2.雇用契約を解除する理由を就業規則に明記しておく
- 4.3.30日以上前に解雇予告を行う
- 4.4.解雇予告手当を払う
- 4.5.法律に違反しないか確認する
- 5.雇用契約の解除を避けるために行うべき反社チェック
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【独自で収集した反社リストについてもっと知る】
雇用契約の解除とは

雇用契約の解除とは、企業と従業員の間で締結された雇用契約を終了させることを指します。
労働契約は、原則として双方の合意に基づいて継続されるものですが、一定の条件下では一方的な解除も認められています。
ただし、解除には法的な要件や手続きが伴い、誤った対応は労働トラブルに発展する可能性があるため、慎重な判断が求められます。
雇用契約を解除する3つのケース
雇用契約の解除には、大きく分けて以下の3つのケースがあります。
それぞれ詳しく解説します。
企業から従業員を解雇するケース
企業が従業員に対して一方的に雇用契約を終了させる「解雇」は、労働契約法第16条により「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。
懲戒解雇や普通解雇、整理解雇などの種類があり、それぞれに厳格な要件が定められています。
例えば、重大な規律違反や業務命令違反、経営上の必要性などが該当しますが、いずれも証拠や手続きの正当性が不可欠です。
関連記事:解雇するための条件とは?主な解雇理由や解雇後の注意点についてわかりやすく解説
従業員から解除を申し出るケース
従業員が自己都合で退職を申し出る場合は、民法第627条に基づき、原則として2週間前の通知で契約解除が可能です。
ただし、就業規則や雇用契約書に退職時期の定めがある場合は、その内容に従う必要があります。
企業側としては、業務の引き継ぎや人員補充の観点から、早期の申し出と円滑な退職手続きが望まれます。
企業と従業員の話し合いで解除するケース(合意解約)
企業と従業員が話し合いの上で契約解除に合意する「合意解約」は、最もトラブルが少ない方法です。
双方の納得のもとで退職が進められるため、後の紛争リスクも低くなります。
合意内容は退職合意書などの文書で明確にしておくことが重要で、退職日や退職金の有無、秘密保持義務などを明記することで、法的なトラブルを防ぐことができます。
雇止めとの違い
「雇止め」は、有期雇用契約の満了時に契約を更新せず終了することを指します。
一見すると自然な契約終了のように思えますが、過去に繰り返し契約更新が行われていた場合や、従業員が契約更新を期待していた場合には、実質的に「解雇」とみなされることがあります。
この場合、企業側には雇止めの合理的理由と説明責任が求められ、対応を誤ると不当解雇と判断されるリスクがあります。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
雇用契約解除が認められる正当な理由とは
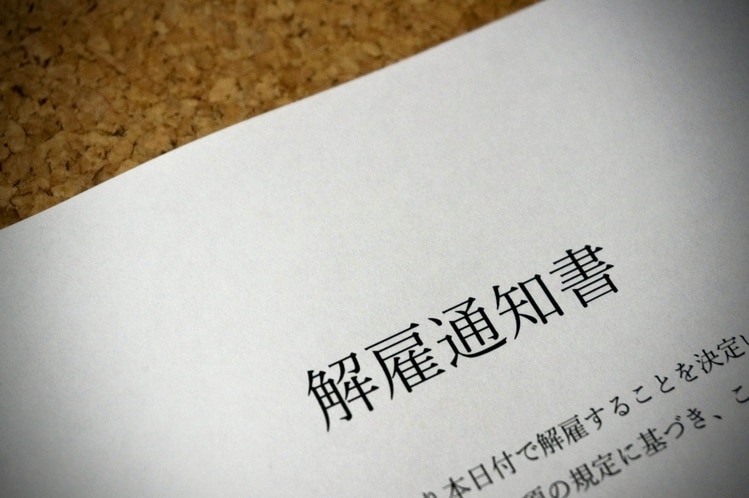
企業が従業員との雇用契約を解除するには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」が必要です。
これは労働契約法第16条に基づくもので、企業の一方的な判断だけでは正当性は認められません。
例えば、重大な規律違反や業務命令違反、長期の無断欠勤などは正当な理由とされる可能性がありますが、いずれも証拠と手続きの適正が求められます。
能力不足は「やむを得ない事由」になる?
能力不足のみを理由にした解雇は、原則として認められにくいのが実情です。
業務遂行に支障がある場合でも、企業側が教育・指導・配置転換などの改善措置を講じた上で、それでも改善が見込めないと判断される場合に限り、「やむを得ない事由」として認められる可能性があります。
つまり、能力不足を理由にするには、企業側の対応履歴と合理的な判断が不可欠です。
関連記事:雇用契約と業務委託契約の違いと見分け方を徹底解説!業務委託のメリットも解説
雇用契約解除が不当と判断された場合のリスク

企業が従業員との雇用契約を解除する際、法的な根拠と手続きの妥当性が欠けていると「不当解雇」と判断される可能性があります。
これは単なる人事上の手続きミスでは済まされず、企業にとって多方面にわたるリスクを引き起こします。
以下では、具体的な影響を5つの観点から整理します。
契約解除が無効になる
不当と認定された場合、解除そのものが法的に無効となり、従業員の雇用関係は継続しているとみなされます。
これは、企業が解雇したつもりでも、法的には「解雇していない」状態に戻されることを意味します。
結果として、従業員の地位回復や職場復帰が求められ、企業の人事計画に大きな修正が必要となります。
復職+バックペイの支払い
契約が無効とされた場合、従業員は復職する権利を持ち、企業はその間の未払い賃金(バックペイ)を支払う義務を負います。
これは単なる給与支払いにとどまらず、賞与や社会保険料の企業負担分なども含まれる可能性があります。
特に長期にわたる争議となった場合、金額は数百万円規模に膨らむこともあり、予期せぬ財務負担となります。
関連記事:雇用期間に関する法律上のルールとは?有期雇用契約のポイントや注意点を解説
損害賠償の請求を受ける
不当な契約解除によって従業員が精神的・経済的な損失を被った場合、損害賠償請求が発生することがあります。
これは、バックペイとは別に、慰謝料や逸失利益として請求されるもので、特に懲戒解雇など名誉に関わる処分を伴う場合は高額化する傾向があります。
裁判に発展すれば、訴訟費用や弁護士費用も企業負担となり、経営資源の消耗につながります。
他社員にも波及し、多額の金銭支払いが発生する
一件の不当解雇が社内に波及することで、過去に同様の処分を受けた従業員が再検討を求めるケースや、労働組合が介入する事態に発展することがあります。
これにより、複数の訴訟や労働審判が同時並行で発生し、企業は継続的かつ広範な金銭的負担を強いられる可能性があります。
人事制度全体の見直しを迫られることもあり、組織運営に深刻な影響を及ぼします。
企業イメージが悪化する
労働トラブルが外部に露見すると、企業の社会的信用やブランド価値が損なわれます。
特にSNSや口コミサイトでの情報拡散は迅速かつ広範囲に及び、採用活動や取引先との関係にも悪影響を与えかねません。
「労務管理が不適切な企業」として認識されることで、優秀な人材の獲得が困難になり、長期的な競争力低下につながるリスクもあります。
関連記事:企業イメージをアップさせるコンプライアンス遵守を解説
雇用契約の解除に関して注意すべきポイント

雇用契約の解除は、企業にとって人事上の重要な判断であり、慎重な対応が求められます。
解除の正当性が認められなければ、法的リスクや企業イメージの毀損につながる可能性もあります。
ここでは、雇用契約解除を検討する際に押さえておくべき5つの実務ポイントを解説します。
有効となる理由を準備する
契約解除には「客観的に合理的な理由」が必要です。
これは単なる業務上の不満や曖昧な評価では認められず、具体的な事実と証拠が求められます。
例えば、業務命令違反や重大な規律違反、長期の無断欠勤などが該当しますが、いずれも記録や面談履歴などの裏付けが不可欠です。
事前に改善指導を行い、その経過を文書化しておくことで、解除の正当性を補強できます。
雇用契約を解除する理由を就業規則に明記しておく
就業規則は、企業と従業員の間のルールブックです。
解雇事由を明確に記載し、従業員に周知しておくことで、解除の根拠を明文化できます。
例えば、「業務命令への著しい違反」「勤務態度の著しい不良」など、具体的な文言で定めておくことが重要です。
就業規則が曖昧な場合、解除の正当性が問われるリスクが高まります。
関連記事:今すぐ取り組むべき就業規則の見直し―押さえるべきチェック項目と変更手順を解説
30日以上前に解雇予告を行う
労働基準法では、解雇の30日前までに予告することが義務付けられています。
これは従業員が生活設計を立てるための猶予期間であり、企業側の誠実な対応が求められます。
予告なしに即時解雇を行う場合は、後述する「解雇予告手当」の支払いが必要となるため、原則として事前予告を行う方が望ましいです。
解雇予告手当を払う
30日前の予告ができない場合、企業は平均賃金の30日分に相当する「解雇予告手当」を支払う義務があります。
これは法定の最低保障であり、支払いを怠ると労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。
なお、懲戒解雇など一部の例外を除き、ほとんどのケースで予告または手当のいずれかが必要です。
法律に違反しないか確認する
雇用契約解除に関しては、労働契約法、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など、複数の法令が関係します。
例えば、育児休業中の解雇や、妊娠を理由とした契約解除は原則として違法です。
また、労働組合活動を理由とした解雇も、労働組合法に抵触する可能性があります。
解除を検討する際は、社労士や法務部門と連携し、法令違反がないか事前に確認することが不可欠です。
関連記事:日本の雇用問題とは?解決に向けた対策や知っておくべき統計データを解説
雇用契約の解除を避けるために行うべき反社チェック

反社チェックとは、「反社会的勢力」と関わりがない人物かどうかを調査することです。
企業が従業員との雇用契約を解除する際、反社会的勢力との関係が判明すれば契約解除は可能です。
しかし、実際には法的手続きや証拠収集に時間と労力がかかり、即時対応が難しいケースもあります。
だからこそ、採用前に反社チェックを徹底しておくことが、リスク回避の鍵となります。
反社チェックはすべての従業員に対して必要
反社チェックは、役職や職種に、雇用形態に関係なく、すべての従業員に対して実施すべきです。
特に営業職や外部との接点が多いポジションや役員は、企業の信用を守る観点からも重要です。
採用時だけでなく、定期的なチェックを行うことで、継続的なリスク管理が可能になります。
万が一、反社との関係が疑われる場合でも、早期発見により穏便な対応が可能となります。
関連記事:反社チェックの必要性とは?基礎知識や反社関与の判断基準を解説
反社チェックを効率化する反社チェックツール
近年では、反社チェックを効率化するツールが多数登場しています。
外部データベースと連携し、氏名・住所・企業名などを自動照合することで、人的ミスや見落としを防げます。
また、継続的なモニタリング機能を備えたサービスを導入すれば、在籍中のリスクもリアルタイムで把握できます。
法務部門や人事部門の負担を軽減しつつ、コンプライアンス体制の強化につながるため、導入を検討する価値は十分にあります。
事前の反社チェックは、雇用契約解除という最終手段を避けるための予防策です。
企業の健全性を守るためにも、制度化とツール活用を進めましょう。
関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説
まとめ
雇用契約の解除は、企業にとって重大な判断であり、法的な正当性と慎重な対応が求められます。
不当解雇によるリスクを回避するためには、事前の準備と社内体制の整備が不可欠です。
特に就業規則の整備、証拠の文書化、反社チェックの徹底など、実務的な対応を怠らないことが、企業の持続的な成長と信頼構築につながります。
関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説
関連記事:戦略人事とは?メリットや必要な機能、成功させるためのポイントを解説