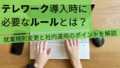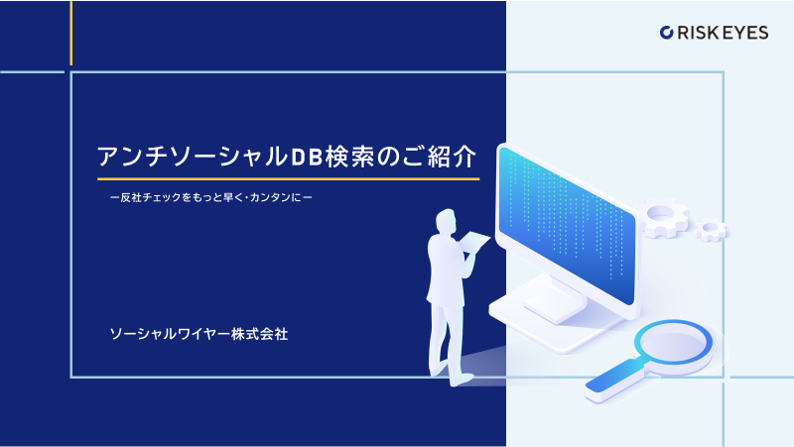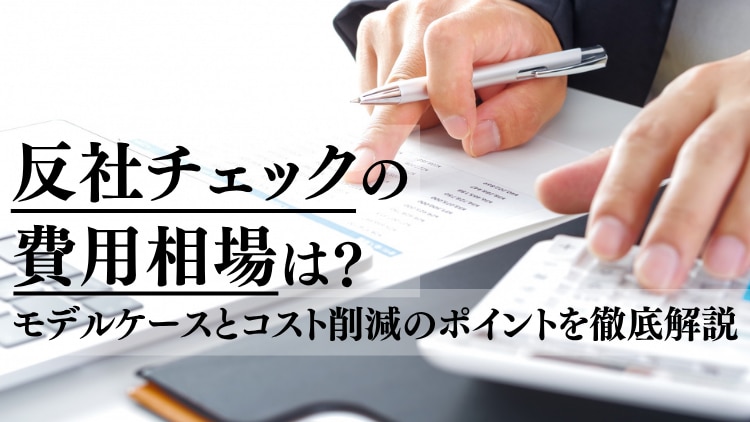
反社チェックの費用相場は?モデルケースとコスト削減のポイントを徹底解説
企業の信用と法的リスクを守るうえで、反社チェックは必須の業務です。
しかし、調査方法によって反社チェックの相場費用は大きく異なり、不要なコストをかけてしまうケースも少なくありません。
この記事では、反社チェックの費用相場やモデルケースを紹介し、効率的かつ低コストで運用するためのポイントを徹底解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
注意すべき相手をすぐに発見できる反社リストを検索
目次[非表示]
- 1.現代に欠かせない反社チェックとは
- 1.1.「反社」とは
- 2.費用をかけてでも反社チェックを行うべき理由
- 3.反社チェックの調査費用の相場
- 3.1.反社チェックツールを利用する場合
- 3.2.その他のデータベース検索を利用する場合
- 3.3.専門の調査会社に依頼する場合
- 3.4.専門機関や弁護士に相談・依頼する場合
- 3.5.自社でインターネットなどで検索する場合
- 4.反社チェックの費用のモデルケース5選
- 4.1.すべての調査対象者を調査会社に依頼
- 4.2.すべての調査対象者をデータベース検索サービスで調査
- 4.3.すべての調査対象者を反社チェックツールで検索
- 4.4.すべての調査対象者をインターネットなどで検索、危険性のある対象者のみ調査会に依頼
- 4.5.データベース検索を3割、残りの7割はインターネットなどで検索
- 5.反社チェック費用を安く抑える方法
- 5.1.従量課金制のプランを選ぶ
- 5.2.依頼する調査の件数を減らす
- 5.3.一部業務を自社で負担する
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【独自で収集した反社リストについてもっと知る】
現代に欠かせない反社チェックとは
 企業活動において、反社会的勢力との関係を遮断することは、法令遵守や信用維持の観点から極めて重要です。
企業活動において、反社会的勢力との関係を遮断することは、法令遵守や信用維持の観点から極めて重要です。
近年では、取引先や採用候補者が反社会的勢力と関わりがないかを調査する「反社チェック」が常識となっており、上場企業や金融機関だけでなく、中小企業においても対応が求められています。
反社勢力との関係が明るみに出れば、行政処分や契約解除、取引停止などのリスクが生じるだけでなく、企業ブランドの毀損にもつながります。
反社チェックは、単なるリスク回避策ではなく、健全な企業経営の基盤として位置づけられるべき取り組みです。
「反社」とは
「反社会的勢力(反社)」とは、暴力団、暴力団関係者、フロント企業、過激な活動を行う団体、違法行為を繰り返す個人など、社会秩序を脅かす存在を指します。
これらの勢力は、企業との取引を通じて資金を得たり、信用を悪用したりすることで、活動を拡大させる恐れがあります。
暴対法や各自治体の暴力団排除条例が施行されたことで、暴力団は排除が進みましたが、反社会的勢力は年々不透明化しています。
反社会的勢力との関係を持つことは、企業にとって重大なリスクであり、法的責任や社会的非難を招く可能性があります。
そのため、定義を正しく理解し、日常的にチェック体制を整えることが不可欠です。
関連記事:反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用は可能なのか?
費用をかけてでも反社チェックを行うべき理由
 企業が反社会的勢力と関係を持つことは、信用の失墜や行政処分、取引停止など重大なリスクを伴います。
企業が反社会的勢力と関係を持つことは、信用の失墜や行政処分、取引停止など重大なリスクを伴います。
反社チェックは、形式的な対応にとどまらず、コンプライアンス体制の根幹を支える重要な業務です。
特に近年では、取引先や採用候補者に対する事前確認が求められる場面が増えており、費用をかけてでも確実なチェック体制を整えることが、企業の持続的成長とリスク回避に直結します。
政府指針で企業の反社対応が要請されている
2007年に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」では、反社との関係遮断が企業の責任として明示されています。
契約書への暴排条項の導入や取引先の事前確認など、具体的な対応が求められており、特に金融機関や上場企業では反社チェックの有無が審査項目に含まれるケースもあります。
各自治体の暴力団排除条例で企業の義務が規定されている
全国の自治体で施行されている暴力団排除条例では、企業が暴力団関係者に利益供与することを禁止しています。
契約書への反社条項の記載や誓約書の取得が求められ、違反時には契約解除や指名停止などの制裁が科される可能性があります。
法令遵守の観点からも、反社チェックは不可欠です。
関連記事:暴力団排除条例で罰則の対象になる禁止事項とは?企業が対応すべきことについて解説
反社チェックの調査費用の相場
 反社会的勢力との関係遮断は、企業の信用維持と法令遵守に欠かせない取り組みです。
反社会的勢力との関係遮断は、企業の信用維持と法令遵守に欠かせない取り組みです。
しかし、反社チェックの方法によって費用は大きく異なります。
ここでは、代表的な調査手段ごとの費用相場と特徴を整理し、企業が自社に合った方法を選ぶための参考情報を提供します。
反社チェックツールを利用する場合
近年注目されているのが、AIやRPAを活用した反社チェックツールです。
これらは定額制または従量課金制で提供されており、月額3,000円〜15,000円程度、または1件あたり200〜300円が相場です。
大量の対象者を効率的にスクリーニングできるため、採用や取引先の数が多い企業に適しています。
導入初期には操作習得や社内フローの整備が必要ですが、長期的にはコストパフォーマンスに優れた選択肢です。
関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説
その他のデータベース検索を利用する場合
帝国データバンクや信用情報機関などの有料データベースを活用する方法も一般的です。
月額利用料は10,000円前後で、検索1件あたり100〜500円程度が目安です。
新聞記事、行政処分歴、企業情報などを網羅的に確認できるため、一定の信頼性を確保できます。
検索代行サービスを併用する場合は、別途手数料が発生しますが、社内の負担を軽減できるメリットがあります。
専門の調査会社に依頼する場合
精度を最重視する場合は、専門の調査会社への依頼が有効です。
個人調査は1件あたり30,000円〜、企業調査では100,000円以上が相場です。
対象者の交友関係、過去の報道、行政処分歴などを詳細に調査し、報告書として提供されるため、リスクの高い取引先や重要な採用候補者に対して活用されます。
ただし、費用が高額なため、件数が多い場合は予算面での調整が必要です。
関連記事:反社チェックの際に検索すべきキーワードとは?その他のチェック方法と注意点も紹介
専門機関や弁護士に相談・依頼する場合
反社チェックの結果を踏まえて契約書の整備や法的対応が必要な場合は、弁護士や専門機関への相談が必要です。
相談料は1回10,000円〜、顧問契約では月額30,000円〜50,000円程度が一般的です。
暴排条項の作成や契約解除対応など、法的リスクへの備えとして重要な役割を果たします。
特に反社との関係が疑われるケースでは、専門的な判断が不可欠です。
自社でインターネットなどで検索する場合
Google検索やSNS調査などを自社で行う方法は、調査自体に費用はかかりません。
しかし、調査漏れのリスクや情報の信頼性に限界があるほか、担当者の工数や人件費が発生します。
簡易的なスクリーニングには有効ですが、精度を求める場面では外部サービスとの併用が推奨されます。
社内での調査フローを整備することで、外注費を抑えつつ一定のリスク管理が可能です。
関連記事:反社チェックをGoogle検索で行う方法とは?調査範囲や進め方について解説
反社チェックの費用のモデルケース5選
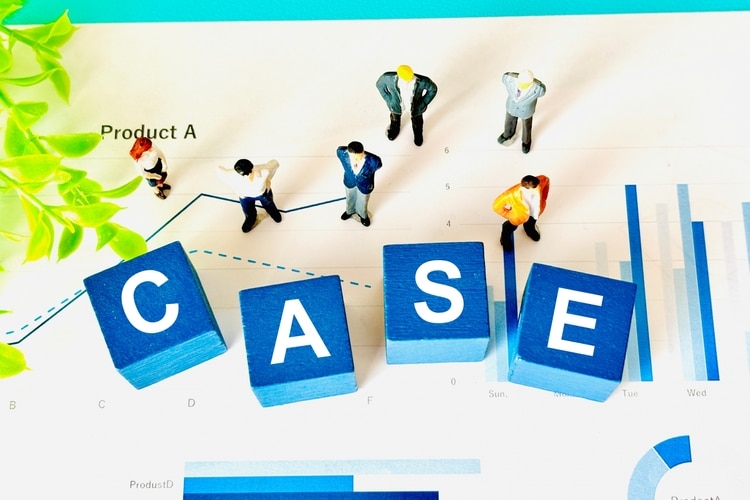 反社チェックの費用は、調査方法の選択によって大きく変動します。
反社チェックの費用は、調査方法の選択によって大きく変動します。
ここでは、毎月100件の調査を行うケースを想定し、代表的な5つのモデルを比較します。
自社のリスク許容度や予算に応じて、最適な運用方法を検討する参考にしてください。
すべての調査対象者を調査会社に依頼
最も精度が高く、信頼性のある方法ですが、費用は非常に高額です。
個人調査1件あたり3万円、企業調査では10万円以上が相場とされており、100件すべてを外部調査会社に依頼すると、月額で300万円〜1,000万円程度のコストが発生します。
金融機関や上場企業など、厳格なコンプライアンス体制が求められる場合に適しています。
ただし、費用負担が大きく、継続的な運用には課題となりやすい方法です。
すべての調査対象者をデータベース検索サービスで調査
帝国データバンクや信用情報機関などの有料データベースを活用する方法です。
1件あたり100〜500円程度の検索料がかかり、月額費用は10万〜50万円程度に収まります。
調査会社ほどの精度はないものの、一定の信頼性を確保できるため、コストと効率のバランスが取れた選択肢です。
検索代行を併用することで、社内負担の軽減も可能です。
すべての調査対象者を反社チェックツールで検索
AIやRPAを活用した反社チェックツールを導入することで、1件あたり200〜300円程度の従量課金で対応可能です。
月額では20万〜30万円程度が目安となり、データベース検索よりも安価かつ自動化による業務効率化が図れます。
初期導入や操作習得が必要ですが、継続的な運用には非常に適しています。
すべての調査対象者をインターネットなどで検索、危険性のある対象者のみ調査会に依頼
まず自社でGoogle検索やSNS調査を行い、リスクが高いと判断された対象者のみを外部調査会社に依頼する方法です。
調査会社への依頼件数を20件程度に絞れば、月額費用は60万〜80万円程度に抑えられます。
人的コストはかかりますが、精度とコストのバランスを取る実践的な運用モデルです。
データベース検索を3割、残りの7割はインターネットなどで検索
100件のうち30件を有料データベースで検索し、残り70件は自社でインターネット調査を行う方法です。
データベース検索にかかる費用は月額1万〜2万円程度、人的コストを含めても総額30万〜40万円程度に収まります。
中小企業やスタートアップにとって現実的かつ柔軟な選択肢であり、リスク管理とコスト削減を両立できます。
関連記事:反社チェックに日経テレコンは活用できるのか?メリット・デメリットを解説
反社チェック費用を安く抑える方法
 反社チェックは企業の信用維持や法令遵守に欠かせない業務ですが、継続的に実施するにはコスト面の工夫が必要です。
反社チェックは企業の信用維持や法令遵守に欠かせない業務ですが、継続的に実施するにはコスト面の工夫が必要です。
特に中小企業やスタートアップでは、限られた予算の中で効率的な運用を求められます。
ここでは、反社チェックの費用を抑えるための具体的な方法を3つ紹介します。
従量課金制のプランを選ぶ
反社チェックツールやデータベースサービスには、月額定額制と従量課金制のプランがあります。
定額制は件数が多い場合に有利ですが、調査件数が変動する企業にとっては、使った分だけ支払う従量課金制の方が無駄がなく、コストを抑えやすい傾向があります。
特に繁閑の差がある業種では、柔軟な課金体系を選ぶことで、年間の支出を大幅に削減できます。
関連記事:反社チェックに引っかかるケースとは?チェックが必要な理由と対策を解説
依頼する調査の件数を減らす
すべての対象者に対して外部調査を依頼するのではなく、リスクの高い対象者に絞って依頼することで、費用を抑えることが可能です。
たとえば、一次スクリーニングを自社で行い、過去に行政処分歴がある、SNS上で問題行動が確認されたなどの対象者のみを調査会社に回すことで、件数を大幅に削減できます。
リスクベースの選定は、コストと精度のバランスを取る上で有効です。
一部業務を自社で負担する
Google検索やSNS調査など、初期段階の情報収集は自社でも対応可能です。
調査漏れのリスクはあるものの、基本的な情報確認を社内で行い、専門的な判断が必要な場合のみ外部に委託することで、外注費を抑えられます。
社内に簡易チェックのフローを構築することで、業務効率化とコスト削減の両立が可能になります。
関連記事:反社チェックに関するルールはある?チェックのタイミングや社内の対応手順も解説
まとめ
反社チェックは企業の信用と法的リスクを守るために不可欠な業務です。
費用は手法によって大きく異なりますが、ツールの活用や調査対象の絞り込みによって、コストを大幅に削減することが可能です。
自社の規模やリスク許容度に応じて、最適なチェック体制を構築しましょう。
関連記事:反社チェックを行うべき頻度は?定期的なチェックが大切な理由
関連記事:反社会的勢力の実名リストはある?指定暴力団や関係企業の確認方法