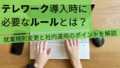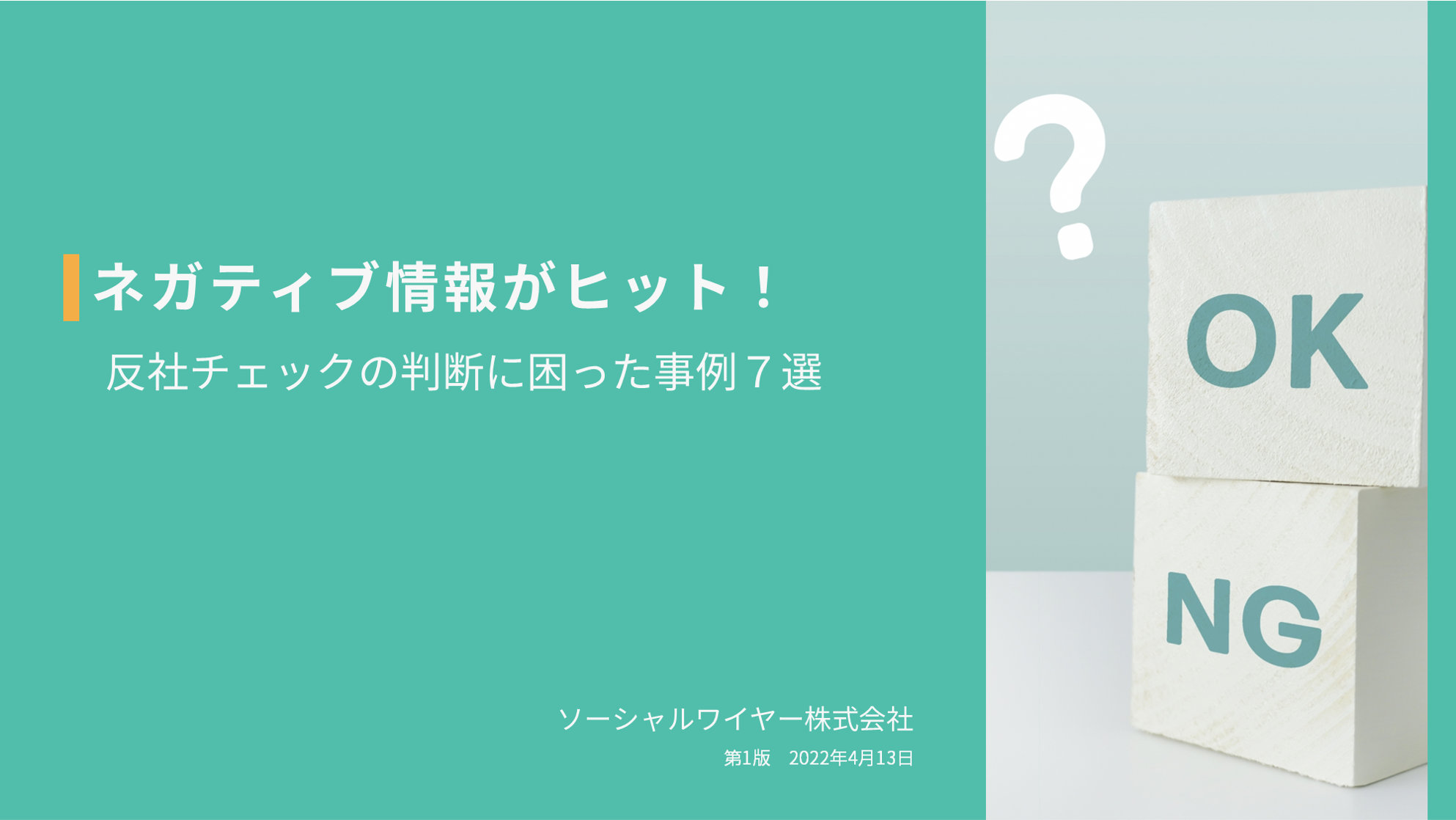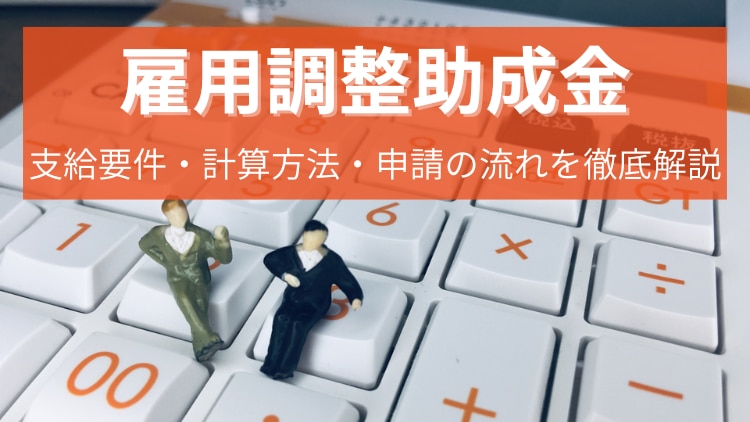
【2026年最新版】雇用調整助成金とは?支給要件・計算方法・申請の流れを徹底解説
企業が従業員の雇用を守るために活用できる「雇用調整助成金」。
2026年の最新制度改正や特例措置により、申請要件や計算方法にも重要な変更が加えられています。
この記事では、制度の概要から申請の流れ、注意点までをわかりやすく解説。
申請ミスを防ぎ、確実に助成を受けるためのポイントを押さえましょう。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【実務担当者】反社チェックの契約可否の判断に迷った事例
目次[非表示]
- 1.雇用調整助成金とは
- 2.雇用調整助成金の支給要件
- 2.1.対象事業主
- 2.1.1.不支給となる事業主の要件
- 2.2.対象期間、日数
- 2.3.支給対象となる休業、教育訓練、出向
- 3.雇用調整助成金の受給額と計算方法
- 3.1.基本の受給額・加算額
- 3.1.1.令和6年4月からの変更点
- 3.1.2.令和7年1月からの変更点
- 3.2.残業相殺
- 3.3.併給調整
- 4.雇用調整助成金の申請の流れ
- 4.1.雇用調整の計画作成
- 4.2.計画届を労働局に提出
- 4.3.休業・教育訓練・出向の実施
- 4.4.助成金の支給申請
- 4.5.労働局による審査→支給決定
- 4.6.指定口座への振り込み
- 5.雇用調整助成金を申請する際の注意点
- 5.1.「変更届」なしの変更は支給対象外
- 5.2.休業日の自主出社も支給対象外
- 5.3.申請期限を1日でも過ぎたら申請不可
- 5.4.申請には最新の要件や書類を要確認
- 5.5.悪質業者によるトラブルに注意
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの事例を学ぶ】
雇用調整助成金とは
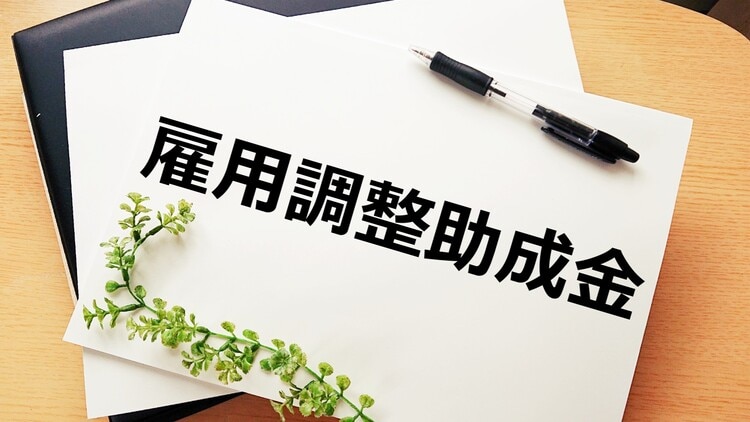 雇用調整助成金とは、景気の変動や自然災害などにより事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、従業員の雇用維持を図るために実施する「休業」「教育訓練」「出向」にかかる費用の一部を国が助成する制度です。
雇用調整助成金とは、景気の変動や自然災害などにより事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、従業員の雇用維持を図るために実施する「休業」「教育訓練」「出向」にかかる費用の一部を国が助成する制度です。
雇用保険の適用事業所であることが前提で、一定の要件を満たすことで申請が可能です。
2026年現在、能登半島地震や豪雨災害に伴う特例措置も導入されており、地域や状況に応じた柔軟な支援が行われています。
関連記事:【2026年最新版】トライアル雇用の条件とは?対象者・事業主・助成金をわかりやすく解説
雇用調整助成金の支給要件
 雇用調整助成金を活用するには、事業主が一定の支給要件を満たしている必要があります。
雇用調整助成金を活用するには、事業主が一定の支給要件を満たしている必要があります。
制度の趣旨は、経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、従業員の雇用を維持するために行う「休業」「教育訓練」「出向」に対して、国が助成を行うというものです。
2026年現在、制度改正や特例措置が加わり、より柔軟な運用が可能となっています。
対象事業主
雇用調整助成金の対象となるのは、以下の条件を満たす事業主です。
- 雇用保険の適用事業所であること
- 売上高、生産量、受注量などの事業活動指標が、前年同月比で10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者に対して、計画的に休業・教育訓練・出向を実施していること
- 労使間で協定を締結し、計画届を事前に労働局へ提出していること
これらの要件を満たすことで、助成金の申請が可能となります。
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説
不支給となる事業主の要件
一方で、以下のようなケースでは助成金の支給対象外となるため注意が必要です。
- 助成対象となる休業等を実施していないに申請した場合(不正受給)
- 休業計画を変更したにもかかわらず、変更届を提出していない場合
- 休業日に従業員が自主的に出社し、業務を行った場合
- 雇用保険未加入の事業所や、対象者が雇用保険被保険者でない場合
制度の信頼性を守るため、厚生労働省は不正受給に対して厳しい対応を取っています。
対象期間、日数
助成金の対象となる期間は原則として1年間以内と定められており、その間に実施される休業、教育訓練、出向が支給対象となります。
休業および教育訓練については、対象労働者1人につき年間最大100日までが助成対象となります。
出向については、出向期間中に限り助成が認められ、原則として3か月以上1年以内の期間が対象です。
なお、災害等による特例措置が適用される場合には、これらの上限が緩和されることがあります。
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?必須項目や2024年法改正に伴う変更点について解説
支給対象となる休業、教育訓練、出向
雇用調整助成金の支給対象となる措置は、「休業」「教育訓練」「出向」の3つに分類されます。
それぞれに細かな要件が定められており、計画的かつ適正な実施が求められます。
休業
休業は、所定労働日における全日休業が原則となります。
労使協定に基づいて、対象者や日数、実施方法などを明記したうえで実施する必要があります。
短時間休業などの部分休業も条件によっては認められますが、助成率や支給額が異なる場合があるため、事前の確認が重要です。
休業の実施状況は、出勤簿や賃金台帳などの記録によって確認されるため、書類の整備が不可欠です。
教育訓練
教育訓練は、従業員の職業能力の向上を目的とした研修や講座などが対象となります。
たとえば、業務に関連するスキル研修や資格取得支援などが該当します。
訓練時間は原則として1日4時間以上とされており、受講者本人による訓練報告書の提出が必要です。
教育訓練を実施することで、通常の助成額に加えて「教育訓練加算」が適用される場合もあり、積極的な活用が推奨されます。
出向
出向は、雇用維持と人材活用の両立を図る手段として注目されています。
助成対象となるには、出向元と出向先の事業所間で契約が締結されていることが前提です。
出向期間は原則として3か月以上1年以内であり、出向先での労働条件が適正であることが求められます。
賃金水準や労働時間などが適切に設定されているかどうかが審査のポイントとなります。
なお、災害等による特例措置が適用される場合には、出向に関する要件が緩和されることもあります。
関連記事:雇用期間に関する法律上のルールとは?有期雇用契約のポイントや注意点を解説
雇用調整助成金の受給額と計算方法
 雇用調整助成金の受給額は、事業主が従業員に支払った休業手当や教育訓練費、出向にかかる賃金の一部を国が助成する仕組みで、支給率や上限額は制度改正により随時見直されています。
雇用調整助成金の受給額は、事業主が従業員に支払った休業手当や教育訓練費、出向にかかる賃金の一部を国が助成する仕組みで、支給率や上限額は制度改正により随時見直されています。
2026年現在、基本的な助成額に加え、特定の条件を満たすことで加算措置が適用されるケースもあり、正確な理解が不可欠です。
基本の受給額・加算額
助成額は、対象となる賃金総額に対して一定の助成率を乗じて算出されます。
中小企業の場合、通常の助成率は4分の3(75%)、大企業は3分の2(66%)が目安とされています。
ただし、教育訓練を実施した場合には、1人1日あたり最大2,400円の加算が認められるなど、条件によって支給額が増えることがあります。
また、1人1日あたりの助成上限額は、令和6年4月時点で8,870円に設定されています。
令和6年4月からの変更点
令和6年4月の制度改正では、申請書類の様式が見直され、提出書類の簡素化が進められました。
これにより、事業主の事務負担が軽減される一方で、助成額の算定方法にも一部変更が加えられています。
特に教育訓練加算については、訓練内容の明確化と報告書の提出義務が強化され、実施の実効性が重視されるようになりました。
関連記事:雇用保険料とは?計算方法や覚えておくべきポイントを解説
令和7年1月からの変更点
令和7年1月からは、能登半島地震および豪雨災害の影響を受けた地域の事業主に対して、新たな特例措置が導入されました。
具体的には、助成率の引き上げ(最大100%)、支給日数の延長、出向に関する要件の緩和などが盛り込まれており、被災地域の雇用維持を強力に支援する内容となっています。
これらの特例は、対象地域や期間が限定されているため、該当する事業主は厚生労働省の公式情報を随時確認することが重要です。
残業相殺
助成対象となる休業日に従業員が残業を行った場合、その分は助成対象日数から相殺される仕組みとなっています。
たとえば、休業日として申請した日に一部の従業員が業務に従事した場合、その時間分は助成額から差し引かれるため、実施状況の管理と記録の正確性が求められます。
残業の有無は出勤簿や業務記録によって確認されるため、申請前に内容を精査することが不可欠です。
併給調整
雇用調整助成金は、他の助成制度との併給が原則として認められていません。
たとえば、キャリアアップ助成金や業務改善助成金など、同一の対象者や期間に対して複数の助成金を申請する場合は、調整が必要となります。
併給が認められるケースでも、助成額の一部が減額されることがあるため、事前に制度の重複を確認し、適切な助成金を選択することが重要です。
関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説
雇用調整助成金の申請の流れ
 雇用調整助成金を適切に活用するためには、制度の趣旨を理解したうえで、計画的かつ正確な申請手続きを踏むことが重要です。
雇用調整助成金を適切に活用するためには、制度の趣旨を理解したうえで、計画的かつ正確な申請手続きを踏むことが重要です。
ここでは、申請の流れを6つのステップに分けて解説します。
雇用調整の計画作成
まず初めに行うべきは、雇用調整の具体的な計画を作成することです。
休業、教育訓練、出向のいずれを実施するかを明確にし、対象となる従業員、実施期間、日数、方法などを整理します。
この段階では、労使間での協議が不可欠であり、労働者代表との合意を得たうえで「労使協定書」を作成する必要があります。
計画の内容は、後の申請や審査に直結するため、曖昧な点がないよう慎重に設計しましょう。
計画届を労働局に提出
計画が整ったら、次に「計画届」を所轄の労働局へ提出します。
この届出は、休業等の実施前に行う必要があり、事後申請は原則として認められていません。
提出書類には、労使協定書、対象者一覧、事業活動の縮小を示す資料(売上減少など)などが含まれます。
なお、計画内容に変更が生じた場合は、速やかに「変更届」を提出することが求められます。
届出がないまま変更を行った場合、助成対象外となる可能性があるため注意が必要です。
関連記事:雇用契約と業務委託契約の違いと見分け方を徹底解説!業務委託のメリットも解説
休業・教育訓練・出向の実施
計画届の受理後、実際に休業や教育訓練、出向を実施します。
この期間中は、対象従業員の出勤簿や賃金台帳、訓練記録などを正確に管理し、後の申請に備えて証拠書類を整えておくことが重要です。
教育訓練の場合は、訓練内容や時間、受講者の報告書なども必要となります。
出向については、出向契約書や出向先での勤務状況の記録が求められます。
実施状況が不明確な場合、助成金の支給が認められないこともあるため、記録の整備は徹底しましょう。
助成金の支給申請
実施が完了したら、助成金の支給申請を行います。
申請は、対象期間終了後2か月以内に行う必要があり、期限を過ぎると申請そのものが受理されません。
提出書類には、実施記録、賃金台帳、出勤簿、教育訓練報告書、出向契約書などが含まれます。
書類の不備や記載漏れがあると、審査に時間がかかるだけでなく、差戻しや不支給となる可能性もあるため、事前にチェックリストを活用して確認することが推奨されます。
関連記事:直接雇用のメリットとは?間接雇用との比較や3年ルール、企業の義務についても解説
労働局による審査→支給決定
申請書類が提出されると、労働局による審査が行われます。
審査では、提出された書類の整合性や実施状況の妥当性が確認され、必要に応じて実地調査が行われることもあります。
審査の結果、助成金の支給が認められると「支給決定通知書」が発行され、事業主に通知されます。
不備があった場合は、追加資料の提出や再申請が求められることもあるため、対応には迅速さが求められます。
指定口座への振り込み
支給決定後、指定した金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
振込までの期間は、審査状況や申請件数によって異なりますが、通常は支給決定から1〜2か月程度が目安です。
振込後は、会計処理や社内報告を行い、助成金の活用状況を社内で明確にしておくことが望まれます。
関連記事:日本の雇用問題とは?解決に向けた対策や知っておくべき統計データを解説
雇用調整助成金を申請する際の注意点
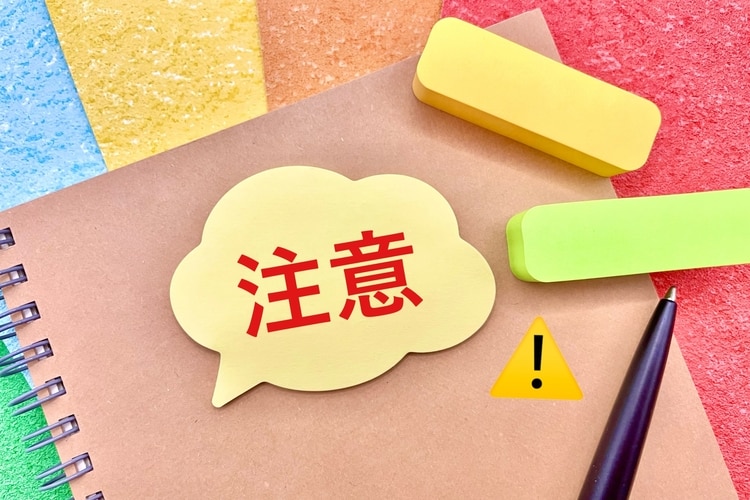 雇用調整助成金は、制度の趣旨に沿って正しく申請すれば、企業の雇用維持に大きく貢献する有効な支援策です。
雇用調整助成金は、制度の趣旨に沿って正しく申請すれば、企業の雇用維持に大きく貢献する有効な支援策です。
しかし、申請手続きには細かなルールがあり、些細なミスでも支給対象外となる可能性があります。
ここでは、申請時に特に注意すべきポイントを整理しておきましょう。
「変更届」なしの変更は支給対象外
計画届を提出した後に、休業日や対象者、実施方法などに変更が生じた場合は、必ず「変更届」を労働局に提出する必要があります。
変更届を出さずに計画を変更した場合、その変更分は助成対象外となり、最悪の場合は全体が不支給となることもあります。
計画の柔軟な運用は可能ですが、事前の手続きが絶対条件です。
休業日の自主出社も支給対象外
休業日として申請した日に、従業員が自主的に出社して業務を行った場合、その日は休業と認められず、助成対象から除外されます。
たとえ本人の意思による出社であっても、業務が発生していれば制度上の「休業」とはみなされません。
出勤簿や業務記録の整備を徹底し、休業日の管理を厳密に行うことが求められます。
関連記事:企業の義務である障害者雇用 2024年改正「障害者雇用促進法」について詳しく解説
申請期限を1日でも過ぎたら申請不可
雇用調整助成金の支給申請は、対象期間終了後2か月以内と定められており、期限を1日でも過ぎると申請は受理されません。
期限厳守は制度運用の基本であり、遅延申請は一切認められないため、申請スケジュールは余裕を持って組み立てる必要があります。
特に複数回に分けて申請する場合は、各回の締切を正確に把握しておきましょう。
申請には最新の要件や書類を要確認
制度は年度ごとに改正されることが多く、申請要件や必要書類も変更される可能性があります。
古い情報をもとに申請を進めると、書類不備や要件未達によって不支給となるリスクが高まります。
申請前には必ず厚生労働省の公式サイトや労働局の最新情報を確認し、最新版の様式や記載例を活用することが重要です。
悪質業者によるトラブルに注意
近年、助成金申請代行を謳う業者の中には、不正受給を誘導したり、高額な手数料を請求するなどの悪質なケースも報告されています。
厚生労働省も注意喚起を行っており、申請は信頼できる社労士や専門機関に相談することが推奨されます。
また、偽サイトや詐欺的な勧誘にも十分注意し、公式情報以外のリンクにはアクセスしないようにしましょう。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
まとめ
雇用調整助成金は、企業が厳しい経済環境下でも従業員の雇用を守るための重要な制度です。
2026年現在、制度の改正や特例措置が多く導入されており、申請には正確な情報と計画的な対応が求められます。
申請を検討している事業主の方は、厚生労働省の公式情報を確認し、適切な手続きを踏むことで、制度の恩恵を最大限に活用しましょう。
なお、雇用調整助成金は毎年の制度改正や特例措置によって随時内容が見直されるため、申請前には必ず厚生労働省の最新情報を確認することをおすすめします。
不安がある場合は社会保険労務士など専門家に相談することをおすすめします。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説
関連記事:外国人雇用の8つの注意点とは?メリットや必要な手続きも解説