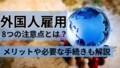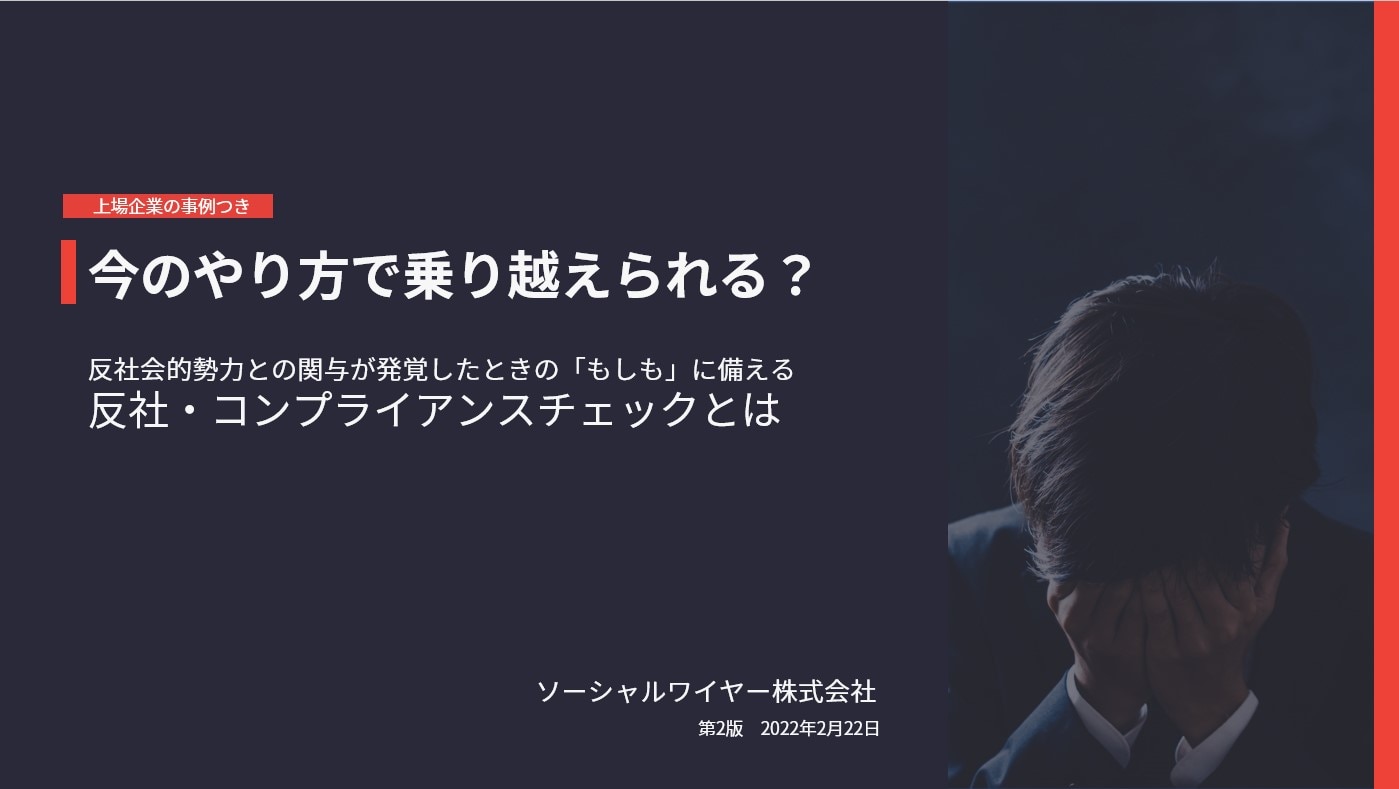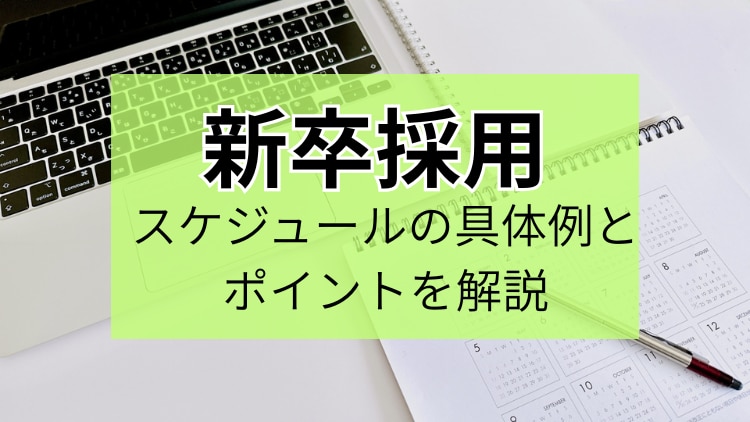
2025年最新!新卒採用のスケジュールの具体例とポイントを解説
新卒採用を成功に導くには、最新のスケジュールを正しく理解し、戦略的に対応することが不可欠です。
この記事では、2025年版の新卒採用スケジュールの具体例を示しながら、採用活動の効率化と学生との適切な接点づくりに役立つポイントを詳しく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【初心者必見】反社チェックのやり方・業務フローまとめ
目次[非表示]
- 1.日本の新卒採用におけるルールの変遷
- 1.1.新卒採用の日程に関するルールの変遷
- 1.1.1.就職協定以前
- 1.1.2.就職協定(1953年~1997年)
- 1.1.3.倫理憲章(1997年~2016年)
- 1.1.4.採用選考に関する指針(2016年~2021年)
- 1.2.現在は政府主導のルール
- 1.3.度重なる就活ルール変更の背景
- 2.2027年卒採用の基本的なスケジュールの具体例
- 2.1.2025年6月~9月
- 2.2.2025年10月~12月
- 2.3.2026年1月~2月
- 2.4.2026年3月~5月
- 2.5.2026年6月~9月
- 2.6.2026年10月~2027年2月
- 3.新卒採用スケジュールを決定する際のポイント
- 3.1.自社の採用ニーズと目標人数の設定
- 3.2.インターンシップ計画・早期イベントの準備
- 3.3.オンライン選考の整備
- 3.4.採用競合企業の動向と差別化戦略
- 3.5.ターゲット学生層の就活スケジュールとの整合性
- 3.6.社内リソースと採用体制の整備
- 4.2027年卒の採用を成功させるポイント
- 4.1.インターンシップなどを活用した早期からの接触
- 4.2.広報・ブランディング活動の前倒し
- 4.3.選考プロセスの明確化と短期化
- 4.4.ダイレクトリクルーティングを用いた採用活動
- 5.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの基本を学ぶ】
日本の新卒採用におけるルールの変遷

日本の新卒採用は、戦後から現在に至るまで幾度となくルールが見直されてきました。
企業と学生の間で最適な採用時期を模索する中で、協定や指針が生まれ、廃止され、そして政府主導へと移行してきた歴史があります。
ここではその変遷を振り返りながら、現在のルールとその背景について整理します。
新卒採用の日程に関するルールの変遷
企業と大学との関係性、そして学生の学業とのバランスを保つために、採用活動の日程に関するルールは大きく変遷してきました。
以下に、その代表的な制度について整理します。
就職協定以前
戦前から戦後にかけての時代、日本の新卒採用は明確なルールが存在せず、企業ごとに採用時期や方法が異なっていました。
特に1920年代から1930年代にかけては、大学卒業後に採用選考を行う「卒業後選考」が主流でしたが、企業の人材確保競争が激化するにつれ、卒業前の早期選考が増加。
これにより学業への影響が懸念されるようになり、ルール整備の必要性が高まりました。
関連記事:採用戦略とは?進め方やメリット、ポイントをわかりやすく解説
就職協定(1953年~1997年)
1953年、文部省と経済団体が中心となり「就職協定」が制定されました。
これは、大学4年生の10月以降に企業訪問を開始し、11月以降に選考を行うというスケジュールを定めたもので、学業への配慮を目的としていました。
しかし、高度経済成長期に入り、企業の採用意欲が高まると「青田買い」が横行。
協定は形骸化し、何度も改定されながらも、1997年には正式に廃止されました。
倫理憲章(1997年~2016年)
就職協定の廃止後、日本経団連は「倫理憲章」を策定。
これは企業に対して、採用選考の早期開始を自粛し、大学の学事日程を尊重するよう求めるものでした。
2003年には「卒業年度の4月以前に選考活動を行わない」と明文化され、企業の署名による共同宣言も行われました。
しかし、広報活動の前倒しや水面下での選考が続き、実効性には限界がありました。
関連記事:採用担当者必見!中途採用の成功事例と成功させるポイントを徹底解説
採用選考に関する指針(2016年~2021年)
2013年、政府は学生の学業への影響を懸念し、就活時期の繰り下げを要請。
これを受けて経団連は「採用選考に関する指針」を発表し、2016年卒から広報開始を3月1日、選考開始を8月1日に変更しました。
しかし、企業や学生の混乱を招き、翌年には選考開始が再び6月1日に前倒しされました。
指針はルールとして一定の効果を持ちましたが、遵守しない企業も多く、再び形骸化が問題視されるようになります。
現在は政府主導のルール
2018年、経団連は「指針の策定を今後行わない」と発表。
これにより、2021年卒以降の新卒採用ルールは政府主導へと移行しました。
現在は、内閣官房を中心とした関係省庁が「就職・採用活動に関する要請」を発出し、企業に対して広報開始を3月1日、選考開始を6月1日、内定解禁を10月1日とするスケジュールを求めています。
これはあくまで「要請」であり、法的拘束力はありませんが、企業の採用活動に一定の指針を与えています。
度重なる就活ルール変更の背景
就活ルールが度々変更されてきた背景には、学生の学業への影響、企業の人材確保競争、そして採用活動の早期化による混乱があります。
特に売り手市場となると、企業は優秀な学生を囲い込むために選考を前倒ししがちで、これがルールの形骸化を招いてきました。
また、インターンシップの活用や通年採用の広がりにより、従来の一括採用スケジュールが揺らぎつつあります。
政府主導のルールは、こうした混乱を抑えるための暫定的な枠組みであり、今後も柔軟な対応が求められるでしょう。
関連記事:採用とは?種類や業務フロー、成功させるポイントを解説
2027年卒採用の基本的なスケジュールの具体例
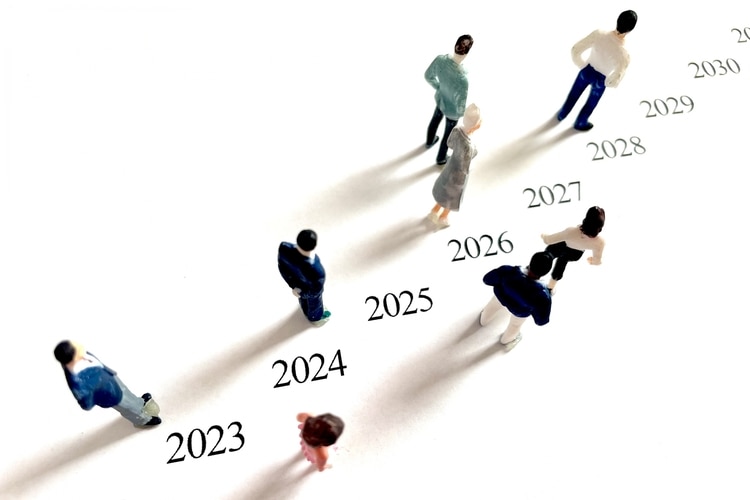
2027年卒の新卒採用活動は、前年から始まり約1年半にわたって展開されます。
採用活動の早期化が進む中、企業は計画的かつ柔軟なスケジュール設計が求められます。
年間のスケジュールを表にまとめると以下のようになります。

以下では、2025年6月から2027年2月までの代表的な流れを具体的に紹介します。
2025年6月~9月
この時期は、学生との初接点となる「夏インターンシップ」の準備・実施期間です。
5日以上の就業体験型プログラムが主流となり、学生の業界理解や職場体験を促す内容が求められます。
企業は広報設計や人材要件の見直しを行い、魅力的なプログラムを企画することが重要です。
2025年10月~12月
後期授業が始まる学生に配慮しつつ、企業は短期型のオープン・カンパニーや1day仕事体験を通じて接点を継続します。
夏インターン参加者のフォローと、新規母集団形成の両軸で施策を展開するのが理想です。
平日夜や土日の開催が効果的です。
関連記事:採用のミスマッチを防ぐリファレンスチェックとは?メリット・デメリットについて解説
2026年1月~2月
学生は学業中心の生活に移行するため、企業は接触タイミングに配慮が必要です。
録画型セミナーやオンラインコンテンツを活用し、学生の関心を維持しましょう。
同時に、面接官の選定やトレーニングなど、選考体制の準備も進める時期です。
2026年3月~5月
3月1日から採用広報が解禁され、企業は説明会やエントリー受付を本格化させます。
学生は志望企業の絞り込みやエントリーシート提出に追われるため、企業は告知の抜け漏れ防止や対象別コンテンツ設計が求められます。
関連記事:採用広告の種類とそれぞれのメリット、効果的に活用する方法を解説
2026年6月~9月
6月1日から選考活動が解禁され、面接やグループディスカッションが本格化します。
並行して28年卒向けインターンシップも始まり、採用担当者の繁忙期となります。
内定辞退対策として、職場見学や座談会などの施策が有効です。
2026年10月~2027年2月
10月には内定式を実施し、入社までのオンボーディング期間に入ります。
学生は社会人になる不安を抱えやすいため、同期交流や先輩社員との接点を設けることで安心感を醸成しましょう。
同時に、採用活動の振り返りと改善も行うべき時期です。
関連記事:採用プロセスとは?設計するメリットや一般的な流れ、ポイントをわかりやすく解説
新卒採用スケジュールを決定する際のポイント

新卒採用は企業の将来を左右する重要な活動です。
限られた期間で優秀な人材を確保するためには、戦略的なスケジュール設計が不可欠です。
以下では、採用スケジュールを決定する際に押さえておきたい6つのポイントを解説します。
自社の採用ニーズと目標人数の設定
まずは採用の目的を明確にすることが出発点です。
どの部署に、どのようなスキルや志向性を持った人材が何名必要なのかを具体化しましょう。
採用人数の設定は、事業計画や人員構成の変化を踏まえて柔軟に見直すことが重要です。
採用基準が曖昧なままでは、スケジュール全体が形骸化する恐れがあります。
インターンシップ計画・早期イベントの準備
近年は「採用直結型インターンシップ」の活用が進み、早期接点の重要性が高まっています。
夏季・秋季インターンの企画は、学生の志望度を高める絶好の機会です。
インターン後のフォローや早期選考への導線も含めて、年間計画に組み込むことで母集団形成の質を向上させられます。
関連記事:採用基準の決め方とは?ポイントや各選考段階での活用法について解説
オンライン選考の整備
オンライン面接や説明会は、地理的制約を超えて学生との接点を広げる手段です。
特に地方学生や理系学生との接触機会を増やすには、オンライン選考の導入が効果的です。
通信環境や面接官の対応力など、オンラインならではの課題もあるため、事前のシミュレーションとマニュアル整備が求められます。
採用競合企業の動向と差別化戦略
競合他社の採用スケジュールや広報手法を把握することで、自社の立ち位置を明確にできます。
選考時期の重複を避けたり、インターンや説明会の内容で差別化を図ることが、優秀層の囲い込みにつながります。
特に同業界の大手企業と比較される場合は、企業文化や成長機会など独自の魅力を打ち出すことが重要です。
関連記事:採用コストの相場はどのくらい?中途・新卒採用の平均コストや計算方法、コスト削減のポイントを解説
ターゲット学生層の就活スケジュールとの整合性
学生の動きは年々早期化しています。
大学3年の夏にはインターン参加、秋には志望業界の絞り込みが始まる傾向があります。
体育会系や公務員志望層など、特定層の動向も考慮しながら、接点のタイミングを調整しましょう。
大学の学事暦や試験期間も確認し、イベント日程が重ならないよう配慮することが大切です。
社内リソースと採用体制の整備
採用活動は人事部門だけでなく、現場社員や経営層の協力が不可欠です。
面接官の確保、評価基準の統一、フィードバック体制の整備など、社内体制を事前に整えておくことで、スケジュール通りの運用が可能になります。
特に中小企業では、リソース不足が採用活動の遅れにつながるため、外部支援の活用も視野に入れるとよいでしょう。
関連記事:採用管理システム(ATS)とは?基本機能や導入するメリット、選定のポイントを解説
2027年卒の採用を成功させるポイント
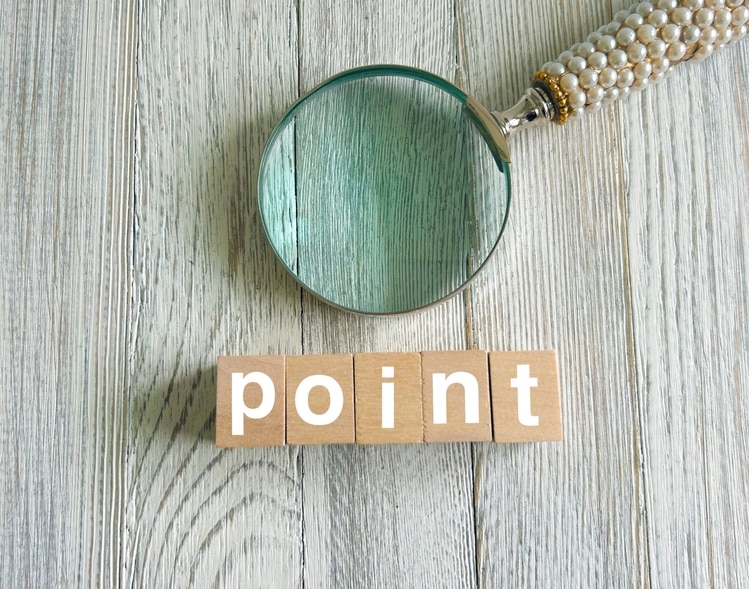
2027年卒の新卒採用市場は、これまで以上に早期化・多様化が進んでいます。
企業が優秀な学生と出会い、採用につなげるためには、従来の手法に加え、戦略的な設計が不可欠です。
ここでは、採用成功に向けた4つの重要ポイントを紹介します。
インターンシップなどを活用した早期からの接触
学生の就職活動は大学3年の夏から本格化しており、インターンシップは単なる体験ではなく、選考の入り口として機能しています。
特に5日以上の就業体験を含む「タイプ3・タイプ4」のインターンは、採用活動への情報活用が可能となり、早期接触の質を高めます。
企業は、職場体験を通じて学生の理解を深め、動機形成につなげる設計が求められます。
広報・ブランディング活動の前倒し
Z世代の学生は、企業の理念やカルチャーに共感できるかを重視します。
そのため、採用広報は「誰に」「何を」「どう伝えるか」の設計が重要です。
SNSや動画、社員インタビューなどを活用し、企業の魅力をストーリーとして発信することで、志望度の向上につながります。
広報解禁前からの情報発信が、母集団形成の鍵となります。
関連記事:採用基準を設ける重要性とメリットとは?3つの要素や設定のポイントを解説
選考プロセスの明確化と短期化
選考の透明性とスピードは、学生の満足度と内定承諾率に直結します。
選考基準やフローを明示し、面接官のトレーニングを通じて一貫性ある評価を行うことで、信頼感を醸成できます。
また、面接回数の見直しや即時対応など、選考期間の短縮も重要です。
学生の意思決定を支援する設計が、辞退防止につながります。
ダイレクトリクルーティングを用いた採用活動
ナビサイト中心の採用から、逆求人型やSNSを活用したダイレクトリクルーティングへと移行が進んでいます。
OfferBoxやdodaキャンパスなどのサービスを活用することで、企業はターゲット学生に直接アプローチでき、ミスマッチの少ない採用が可能になります。
早期からの継続的な接点が、動機形成と内定承諾率の向上に寄与します。
関連記事:ダイレクトリクルーティングとは?特徴や種類、成功させるポイントを解説
まとめ
2027年卒採用は、インターンシップの定義変更や政府主導のルールのもと、より戦略的な設計が求められます。
採用活動の早期化・多様化が進む中で、自社の採用力を高めるには、スケジュール設計と社内体制の整備が不可欠です。
今後の採用成功に向けて、早期からの準備と柔軟な対応を心がけましょう。
関連記事:【採用担当者必見】面接時に聞くべきこととは?基本的な流れや人材を見極めるポイントを解説
関連記事:採用と内定の違いとは?内定通知の注意点や反社チェックについて解説